





 |
 |
 |
 |
 |
 |
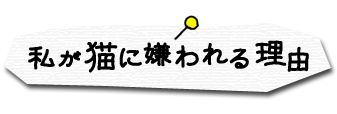 |
|
文・五十畑 裕詞
|
|
第1回 愛犬が怖くて触れない 猫は私が嫌いだ。 少なくとも、我が家の愛猫である花子と麦次郎の2匹は、激しく私を嫌っている。ような気がする。もし猫が人語を話せるなら、私は家に帰ると四六時中猫に罵声を浴びせられっぱなしとなるだろう。 と、妻は言う。 実際、私もそう思う。いや、「最近はそう思うようになってきた」というのが正しい。飼い猫歴が長くなるにつれて、猫の気持ちが少しずつわかるようになってきたからだ。うーん。オレ、なんで今まで猫のことよくわからなかったんだろなあ…。 しかし、思い直したところで時既に遅し。花子は私をただのごはん係としか思っていない。麦次郎にいたっては、私を椅子くらいにしか認識していない。 …ふん、だ。なら、とことんおまえらに嫌われてやるぜ。 で、なぜ私が猫に嫌われたか、である。 もともと、私はどちらかというと犬派だった。猫を飼いその魅力を知ってしまった今となってはどちらかを選ぶことは難しいのだが、昔は「犬犬犬イヌイヌーッ」というくらいの犬派だったのだ。もっとも犬好きとしての私にも、猫好きとしての私同様にかなりの問題があったようだが。 茨城にある私の実家では、マルチーズを飼っていた。ロン毛の印象的な、やたらとキャンキャン鳴く小型犬である。名をイングリという。貧乏人が、柄にもなく外来の純血種に手を出した。…これが失敗だった。 失敗の理由。 ガラッパチで江戸っ子気質の強い父は、この小さな犬にとんでもないしつけをしてしまったのだ。こんな具合である。 1「庭を通りかかった猫はすべて敵だと思え」 父は猫が嫌いなようだ。妹が一人暮らしをしたとき猫を飼っていたのだが、父はまるで変人を見るかのような目つきで妹を見つめていたのを、今でも覚えている。我が家も猫が2匹もいるためか、父は私のマンションを明らかに避けている。そんな父はイングリに「猫は敵だ」と覚え込ませた。猫が通ると「これでもかっ」ってなくらいの激しさで吠え立てるよう、しつけてしまったのだ…。 2「芸をしても必ず褒美がもらえるとは限らない」 室内飼いである。食事のときは当然「なんかちょうだい」と食卓に寄ってくる。父はイングリに覚えさせたお手やチンチンをやらせるのだが、性格が悪いのか、いつもご褒美をじらす。あるいは、あげない。最悪の場合はわさびたっぷりの刺身など、悪意満点のいたずらをする。それが積み重なった結果、我が家のマルチーズはたいへんせっかちな性格となり、芸の動作が超高速になってしまった。目にもとまらぬ速さのお手、すぐにやめてしまうチンチン。芸のあとの「やったんだから、なんかくれよな」と言わんばかりの視線が心苦しかった…。 3「オレにはこいつの気持ちがわからん」 父は若い頃にドーベルマンを飼っていた経験があるらしい。だから、何かにつけてイングリをドーベルマンと比較する。特に、頻繁に鳴く小型犬ならではの性格が父には理解できなかったようだ。キャンキャンと鳴くイングリを見ると、父は必ず「うるさい!」と本気で怒った。イングリは生来負けん気の強い性格だったためか、父に激しく立ち向かう。その結果、「うるさい!」「なんだと!」の悪循環が生じてしまい、イングリはこの上ないほどに無駄吠えの多い犬になってしまった…。 こうして育てられたイングリの性格がどんどんゆがみ続けたのは、誰でも察しがつくだろう。成犬になった頃には、イングリはすでに誰にも手をつけられない暴れん坊と化していた。郵便配達のバイクが通りかかっただけで吠える。客人が自分の嫌いなタイプの人間だと噛みつく。飼い主にも噛みつく。うかつに近づくこともできない。逆襲がこわいから頭をなでてやることもできない。ほとんど野犬のような暴れっぷりなのだ。唯一、毎日食事や散歩などの世話をしていた母だけがこの災難から逃れていたが、父、妹、私の3人は常にイングリのご機嫌ばかりを伺うようになってしまった。つまり、私の家族にとってイングリは最大の脅威だったのだ。 だからだろうか、私の動物好きは少々ゆがんでいて、妻が言うには「変」なのだ。愛犬が怖くて触れないという異常な事態が、今になって私を猫に嫌われるような行動を取らせているに違いない。ああ、トラウマ。 次回からは、私がいかにして愛する飼い猫に嫌われるようになったのか、そのいきさつを語っていきたい。 受け入れられぬ愛ほどせつないものはない。これは人間も動物も同じコトなのだ。
|
《Profile》
|