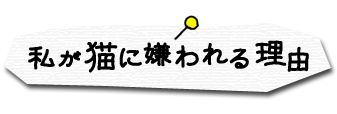|
二〇〇三年十一月
-----
十一月一日(土)
「目に侵食される耳」
九時起床。夕べは雨が降っていたとカミサンはいうが、まったく気づかなかったのはなぜだろう。マンションで暮らすと、意識しないかぎり外の様子はまるでわからなくなる。窓を閉め切るとちょっとした物音はほとんど聞こえなくなるし、カーテンを閉めれば光も閉ざされ、外界とはほぼ完璧に断絶される。それがここ数週間は裏手の建設途中のマンションの防犯用だろうか、プレハブでできた事務所を照らす明かりがカーテン越しに寝室に届き、その明るさが気になって眠れなくなったりしたらどうしようかなどとチラリと考えはしたのだが、たいていの場合はそんなものに気を取られることもなく、蒲団に入ると五分以内には眠ってしまうのが常だから、夜の雨など気づくはずもない。その無神経さ、観察力のたりなさにはわれながら少々呆れてしまう。ひょっとするとカーテン越しの光といっしょに雨の音も感じることができたのではないか、などと想像してみた。光と音は別の情報として知覚するのだから「いっしょに感じる」という表現はおかしいはずなのだが、一度頭のなかを辿り直してみると、音の記憶は光の印象、すなわち視覚的な記憶と対になって覚えていることが多いような気がする。音だけの記憶にも、ぼくはなぜか無意識のうちに視覚的なものを絡めて記憶を捏造しているようで、たとえば今年の夏の長雨の夜に窓を開けて耳を済ませながら眠りについたときの記憶は、地面や屋根を打つ雨音だけでなく、見えているはずのないマンション建設予定地――当時、工事は未着手だった――にできた大きな水溜まりにできた波紋の広がりもいっしょになって覚えているのだが、夜は外に出ることも窓から外を覗くこともなく眠りについたはずだから、そんな観察はしていないはずだ。おそらく、たとえば帰宅するときに見た様子や、翌日出社するまえに外廊下からのぞき込んだときの印象が、音の記憶に侵食しているのだと思う。だが夕べの雨はというと、外の様子は耳はおろか目でも確認していないのだから、想像もできないし、記憶も侵食のされようがない。
午前中は掃除を済ませてから読書三昧。午後より外出。吉祥寺の「ユザワヤ」にて、カミサンに頼まれていた2004年カレンダー用のピンチを購入。つづいて「無印良品」へ。休日に気軽に着れるカットソーが全滅状態なのに気づいたので、二着ほど新調した。「ロヂャース」で猫缶を二十個ほど購入してから事務所により、帰宅。
夕食は豚肉とごぼう、水菜、香菜のナンプラー鍋。西友で購入したナントカさんがつくったのし餠を入れた。餠の食感はナンプラーによく合う。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。ビートルズ、そして木登りの記憶。
-----
十一月二日(日)
「不思議なカレー」
九時三十分起床。外は晴れているようだが、空を仰いでみようという気になれず、すぐにリビングの片づけと掃除をはじめた。遅めの朝食後、モーニング娘。の『ハローモーニング』を見ながらシャツにアイロンをかける。午後からは読書。あれこれ読み散らかしていた本を、さらに読み散らかしてみる。
今日はカミサンがひとり事務所で仕事をしているので、ぼくはにわか主夫だ。得意のカレーを作ろうと思い立ち、いただきもののワインがたまりすぎていたので欧風カレーをつくることにする。しかしただの欧風ではつまらない。牛スジ肉を赤ワインで煮込んでみたら、とろける食感がたまらないはずだ。これを実現すべく、十六時、材料を揃えにスーパーへ。しかし、近所では牛スジ肉が見つからない。とうとう駅前まで歩いてきてしまうが、ここで急に空腹を感じてしまったので、事務所まで歩いてカミサンを誘い、喫茶店「どんぐり舎」で珈琲とマフィンを二人で食べる。食後カミサンと別れ、ぼくは西友へ。やっと牛スジ肉を見つける。急いで自宅に戻り、圧力鍋で肉を煮る。野菜はすり下ろしたものを入れた。二時間後、カレー完成。お味のほうは、どうやらワインが多すぎたようで、カレーの風味があまりしない。カレーという観点で評すれば失敗だが、料理として見れば美味であり、及第である。不思議なカレーをカミサンとふたりで食べた。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。夏休み明けの内田家。
-----
十一月三日(月)文化の日
「十一月三日午後のこと」
誰の作品だったかはまるで覚えていないのだが、『十一月三日午後のこと』というタイトル――だったはずだ――の小説がある。戦前の話だったと思う。季節外れの暖かい陽気のなか、主人公が歩いていると、軍隊が――自衛隊ではなかったはずだ――路上で訓練している。みな暑苦しい戦闘服を着て走っているのが、暑さで弱り、兵士は次から次へと倒れていく。――そんな様子を克明に描写した作品だ。十一月三日といえば、まずは父の誕生日を思い出すのだが、間髪入れずにこの作品を思い出してしまい、はて誰が書いたのだろうかともどかしい気分になりつつも、空をあおいで、十一月三日は晴れることが多い「特異日」だったはずだなあなどとも同時に考え、散歩でもしてみたいと思うのだが、残念ながら今日の空は雨模様で、路上は濡れ、空は重たそうなグレーの雲が低い位置にフラットな感じで広がっていた。九時起床。残念な空に気を取られながら、ごみ捨てをし、部屋に掃除機をかけた。
十時三十分、事務所へ。先月溜め込んでいた経理の記帳を一気に片づける。午後よりカミサンも事務所へ。東京都美術館から絵はがきのオーダーが千枚以上来てしまい、てんてこまいしている。午後は早々に自宅に引き上げ、猫と昼寝でもしようかと考えていたが、大変そうなので材料の紙を、カミサンに代わって買いに行ってやる。あとはいたところで鬱陶しがられるだけなので、いそいそと帰宅する。十五時。
帰宅後は猫をあやしながら読書。麦次郎をケージから出してやると、締め出しておいた花子がさみしそうにフニャンフニャンと鳴きはじめてしまう。麦をケージに入れ、花子をリビングに入れてやると、今度は麦がナアンナアンと鳴きはじめ、出せ出せとはげしく要求する。この連続である。いやになってきたので、ほったらかして昼寝を決め込むことにする。ぼくが寝はじめたら、麦次郎はだいぶ大人しくなった。花子も多少はましになったようだ。猫とはそんなものなのかもしれない。人が起きていれば、甘えようとするのが常だ。
二十時、カミサン帰宅。水炊きで夕食。ワールドカップバレーをチラリと観る。日本対韓国、接戦で日本が勝ったようだ。女子バレーを観ると、身長が高いから服を買うときたいへんだろうなどと余計なことばかり考えてしまう。元全日本の大林、最近レポーターとしてよくテレビに出ているようだが、やはり服には苦労しているようだが、どうなのだろう。女性で一八〇センチもあると、ビジネスライクなセットアップスーツでは威圧的になるし、ソフトでフェミニンなラインの服では体格に負けてしまいそうだ。
夜、父より電話。誕生日のプレゼント、届いたとのこと。カーキ色のブルゾン、気に入ったようだ。「ちょっとイギリスっぽい感じだな」とオヤジがいう。たしかに裏地はチェックになっていたから、そんな雰囲気はなくもない。生地もちょっとメルトンっぽい感じがするので、若いころ仕立屋をしていたことが父は、昔たくわえた知識をもとに、そんな感想をいったのだろう。「これを来て、ベレー帽でもかぶって散歩しようかな」どうやら気に入ってくれたらしい。安心する。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。真実は日常のなにげない会話のなかにある、というのがこの作家の主張でありテーマだと思う。それはこの作品にも如実に表れている。たとえばこんなシーン。主人公であり語り手である高志が従姉妹たちが来ていたときに話題になった、かつてこの風呂にでた影のような幽霊の話を同居人たちに話すと、彼らは毎日のようにその話に夢中になる。一階の部屋を間借りして仲間たち三人と会社を経営している浩介は、若い者たちがこの手の超常現象話をクールなスタンスで愉しんでいることを「怪談の世代」だからと説明する。
□ □ □
「だから『怪談の世代』だって、言ったじゃない」
と浩介が笑った。
「だからね。怪談の世代はお話と現実の区別がおれたちと違ってるっていうかね。現実がうまくお話みたいに切り取られたときに、ワッと反応するっていうかね。まあとにかく、本当の話だとはどこかで感じてないんだと思うんだよ」
「『本当の話という作り話』みたいなもんか」
と私が言うと、浩介は相変わらず笑いながら「いちいち自分の言葉に置き換えないと納得できないところが、もう完全にオヤジだよね」と言った。それをいちいち否定する気持ちもなくて、「おかしなもんだな」と私は言った。
「こうして同じひとつの空間にいるのに、おれと若者たちとで見ているものや感じているものが違うなんて、別々の現実に住んでるみたいじゃないか。
でももっと深い次元まで掘り下げていったら、結局同じ現実に生きているはずなんだけどな」
「『深い次元』って?」
□ □ □
普通の作家なら、会話をとにかく軽いものにして、こういった内容は心理描写にしたり、暗喩的に表現したりするんだろうなあ、なんて考えながらこのくだりを読んだ。
-----
十一月四日(火)
「夢を断つ猫」
空港は暗く厚い雲に覆われている。いつ雨が降ってもおかしくないが、フライトは予定通り運行されるようで、乗客は次々と搭乗手続きを進めている。ぼくはその人波にうまく乗り上げるようにしてゲートをくぐり飛行機のなかへ乗り込んだが、乗り込む瞬間のことがどういうわけか思い出せない。気がつくとすでにぼくは自分のシートのまえにいる。あたりを見回す。シートはほとんどがスタッキングチェアーでできていた。乗客に対し、シートの数は絶対的に不足している。坐りきれない乗客は、機体の隅に「体育座り」でしゃがみこみ、飛行機が離陸のを待っている。彼らの体は、どこから伸びているのかわからない安全ベルトでしっかり固定されている。ぼくはスタッキングチェアーに座ろうとする。すると、そこにグレーのニット帽をかぶり機関銃を抱えた男が二人立っている。男はぼくに銃口を向け「動くと撃つ」と、ハイジャック犯の紋切り型のような科白を口にする。スチュワーデスが横から「お客さまどうぞお従いください」とぼくに忠告するが、ぼくはそんなことは聞き入れるまでもない、コイツラとっつかまえてひどい目に合わせてやると意気込み、スタッキングチェアーをひっつかんで彼らの目のまえへと歩き出す。気の弱そうな男が引き金を引く。ぼくは「ヤベエ」と思いながら手にした椅子を盾にする。銃声はなるが、いやに間延びしているのが気になる。弾丸はなぜかゆっくりと飛び、ゆっくりとぼくが前方へ突き出しているスタッキングチェアーの座の部分に突き刺さり、のこりはしずかにぼくの横をかすめてうしろへと飛んでいく。この一瞬だけ、時間がゆっくりと動いているのだ。すべての弾丸が後方へと流れていくと、ふたたび時間は以前とおなじ速さで流れはじめる。もう一方の男も引き金を引く。ぼくは椅子で体を守りながらすかさずしゃがみこみ、そのままクラウチングスタートの要領で男のほうへ猛然と駆け寄り、ひざ元のあたりにタックルしようとする。バランスを失わせたところですかさず一本背負いで投げてしまえ、
そんな作戦を0.0数秒のあいだに頭のなかでシミュレーションし、実行しようとする。ところがぼくはタックルできない。いつのまにか目の前から男たちは消えている。ぼくの手にあったはずの椅子もない。あるのは毎晩愛用する羽毛布団とタオルケット、それからテンピュールの低反発枕だけである。銃声は聞こえない。代わりにフニャンフニャンというなにかを要求しているときの花子の鳴き声が聞こえ、二度ほど手をカプリと噛まれた。しばらくは夢と現実の境目がよくわからず、蒲団のなかで呆然としてしまった。七時三十分にセットしておいた目覚まし時計のアラームで、ようやく現実に引き戻された。
花子は毎朝こんなふうにしてぼくを起こす。夢の進行を妨げられたのは、久しぶりのことだった。
九時、事務所へ。午前中は事務処理。午後より九段下のD社へ。帰社後はU社PR誌のカンプ用原稿。十九時三十分、帰宅。
帰りがけに書店に立ち寄り、久しぶりに本を買う。夏目漱石『吾輩は猫である』、『夢野久作全集9 ドグラ・マグラ』、野坂昭如『エロ事師たち』、古井由吉『杳子・妻隠』『白髪の唄』。『猫』は、仕事で「猫の視点から見た現代社会」というテーマで文章を書かなければいけなくなったので購入。中学時代以来、二十年ぶりに読むことになる。
夕食は刺し身。麦次郎をケージから出し、花子といっしょに刺し身をすこしだけ分けてやると、二人ともハグハグと音を漏らしながら夢中になって食べている。そしてまた刺し身がもらえるまで、ぼくらのそばでじっと待っている。麦次郎のそばに花子が近寄っていき、危険だ一触即発かと冷や冷やするが、たがいに臭いの嗅ぎあいをしたりするばかりで、感情的な行動に出ない。おたがいの存在をかなりしっかりと認めあいつつあるようだ。麦次郎がちょっとしつこくしたときに花子が肉球で麦をパシリと叩いたが、攻撃といえばそれくらいでしかない。今週末には麦次郎をケージから出してやれるかもしれない。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。家の庭に生える緑を克明に描写している。克明というより、執拗といったほうが正確か。
漱石『吾輩は猫である』も併読しはじめる。こちらは仕事。
-----
十一月五日(水)
「終わらない腕立て伏せ」
延々と腕立て伏せをする夢を見る。目が覚める。腕を触ってみるが、筋肉痛は起きていない。夢をみながら実際に腕立てしていたのではないかと心配になったが、そこまで寝ぼけてはいなかったようだ。安心する。
八時起床。麦次郎との家庭内別居がはじまってから、花子の「起きてよ攻撃」がこれまで以上にひどくなったことはこれまで何度も書いた。ところが花子も麦次郎も互いに相手を許しはじめたここ数日は、花子のぼくの起こし方が、少々なまぬるくなってきた。これは彼女の意識――興味対象というべきか、仲間意識や連帯意識の矛先というべきか――がニンゲンから麦次郎のほうへと移りはじめた証拠なのではないかと思う。
ワイズフォーメンの今期の作品であるステッチギャバのセットアップを来て出社。怪しいほどのオーバーサイズ。ワイズらしいシルエットだが、パンツは細身だ。
九時、事務所へ。天気予報は午後から雨と報じている。空は陽の光を透かす薄くて白い雲のしたに、鼠色の濃淡の比較的はっきりした雲が重なっているように見える。風はほとんどないが、雲はゆっくりと東に向って移動している。午後には雲が動ききってすっかり雨雲と交代、ということになるのだろうか。
U社PR誌、D社PR誌、N振興会ホームページ。L社のLさんから、新規案件の打診あり。前向きな返答をしておいた。
十九時すぎ、帰宅。案の定雨が降りだした。雲のヤツめを拝んでやろうと空を見上げるが、陽はすっかり落ちていて、雲のかたちなどはっきりわかるわけもない。差している傘も視界を遮ってしまう。
『マシューズベストヒットTV』を観る。モー娘。のよっすぃーがゲスト出演していた。吉澤ではマシューの相手はしきれないと痛感する。
漱石『吾輩は猫である』。黒君との出会い。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。木登りの思い出とその考察。そうだ、この小説は考察しっぱなしなのだ。
-----
十一月六日(木)
「迷える落ち葉」
八時起床。花子と麦次郎の関係が修復されつつあるせいで早起きをする必要もなくなったため、朝はギリギリまで蒲団のなかにいるようになってしまった。早起きは慣れると気分のいいものだが、慣れていないと苦痛以外の何物でもなく、したがって多くのニンゲンは早起きは変人的行為だと思い込んでいる。毎朝何時に起きるかという質問に、早朝から仕事がある人が例えば毎日五時に起きると答えたとしよう。聞き手は五時という時間の早さに驚くだろうが、聞かれたほうにしてみれば、毎朝五時に起きるのは必然なのだから、主観的に考えればそれは早起きではなくてただの習慣でありきまりである。彼にとっての早起きとは、四時、三時、二時に起きることにほかならない。
九時、事務所へ。夕べから降っていた雨は弱まってきた。雲が昨日よりも平坦に見える。妙に白っぽい灰色が空全体に広がっているせいか、道端や一戸建ての庭、マンションの植え込みなどで咲いている秋の花の鮮やかさが、いつも以上に際立っている。雨の日は、視線は枯れ葉や落ち葉にはなかなか向わない。雨水に濡れた落ち葉は菌に侵食されやがて腐るのかもしれないが、それを受け止める土は、アスファルトのしたに隠れている。だから濡れた落ち葉は行き場を失っているように見えるのだ。途方に暮れた秋の落ち葉が、アスファルトにペタリと、身を寄せるようにしてへばりついている。
D社PR誌、N振興会ホームページなど。
十四時、ご夫婦でイラストとウェブデザインをやっているNさんがやってくる。作品を見せていただいた。
夕方、外出。新宿のB社にて、U社PR誌の打ちあわせ。B社に伺うときはいつも雨降りだが、今日は午前中で雨はすっかり止み、昼間には青空が広がった。歩くとジワリと汗ばんでくるのがやっかいだ。この季節、温度調節の難しさのために着る服の選択基準がわからなくなって困る。
帰社後は請求書などの事務処理、U社PR誌など。二十時帰宅。
花子と麦次郎の関係修復は、いよいよ最終段階に突入したのかもしれない。麦次郎は花子と遊びたいという衝動を抑えきれず、ケージから出るとなにかとちょっかいを出そうとする。つい先日までは、麦のそんな行動(のしつこさ)にすぐ反応し、シャーと威嚇の声を出して拒絶の意を示していたのだが、今日は威嚇などするふうでもなく、麦の誘いに乗るほどではないが、まあいいか、くらいのノリで応じているように見えてしまう。
漱石『吾輩は猫である』。年賀状に描かれた猫、そして苦沙弥先生の元門下生である寒月くんが登場する。寒月のモデルは、寺田寅彦だという説がある。実際にも寺田にとって漱石は師にあたる存在らしく、寒月が苦沙弥の家に入り浸るのと同様、夏目家にはちょくちょく顔を出していたようだ。
この作品を読むのは中学生以来。この歳になって、ようやく文体のおもしろさやアイロニーの巧みさがよくわかるようになってきた。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。会話はすこしずつ、「庭の記憶」から「家の記憶」へと移行する。
-----
十一月七日(金)
「平穏な一日」
八時起床。九時、事務所へ。N振興会ホームページなど。夕方、少々時間ができたので吉祥寺へ。『群像』十二月号購入。十九時帰宅。
取りたてて書くことのない、平穏な一日。
漱石『吾輩は猫である」。保坂和志『カンバセイション・ピース』。
-----
十一月八日(土)
「再生か改造か」
十時起床。最近はさほど忙しくないというのになぜか疲労はたまっていて、目覚めると体がどろりとした感じがする。これが健康を扱ったテレビ番組でよく取り沙汰される「ドロドロ血」なのだろうか。しかし血がドロドロしているという実感などありはしない。先日も左手の親指をざくりとカッターで切ってしまったが、血はさらさらと流れつづけた。ティッシュで血を拭きマキロンで消毒してから絆創膏をすると血はすぐに止まった。正常な感じがするから、やはりぼくの血はドロドロはしていないのでないか。確認する方法がわからないなからなんともいえないが。問題は体のドロドロ感だ。肉体の疲労に対しての睡眠時間のバランスがとれていないのだと思う。おそらく眠りすぎだろう。惰眠をむさぼるとだらしなくなる。それは精神も肉体もおなじことで、眠りすぎはよくないことだとつくづく思うが、それでも寝坊はやめられず、自分は年老いて死ぬまで休日の朝寝坊をつづけてしまうのだろう。
午前中は掃除、洗濯。午後より外出。自宅改造計画の第二段階であるインテリアのリプレース、その第一歩としてリビング用のフロアテーブルを物色しに、六本木へ行く。なぜ六本木なのか。理由は単純だ。ダイニングテーブルとチェアーとおなじ「Y's
for Living」でフロアテーブルも揃えたいだけだ。以前はここの直営店が代官山にあったのだが、最近六本木に移転したという。ほしい商品はほぼ決まっている。そのショップで一度現物を見てから購入しようという魂胆だ。だが残念ながら、現品は現在雑誌の取材だかなんだかで貸し出し中で、ここにはないという。展示しているショップがほかにないか――新宿伊勢丹をはじめ、都内何ヵ所かのデパートで取り扱っている――調べてもらうが、どこもスペースの都合で在庫はないという。しかたないので、現品が返却されたときに電話をもらい、もう一度ここに来ることにした。
ついでに六本木ヒルズに立ち寄る。建築物としては陳腐なデザインだが、都市としてここは作られているようで、全体のバランスはいいように思えるが、居心地、住み心地、働きごこちはここで住んだり通ったりしてみないことにはわからない。シト襲来のオブジェを見る。なるほどこれは造形的におもしろいが、街の雰囲気とは絶望的にあっていないと痛感する。なにしろ人が多いのだ。そこにシトときた。ニコニコしながらウロウロする人々の表情も行動も心境も、シトにはとうてい似合わない。これがもしゴジラだったらと想像する。ゴジラと笑顔は似合うのではないか。なぜならゴジラは国民のアイドルだからだ。
チラリ建物のなかをのぞいてみるが、どこをどうみたらいいやら迷う。いわゆるインターナショナルブランド――グッチやプラダやヴィトンなど――にはまるで興味もなく、空腹は感じるが興味をもったレストランもなく、ましてやこんな場所でまるで落ち着けないタリーズコーヒーやスターバックスに入るほどの酔狂じゃない。こじゃれた雑貨やインテリアを扱うショップをグルリ回ってから、いそいそと退散する。
六本木から渋谷方面へと歩く。そもそも六本木自体ほとんど来たことがなく――サラリーマン時代に「深夜の六本木のキャバクラ打ちあわせ事件」というのがあったが、その話は後日に譲ろう――、したがってこのあたりを歩いたことなど一度もないから、目にするものすべてが新鮮なのだが、いっしょにいたカミサンはサラリーマン時代にこのあたりにクライアントがあったのだそうで、「変わった」を連発しつづけている。古い街並みはみな壊され、マンションやビルが建設中だ。こういった風景を見ると、街は再生するのではなく改造されているのだと感じる。改良なら許せるのだが、と思いながら歩きつづける。
麻布の交差点で落ちついた雰囲気のカフェを見つけたので、入店して一休み。どうやらアジアンな食事もとれるカフェらしい。店内は大人が多くて安心する。喫煙率も少ない。ぼくはベトナムのビール、カミサンは蓮茶を、そしてサンドイッチを二種類注文する。ビールはちょっとタイのシンハーに似た感じだが、もっと口当たりは軽い。サンドイッチはヨーロッパとアジアの融合という感じか。パンはフランスパンっぽい。ベトナムはフランスの植民地だったかと記憶をたぐるが、思い出せない。調べてみようと思うが、きっと忘れてしまうだろう。
青山の骨董通りを抜け、そのまま渋谷まで一気にあるく。山手線に乗り、新宿に移動。伊勢丹の「ワイズフォーリビング」へ。ラグマットを注文する。今日はフロアテーブルだけでなく、ラグマットも買う予定だったのだ。両方とも直営店で買うつもりはなかった。伊勢丹ならアイカードで7%割引になるからだ。テーブルは直営店で現物を見てから、伊勢丹で購入しようと思う。
カミサン、ついでに服がみたいというので「ワイズ」へ行く。勢いでスカートを購入してしまう。ぼくは何も買わず。
小田急などを回ってから帰宅する。
夕食はすき焼き。といっても、肉は安めのものを使う。
漱石『吾輩は猫である』。迷亭に担がれる苦沙弥。ところで苦沙弥はまだ名前を紹介されていない。寒月、東風、迷亭は登場したが、まだ苦沙弥は「先生」のままだ。
-----
十一月九日(日)
「選挙の日」
トリたちの鳴き声で目が覚めた。と書くと爽やかな目覚めのように思えるが、しょせんはセキセイインコの鳴き声である。キョロロロロロギョギョギョギョギョゲッゲッゲ、とけたたましく騒がれては、爽やかもクソもあったもんじゃない。十時。
鳥籠掃除、掃除、洗濯。午後より選挙に行く。ウチの選挙区は石原伸晃が立候補している。誰に投票したかは書かない。
「それいゆ」でケーキを購入。百円ショップ、スーパーを回ってから帰宅する。
空模様がどんどんあやしくなってきた。雲は墨っぽさを増し、JRの高架線下に入ると、夜のように思えてくる。光が足りないと、木々の葉の色の微妙な具合がわからなくなる。陽光に照らされた葉も雨に濡れた葉も季節を十分に語ってくれるが、どんよりと曇っただけの空は、季節を誤魔化してしまうのではないか。そんなことをぼんやり考えながら歩く。
夕食はモツ鍋。休日は鍋ばかり喰ってしまう。手軽だからだ。
食後は日本テレビの選挙速報を観る。民主党、躍進などと言われているが、それは以前からの比較で評価しているからで、実際は苦戦といったほうがいいだろう。二大政党制まではもうすこし長くかかりそうだ。
漱石『吾輩は猫である』。ダラダラとした日常における些細な出来事がつづくのは、保坂和志の作品とつうじるところがあると思う。それが漱石の現代性なのかもしれない。保坂との違いは、保坂は描写のあとにふと哲学的・科学的な論証が顔を出すが、『猫』の場合は語り手が名無しくん(猫)であるからさほど理屈っぽさはなく、そのぶん登場人物たちの間抜けっぷりが際立ち、それがアイロニカルな文体と作品の個性を生みだしている。
-----
十一月十日(月)
「眠れない夜/鞄が悪い」
新聞を読むのは好きで、自宅では朝日を、事務所では日経を取っている。すべての記事を熟読するわけではないが、一通り――朝日はさぼることがあるが、日経は一通り――見出しくらいは目を通す。気になる記事があれば、読む。新聞記事は起承転結の結からはじまって起承転とつづくから、どこで読み終えても意味が通じる。ここ二三年は政治欄がおもしろかったように思え、したがって今思い返すと昨日の衆議院選挙をぼくはかなり楽しみしていたふしがあるのではないか。選挙を一種のエンターテイメント、たとえば特定のチームのファンというわけではないが野球は好きでスポーツ新聞には必ず目を通し、その年の戦況につねに目を光らせる野球マニアとおなじような感覚で、政界ウォッチングをレジャーとして愉しんでいたように思えるのだ。そのためであろう、夕べは蒲団に入り目を閉じても、「○○氏が当選」「××氏、無念の落選」そんな声がどこからともなく聞こえてきくる。瞼には嘘くさい笑みをたたえた選挙ポスターの図柄や新聞などでよくみる立候補者一覧にあったバストアップの角版写真が自然と浮かんできてしまう。ウトウトしだしても、すぐに「ばんざーい、ばんざーい」と叫ぶオヤジどもの声が頭に響き渡り、ちっとも寝むれやしないのだ。羊の頭数を数えても、六匹目あたりが政治家の顔になる。菅直人の声のしわがれが気になる。阿倍晋三は眠そうだが居眠りしていないだろうかなど、つまらないことまで気になりはじめる。眠れない。
七時起床。四時に花子が激しく騒いでご飯をせがんだせいもあり、ほとんど眠れていない気がする。今日は事務所の可燃ゴミを出さなければいけないのだが、八時三十分には集荷してしまうので、八時前に行かなければいけない。というのに朝の身支度はどういうわけか――もちろん睡眠不足もたたっているのだろうが、それ以前の問題として、なんだか調子が狂っていて遅々として進まない。慌てて事務所に向う。外はようやく冬らしく肌寒さを感じるが、それが晩秋の雨のおかげで空気はさらに冷え、あるいているとなんだかみじめな気分になってくる。みじめに思えるのはおそらく寝不足だからだろう。そんなことばかり考えながら事務所の前の通りにさしかかったとき、ゴミ集配車を見かけ、これはヤバイと冷たい雨のなか全速力で走る。なんとかゴミは出せそうだ。鞄から鍵を取り出しドアを開けようとするが、今度は鍵が見つからない。自宅に電話すると、土曜日に使ったショルダーバッグのなかにはいっているという。どうやら仕事用の鞄に入れたつもりが、ショルダーのほうに戻してしまったらしいのだ。雨のなか泣く泣く自宅に戻ることにする。もちろんこのあいだにゴミ集配車がわが事務所のまえを通過したことは説明するまでもないだろう。すべて寝不足と選挙が悪いことにする。それから鞄も悪者にする。じつは今朝、今まで使っていた鞄が壊れてきたので、まだ壊れてはいないがしばらく使っていなかった鞄に中身を入れ替えたのだ。壊れかけた鞄、デザインは気に入っているのだが、とんでもないトラブルメーカーなのだ。街中でファスナーが突然ビャーと開き、なかみが路上にばらけたことは何度もある。これはファスナーが側面のしたのほうまで付いていることが原因で、なまじファスナーのすべりがよすぎたから起きたトラブルだ。ショルダーベルトは、なぜか突然ブチリとはずれ、鞄が路上に落下することが何度もあった。そのうちベルトを止めるリングの付け根の部分がほつれてきて、すぐに穴が開いてしまった。購入後二、三ヶ月のことである。鞄のなかにいれておいた万年筆のボトルインクの蓋が突然馬鹿になり、鞄のなかにインクが広がる大惨事となったこともある。最後のトラブルは鞄が原因ではないが、こうなるともう使うのが嫌になる。だがデザインが好きなので、今まで我慢して、そして工夫を加えながら――ファスナーにストッパーをつけたり、ベルトを別のものに取り替えたりすることでトラブルを防いだ――使いつづけてきたのだ。でも、やはりトラブルは起きる。鞄を変えたら変えたでトラブルが起きた。もう嫌だ。使わない。
午前中は事務処理。午後より小石川のL社へ。O社キャンペーン企画の打ちあわせ。銀座に寄ってから帰社。O社キャンペーンのネタを少し考えてから帰宅する。
家に帰ると、書斎に猫のウンコが転がっている。よく見るとウンコをなびったあとがある。花子の尻をみると、案の定立派なウンコが股のあたりにプランプランとぶら下がっていた。すぐに花子を捕獲し抱きかかえ尻のウンコをカミサンと二人がかりでもぎり取る。長毛種の猫は下の世話がちょっと大変だ。
漱石『猫』。苦沙弥の訳のわからない知恵熱の体験談。そして三毛子の死。身近な存在の唐突な死に対し、名無し君は冷静に対峙している。これは視点を異化しているが故にできる描写だと思う。ニンゲンが語り手であったなら、ここに必ず過度な「感情」が紛れ込む。感情は描写の力を弱めてしまう。だからぼくは、ひどく感情的な作品は嫌いだ。文学に限らず、絵画も音楽も、である。感傷的でありながら、感傷的であることを否定する。それが悲しみを表現するための究極の手法なのではないか、なんて思っている。
-----
十一月十一日(火)
「『時雨』という季語」
時の雨と書いてしぐれと読む。昨日からつづく雨は、強まったかと思えば止んだように思え、しかし雨足は途切れずに降りつづけている。こんな気まぐれな雨を「時雨」というのだと思っていたが、どうやらこれは晩秋から初冬にかけて降るまばらな雨のことだけを差すもので、俳句の季語にもなるらしい。なるほど梅雨時の雨足の強弱こそはあれ、止む気配は一向に見せぬ雨を時雨と呼んだりはしない。今朝も空は冷たい雨に濡れている。八時起床。
リフォームしてから、室内外の気温差が今まで以上に開いたように感じられる。おそらく床材をカーペットからクッションフロアーに変えたためだろう。ビニール系の素材は羊毛などより保温性が高いはずだ。冬は心地よいだろうが、夏はいったいどうなることか。あまり想像したくない。
午前中は予定がなかったので十時に事務所へ。事務処理や新聞の整理――仕事で使えそうな情報の整理――などに時間を費やす。
昼食はひさしぶりに「それいゆ」へ。新メニューの「シーフードピラフ」を試してみる。エビ、イカ、ホタテの御三家が豊富で食べごたえがある。
午後からも事務処理など。夕方L社のN氏と打ち合わせをする予定だったが、得意先都合でキャンセルになってしまう。残念だ。二十時帰宅。
テレビ『踊るさんま御殿』を観る。瀬川瑛子が今シーズンのヨウジヤマモトを着ていた。ちょっとショック。
漱石『猫』。金持ちの金田さんちの鼻子の家を偵察してくる名無し君。シニカルでアイロニカルな視点。主格の擬人化による視点の異化。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。妻の機嫌の悪さから夫婦という関係の奥底に潜む何かをさらりと語ろうとする主人公。保坂はとことん日常生活に――本作の場合は「家」を中心とした生活――こだわりつづける。
-----
十一月十二日(水)
「いやにまぶしい/いやになる」
八時起床。昨日一昨日とつづいた時雨は眠っているうちに止んだようだ。まるで気づかなかった自分に唖然とする。秋の夜長というが、空模様の悪い日はそんなことはまるでわからず、ただただ惰眠をむさぼるばかりだ。何度か鼻子に、じゃなかった花子に――「鼻子」は漱石の『猫』に出てくる人間の女だ――起こされたりはするが、気密性の高いマンションのなかには夜の長さも外気の秋らしさも空模様も伝わってこない。空を見る。薄い雲が幾筋も浮かんでいるが、青空だ。朝日とはもう呼べないかもしれない八時の陽の光がいやにまぶしい。
九時、事務所へ。午前中は電話で打ち合わせなど。午後より外出。十三時三十分、D社PR誌の打ちあわせ。大慌てで帰社。ちょっとだけ事務所に戻り、すぐにカイロプラクティックへ。帰社後はO社のノベルティの企画。二十時帰宅。家についてから、今日は夕陽が見られなかったことを悔やむ。ばたばたと動き回っていると、景色を楽しもうという気がなかなか起きない。自分の心の狭さ、感性の乏しさがちょっといやになる。
夜はテレビ『トリビアの泉』など。
漱石『猫』。鼻子がいる金田家の面々を観察するのがやめられなくなってしまった名無し君。そして細君のハゲという、本作でもとくに有名なエピソード。
保坂『カンバセイション・ピース』。横浜球場での野球観戦。横浜ベイスターズが負けているときの心境と視点の変化。
-----
十一月十三日(木)
「かっこ悪い自分の像」
八時起床。朝起きたときの体がこわばった感覚は苦手で、寝室からトイレを経由してリビングに行くまでのわずか数メートルの廊下を歩くのがつらく、おまけにカッコ悪く思える。自分で自分の姿を見ているわけではないのだが、頭のなかには寝癖だらけでガニマタ気味に廊下を歩く姿が妙にリアルに浮かんでくる。おそらく自分の足取りの感覚とそれ以外の記憶とが重なり合って、実際には見たはずのない自分の歩く姿が頭のなかに像を結んでいるのだと思う。保坂和志も『カンバセイション・ピース』で同じようなことを書いている。
九時、事務所へ。掃除を済ませたところでT社のP氏より電話。二十分も話してしまう。会って打ち合わせをしたほうがよさそうだと思ってしまった。十一時、吉祥寺へ。O社プロモーションのための情報収集。「まめ蔵」でカレーを食べてから帰社。
午後からはO社プロモーションの企画書作り。二十時帰宅。
毎年のことなのだが、この季節になると必ず着る服を選ぶのに困る。朝夕が肌寒くなってきたが、だからといってまだコートを着るのは早すぎるような気がする。昼間、妙に陽射しがあたたかくて汗ばむときもあるのだから、ジャケットの下はシャツにするかニットにするか、ニットでも薄手でいいのかちょっと厚めでも構わないのかが判断できず、結局前日に街ですれちがった人たちの服の重ね具合やモコモコ具合を参考に、その日の服を決めることになる。
漱石『猫』。同窓生である鈴木君の名刺を便所に捨てる苦沙弥。鈴木君が坐ろうとした座布団にいち早く陣取って彼を困らせる名無し君。
-----
十一月十四日(金)
「人の話を聞きなさい」
八時起床。九時、事務所へ。仕事がさほど忙しくないときは苛々する時間がないぶん呑気になるように思えるが、実際はそうではない。職業柄か、歩きながら仕事の企画を考えたり文章の構成を組み立てたりキャッチフレーズの切り口をひねり出したりすることが多い。では暇になったらどうなのか、ただぼんやり歩いているだけなのかといえばじつはそうではなく、頭のなかで目に見えたものをことばに置き換えていること、つまり描写の訓練をしていることが多い。どうやらぼくは歩きながらなにか考えていないと落ちつかない質で、放心とか無心とか、そういったことができないらしいのだ。それは歩いているときだけでなく、日常生活のなかでも顕著らしく、たとえば帰宅して服を着替えているあいだにカミサンになにかを話しかけられても、まるで聞いていないようなのだ。ようするに、着替えているときは着替えていることを頭のなかで綴っているか、あるいはまだ仕事のことを考えているかのどちらからしく、そこにはカミサンのことばが入り込む余地はないらしく、それが原因でぼくは頻繁に怒られる。「人の話を聞きなさい」朝の通勤のときは、人の話を聞くことなく、ひとり考えに没頭したり目に見えた西荻窪をすっぽり覆う季節や天気、そのなかに存在するニンゲンやらドウブツたちの様子をブツブツ脳内で文章に仕立て上げたりできるから、まあ呑気といえば呑気なものだが、呑気じゃないと言いきることもできそうだ。
朝からD社PR誌のための資料の読み込みに集中する。とある企業のMAN(Metropolitan Area Network)の取材をするにあたってのお勉強だ。今回の取材先は、敷地内にある十五の工場をリング状のネットワークで接続しているそうだ。通常のLAN間接続によくあるスター型のトポロジではないため、冗長化技術や障害対策はより高度なものが求められる。今回は「DPT」という技術を使っているそうだ。
決して読み慣れているとは言い難い技術資料と取っ組み合いをつづけたせいか、夕方には頭がパンクしてくる。ほかの案件のメールに返答を出したりスケジュールの確認をしたりして気分転換してみたが、仕事を別のものに切り替えただけだから抜本的な改善、つまり完璧な気分転換にはなっていない。二十時、一段落ついたので帰宅する。
夕食はクリームスパゲティ。白ワインを一人で三分の二ほど飲んでしまった。
漱石『猫』。鈴木君と、寒月の結婚話について話している苦沙弥先生のところへ、例のごとく迷亭が乱入。『猫』の魅力は、名無し君の視点から見た日常生活の「異化」だけでなく、キャラクター設定によるところも大きいと思う。実業家である鈴木君は、学問の道を選びダラダラと高い知識を無駄に蓄えたり浪費したりしつづけている苦沙弥、寒月、迷亭とはじつに対称的。教養のある苦沙弥と頭にハゲがある、(苦沙弥から見れば)無教養な細君の対比もある。名無し君と俥屋――だったかな?――の黒、名無し君と死んでしまった深窓の令嬢ならぬ令猫三毛子の対比もある。相反するものたちがぶつかり合うことで生まれる「ズレ」が、文章をユニークな方向へと導くのだ。
-----
十一月十五日(土)
「よくわからん体調」
十時起床。猫たちはかなり仲良しになった。以前の関係にもどるまでもう少しの辛抱だ。だが今日は辛抱すべきことがほかにもある。アタマが痛いのだ。これはどうやら夕べのワインのせいらしい。ぼくの辛抱はまだつづく。鼻水も出る。目も痒い。目が痒いのはおそらくアレルギーだから、医者に処方してもらった目薬を差しながら堪えるしかない。鼻水はひたすらかむしかない。だがよくよく考えると、頭痛と鼻水はひょっとするとおなじ原因によるものではないのだろうか。風邪? よくわからん。
午後より六本木へ。「Y's for Living」のショールームへ行き、先週見そこねたフロアテーブルを見せてもらう。新宿へ移動。伊勢丹の「Y's
for Living」で、カミサンの伊勢丹カードを使って購入することに。そうしたほうが、カード会員優待で安くなるのだ。
ついでに紳士服バーゲンの会場へ行き、マフラー、パジャマなどを買う。十九時、荻窪着。西友で食材を買ってから帰宅。
夕食はモツ鍋。ニンニクを大量に摂取し、風邪薬を飲んでからすぐに蒲団に入った。二十三時。
漱石『猫』。話は苦沙弥、鈴木君、迷亭の下宿時代の思い出へ。ちょっと迷走気味。
-----
十一月十六日(日)
「確信の尻臭」
九時。昨日の体調不良は風邪のせいなのだろうか。それともワインの宿酔いか。よくわからないままに風邪薬を飲みすぐにグースカと眠ったのが、その判断がよかったのか、頭痛は取れているものの、まだ重たい感覚だけは残っていて、それが全身をごくごく軽くではあるが、しびれさせているような気がしてしまい、しゃきっとすることができないのだが、休日なのだからしゃきっとする必要もないさと自分に言いきかせ、鈍るアタマを枕に埋めさせて惰眠をむさぼろうとするが、陽が昇ると嫌でも目が覚めてしまうタイプだし花子もインコたちもやかましく騒ぎ立てているともう蒲団のなかにとどまっていること自体が苦痛になり、釈然としない気持ちで起床した。
目の痒みと鼻水はやはりハウスダストが原因かと推測する。ハウスダストのもっとも多く発生する場所の掃除を念入りにすれば、鼻水はピタリ止まるはずだという仮説を立ててから掃除機のスイッチを入れる。家中くまなく掃除機をかけたあと、先週購入したラグマットの毛羽を、何度も丁寧に吸い取った。それが功を奏したのか、今日はさほど目は痒くない。
十一時、遅めの朝食。モー娘。の番組を見ながらアイロンかけ。午後からは例によって乱読。乱読しすぎて、集中できず。なにを読んだかがよくわからなくなる。
夕方、ひとりできゅーを連れて鳥の病院へ。検便をすると、またバクテリアの量が増えているとのこと。新しい薬を処方していただく。ぷちの元気のよさがきゅーの食事を妨げているかもしれないので、ぷちとは別居すべしとの指導も受けた。
帰宅後、さっそく予備の鳥籠を用意し、二羽を別居させる。ぷちを予備の籠へ入れようとしたとき、カミサンめすばしっこくチョロチョロするぷちを捕まえようと尻尾をにぎったら、そのままズルリと尻尾の毛がすべてまとまって抜けてしまった。だから今、ぷちのお尻はみょうに短い。幼女のおかっぱ頭のようになってしまった。
夕食は、ミツカンのコマーシャルでやっていた豚肉と大根と水菜のしゃぶしゃぶをやってみようとしたのだが、豚肉はなかなか熱が通らないわ、大根は素人では薄く切れないから箸でつかみにくいわ、豚肉といっしょに食べにくいわで、いいことがひとつもなし。味だって、特筆すべきものがあるわけではない。ようするに豚鍋なのだ。結局面倒になりしゃぶしゃぶせずにすべての具を鍋のなかにぶち込んで、水炊きと変わらない食べ方をした。そのほうがうまい。
ところで猫だ。今日は麦次郎をケージに入れたりせずに、一日中ほったらかしにしてみた。花子がうろうろしていると麦もスッタカタとやって来て花子の横をスッと通りすぎるのだが、そのとき花子はふっと体を横に向け、麦の尻のニオイをクンと嗅ぐ。そのあとは二匹ともおたがい我関せずといった態度でアッケラカンとしているので、これはもう大丈夫だろうと判断した。おそらく二匹とも相手は少なくとも敵ではなく、だから怒る必要もない、むしろ仲良くしておいたほうが楽しそうだということが、尻の臭いを通じて理解できたのだろうとぼくは思う。この日記を書いている夜中になっても、二匹の関係がおかしくなったりギクシャクしたり大爆発したりすることはない。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。横浜ベイスターズが負けると悔しい、ということが、延々と書き連ねてあった。苦笑。
漱石『猫』もちょっとだけ。
-----
十一月十七日(月)
「秋の終わり、冬のはじまり」
朝目覚めると、今日は寒いだろうという予感めいたものはたしかに感じるのだが、それが本当に「予感」なのか、それとも無意識のうちに得たなんらかの情報に基づいた「推測」であるのかは、じつのところよくわからない。ダラダラと無駄に過ごした日曜日ではあったが、ニュースや天気予報をテレビで見たような気はするのだが、記憶を辿ろうとするとそれはたちまち曖昧なものになる。それが積もり積もると、ニンゲンはだんだんいい加減な存在になっていくのだろうなどと考えながら起床。八時。『ズームイン』の天気予報によれば、今日は昨日より五、六度冷えこむとのことだが、それでも気温は十六度くらいはあるはずだから、さほど寒さなど感じぬだろうと高を括りつつも、リビングの窓にうっすらと付いた結露に、もしや外は寒いのでは、と一抹の不安を感じながら、夕べ食べ残した鍋でおじやを作り、朝食にする。
九時、事務所へ。マンションのエントランスから一歩外へ出れば、朝食のときに漠と感じた不安はみごとに的中したようだ。高く広がる空の色は柔らかな秋のわずかに暖色を帯びた青ではなく、凛とした冬の気配を感じさせる別の青だ。風も強い。落葉しつつある広葉樹の枝が風を切るピュウゥウという音を聞き、とうとう来たかと身構えるようにジャケットの襟を立てた。事務所に着き、インターネットを見るとやはり今朝の風は今年初の木枯らしだったのだそうだ。冷たく吹き下ろす初冬の風は、秋を携えたままの広葉樹から黄葉した葉をピュウゥウという音とともに引きちぎっていく。今日から数ヶ月、寒さと向き合う日々がつづくのかと思いながら仕事をはじめる。
午前中はD社PR誌の取材準備。「えんず」にて昼食。秋鮭西京焼定食にした。あえて「秋」とつくメニューを選んだのは、とうとうやって来てしまった冬に対する最後の悪あがき、拒絶の意図ということか。もちろんオーダーするときはそんなことはまったく考えもしなかったのだが、食べ終わってからふとそんなことを考えてしまう。
午後からは比較的時間に余裕ができたので、資料を整理したり読み込んだりして過ごす。十八時、無事平穏に業務終了。
夕食の買い物を済ませ、十九時ごろ帰宅。猫たちは平常心かつマイペースに今日の午後を過ごしたらしい。数週間前の険悪な状態は嘘のように解消されたのだが、麦次郎が花子にしつこく迫りすぎてときどき怒られたりすると、元の木阿弥かと心配になるが、そこまでひどい状況にはならないのでひとまず安心する。これは今までの関係にもどったと解釈すべきなのか、それとも二匹が新たに関係を築き直したと解釈すべきなのかがよくわからない。猫にももちろん記憶というものはあるわけで、仲直りしかけていたころにおたがいの尻の臭いを嗅ぎあっていたのは、おそらく彼らの記憶は視覚や聴覚だけでなく、嗅覚によっても深く刻まれているということなのではないか、臭いで記憶を――仲が良かったころの記憶を――呼び戻そうとしているのではないかとぼくは思う。だがその一方で、ひょっとすると嫌な過去はすべてなかったことにし、新しい関係を築いたのかもしれないともちょっとだけ思う。ドウブツは本能的に「忘れる」ことで生き続けるものだという説をなにかで読んだことがあるのだ。ニンゲンは怒りや悲しみを引きずりながら生き、苦しみ、それが時とともにすこしずつ癒され、恢復する。やがて悲しみは心のどこか深い部分に沈んでいって、記憶だけが――そのときの感情を左右したりすることなく――残る。だがドウブツは、怒りや悲しみと記憶がひとつづきになっているようで、そういった感情から抜け出すために、彼らは記憶を消してしまう。忘れるというのは生き抜くための知恵なのだ、というのがその本だかなんだかの趣旨だったのだが、ぼくはそんな説は支持したくない。ドウブツもニンゲンも、きっと現実世界と記憶の間で揺れるように生きるものなのではないだろうか。よくわからんが。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。部屋と家族。
漱石『猫』。苦沙弥先生宅に泥棒が侵入。それを観察する名無し君。
-----
十一月十八日(火)
「ギョギョギョの意味」
八時起床。昨日からの冬型の気圧配置の恩恵で関東地方は今日も快晴だが、朝の冷え込みは一気にきびしくなったように感じられる。しかし気密性の高いわが家はそんな微妙な外気の変化がまるで伝わってこないせいか、インコたちは季節外れの陽気さで、ビャースカと朝から大騒ぎをしている。もっとも騒ぐのには彼らなりの訳がある。週末にきゅーを病院に連れていったところ、同居禁止令が出てしまったからだ。鳥籠を二つに分けてから二晩がすぎたのだが、以前二羽とも環境の変化には適応できていないようで、つねにおたがいを呼びあっているようである。セキセイインコの鳴き方はギョギョギョ、ゲッゲッゲ、ピヨヨヨ、キョインキョインと多様なのだが、それぞれなんらかの意味、いや意味という言葉は適当じゃない、なんらかの感情が込められているのは確かなようで、今朝の大騒ぎはやはり籠を分けられたことから来る不満、さみしさ、互いをもとめる気持ち、そんなものから発せられているのではないかと解釈してみると、ニンゲンもドウブツも感情を持つ生命体という意味ではなんら変わりないということが、ココロに滲み込むように理解できる。アタマではなく、ココロ、気持ちで理解する。そんな感じだ。
九時、事務所へ。午前中は吉祥寺で工具などを購入。「武蔵野文庫」で昼食。井伏鱒二の書が飾られた壁に面したテーブルに座り、ここの名物のカレーを食べる。
午後からは資料の読み込みなど。夕方、N不動産チラシの元原稿が到着したので、さっそくコピーアップにとりかかる。ほか、O社ノベルティの見積、アミューズメントメーカーE社の企画など。スケジュールがあわず、ヘアケア用品会社Nの企画の仕事をお断りすることに。二十一時帰宅。
猫たちの関係は修復できたが、必ずしも以前とおなじというわけではないというのが、麦次郎の行動から読み取れる。花子への接し方が微妙に違うのだ。たとえば歩み寄るときの足取りが違う。見つめるときの視線が違う。一歩一歩が、視線のひとつひとつが、今までよりほんのちょっとだけ力がこもっているように見えるのだが、何が麦次郎を力ませているのかはいまひとつよく分らない。変化はごく微妙なもので、こうして言葉で描写しようとしても的確な言葉が見つからないほどのものなのだが、壊れた関係を直すという行為に完全さなど求めてはいけないということなのだろうと一人納得してみる。ズレは必ずあるはずだ。問題は、そのズレがどの部分に生じているかということではないか。
ぼくたちの猫に対する接し方も、今後微妙に変わるのかもしれない。その変化に、猫たちはきっと的確に応えてくれるはずだ。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。風呂場の幽霊の話はまだまだつづく。
漱石『猫』。苦沙弥先生、多々良三平君にもらった山の芋を盗まれる。
-----
十一月十九日(水)
「西荻の緑、小石川の緑」
七時五十分起床。今朝の空はどうやら雲に覆われているようで、リビングは陽が差さずうす暗いせいか、トリたちは昨日ほど元気になくこともなく、ひっそりと静まり返っている。テレビをつけるのがはばかれるように感じる。
九時、事務所へ。通勤途中にある広い敷地の屋敷に背の高い木々が雑木林のように群生していたのだが、屋敷が潰されその跡地にマンションが建てられることになってしまい、木々は四分の一程度を残して、みな切り倒されてしまった。普段敷地内に立ち入ることは当然許されないわけなので、塀沿いを歩きながら幹の太さや梢の広がり、葉や花の育ち具合、枝に止まる鳥たちなどを、見える範囲内でぼんやりと観察するだけだったのだが、やはり街並みを形成するうえで雑木林は重要な役割をしていたようで、散歩が似合う西荻窪の街が一転してつまらない住宅街に堕してしまったように思えてしまう。梢の重なりは織られた布地のように厚みを帯び、それがあたり一帯をゆるやかに包み込んでいた。裸んぼうにされた敷地は、布地をまとうのではなく、コンクリートと鉄筋に固められるのを望んでいるのか。人間は、骨が折れれば針金と石膏で固めて治癒するまでじっと待つ。だが土地は一度塗り固められてしまったら、もう治癒することなどないのではないか。今までこの土地がまとっていた布地が、急に高級品のように思えてくる。
十時三十分、小石川のL社へ。E社POPの打ちあわせ。
茗荷谷の駅前の通りを右に折れ、しばらく歩くと左手に桜並木が現れる。ここは歩道が広々としていて、歩いていてとても気分がいい。十メートル程度の間隔で並ぶ桜の木は、いったいいつごろに植えられたものなのか。黒々とした木肌の幹は太く、人間ひとりが腕を広げたくらいでは到底かかえきれないほどに成長している。それが百メートル以上に渡って、道の左右両側にずらりと続いているのだから壮観だ。じつは花の咲くころにここを訪れたことはない。かすかなピンク色に染まった可憐な花びらが開き、舞うのを見るまでには、まだ四ヶ月ほど待たなければならない。それまでは幹の太さや梢の広がりや、葉の黄葉や散り具合を見るよりほかはない。桜の葉に黄葉ということばを使うのは、ちょっとした抵抗がある。翌々見てみると、散り際の葉の色はじつに多様で、緑色が消えかかっているものの、まだほんのりと生命力のある色彩を残したまま落ちる葉があると思えば、黄土色に変わりカサカサになって散る葉もある。路上に散らばる落葉の色は、一言では言い表せないほど豊かな――豊かだが、ちょっと切ない――色彩を帯びている。だが視線をうえにやると、ほんのすこし水々しさを保ったまま、上質な紅茶を淹れたときのような、濃いオレンジ色に輝いている葉がまだまだ枝に残っているのにすぐ気づく。黄に変わりかけた緑、黄土色、オレンジがつくる点描が、道に沿って重なりながら伸びていく。葉と葉と枝が交差する隙間から、うすい灰色の空が見えた。冬になれば葉はすべて落ち、点描はすっかり姿を消す。
十四時帰社。 N不動産定期チラシ、O社ノベルティ企画、E社POPのコピーなど。二十一時、終了。「それいゆ」で夕食を採ってから帰宅する。
『マシューズベストヒットTV』を観る。ゲストは東野幸治。愛読書として『ゴルゴ13』を紹介していた。ゴルゴのことをまったく知らないマシューは、日本人男性としてモグリである。どうやらマシューもとい藤井隆は、少年時代はマンガや小説はほとんど読まず、アイドルばかりに夢中になっていたようだ。『ドラゴンボール』と『北斗の拳』の区別がつかないのは重症である。根本的な治療が必要だと思うが、よく考えたら治療などしなくても彼は十分生きていけるし、芸能界でもやっていけるのだろうから、まあ一生マンガなど読まずに生きるがいいさ。
漱石『猫』。鼠を捕ろうとして失敗する名無し君。苦沙弥の家でえらく長く打たれたそばを喰ってむせる迷亭。カエルの目玉を再現するために、ガラス玉磨きに専念する寒月。迷亭のモデルはぼくが持っている新潮文庫の解説ではとくに触れられていないが、よくよく考えるとこれは二葉亭のもじりなのかもしれない。たしか漱石は『長谷川君と余』という小品を書いていたはずだ。読んだことはないのだが、長谷川君とは長谷川辰之助、つまり二葉亭の本名のことかな、なんて勝手な推測をしてしまうが、実際のところはどうなのだろう。日本文学史にはさほど詳しくないので、このあたりのことはよくわからない。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。伯父、伯母に関する記憶。そしてシーズンオフ直前の、わびた雰囲気の横浜ベイスターズ。
-----
十一月二十日(木)
「娘にツッコミをいれる母/ボージョレよりスコッチ」
八時起床。トリたちを寝かすために鳥籠にかぶせた布を取るためにリビングに行くと、シトシトと雨の音が窓越しにかすかに聞こえ、なんだ雨かと外に目をやると、ベランダにふっさりとした明るい茶色の毛に覆われた猫が一匹たたずんでいる。お隣のJさん宅のミーちゃんだ。どうやら脱走してきたらしく、わが家のベランダをてくてくと散歩したあとに、手すりの部分によじのぼって、そこから雨を眺めていたらしい。ぼくが声をかけるとミーはギロリとするどい視線を向け、シャーッと威嚇の声をあげた。花子の実の娘である。別にいたって構わないのだが、いかんせん外は雨である。風邪でもひかれちゃかなわない。自宅に帰ってもらおうとベランダに出て説得するが、人の話なんか聞いちゃくれない。近づけば、すぐにシャーッだ。困ったもんだ。カミサンがお隣に電話をかける。隣の奥さんにベランダに出てきてもらう。「ミィチャ〜ン」と声を掛けてもらったら、すぐにというわけにはいかなかったが、なんとか大人しく帰ってもらえた。
脱走した原因は、どうやら三歳になる娘のちーちゃんが窓を開けっぱなしにしてしまったかららしい。ちーちゃん「どうして出ちゃったのかな」と幼児独特のたどたどしい、文節が不明瞭で分断的な口調で口にすると、たちまち奥さんに「おまえがあけたんだろがっ」とつっこまれていた。
九時、事務所へ。午前中はE社POPのコピー、N不動産チラシなど。午後より八丁堀のJ社へ。ポータルサイトNの取材の件、打ちあわせ。
八丁堀から東京駅まで歩いてみることにした。日本の戦後復興とともに成長し成熟したビジネス街である。街並みは中途半端に古くてゴツゴツしたデザインのビルばかりでまったくおもしろみがない。緑が極端に少ないのも、高度成長期の日本を象徴しているように思えた。
帰社後もN不動産。十九時、帰宅。
今日はボージョレ・ヌーボーの解禁日である(「ボージョレ」と入力したら、「Beaujolais」と変換してくれたのでちょっと驚いた)。事務所の向かいにある洋食系の居酒屋は、「ボージョレ解禁」の張り紙をしている。百年に一度の出来という今年の新酒によくあう料理を用意しているのだろうか。西荻ですらこんな店があちこちにあるのだから、新宿や渋谷、六本木、銀座なんかにいったら、あちこちでボージョレだボジョレーだと盛り上がっているのだろう。その隣の、ぼくが贔屓にしている「欧風料理 華」は、そんな世間の騒動めいたお祭り騒ぎなど気にせず「木曜定休」の看板が出ていた。近所の酒屋で今日から飲めるボージョレを買って帰る。
イカ墨スパゲッティとボージョレ・ヌーボーで夕食。さっそく飲んでみたが、しょせん新酒である、さほどうまいとはおもえないのだが、それはぼくにワインのセンスがないということか。学生の頃はフレンチの料理人をしていた先輩にしこまれてかなりワインを飲み散らかしたが、最近ではまったくうまいとおもえなくなってしまった。食事とともにというのであれば、やはりビールのほうが料理をぐっと引き立ててくれる。食後に楽しみたいのなら、スコッチ・ウィスキーか焼酎のロックに限る。
漱石『猫』。蛇飯。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。さめてしまった野球の熱狂と、死ぬということ。
-----
十一月二十一日(金)
「目障りなんだ」
八時起床。小春日和というほどのどかな感じはせぬものの、暖かなのは確かなようで、空はまあ青といえば青いかなという程度の青さで、曖昧に広がり、ほんの少しだけ小さな白くて曖昧な形の雲を浮かべている。昨日、時雨のなかを歩いているときは「これでまたさらに冬めいてくるのかな」などと考えていたが、季節とは人間が考えるほどすんなりと変わっていくわけではないらしい。窓を通じてリビングに曖昧に射し込んでくる陽の光のもとで、猫たちはコロンコロンと寝転がっている。
九時、事務所へ。午前中は銀行回り。振込や支払を済ませてからは、N不動産チラシの原稿。昼食後、突然B社のTさんから電話。U社PR誌のプレゼン、代理店の移行で一見開き差し替えにすることになったという。大至急ヘッドラインだけコピーを書いてくれといわれ、とまどうがなんとか対応。夕方はE社の打ち合わせで大崎に行く予定だったのだがキャンセルという連絡がはいり、さらに予定が狂ってしまう。どうも調子が狂う一日。ここ数日の季節の移り変わりといっしょだなあ、などと呑気なことを考えながら、N社取材準備の下調べなどするが、十五時くらいからビルの改修工事がはじまり、うるさくて仕事どころではなくなってしまう。ヒステリー状態で終業。十九時すぎ。
夕食はカミサンと焼肉屋へ。タン塩、ハラミ、ホルモン、牛刺し、辛口キムチ、冷麺。
帰宅後は残っていたボージョレ・ヌーボーが目障りだったので一気に飲んでしまった。『タモリ倶楽部』を観る。三鷹に船舶の開発施設があるらしく、そこをテーマパークとして紹介していた。おもしろい。
今日はほとんど(趣味の)本を読まなかったなあ。漱石『猫』をほんのすこしだけ。
-----
十一月二十二日(土)
「頼むからもうワインは」
花子が遠くのほうで、おそらくはリビングあたりなのだろうが、そのあたりから、フニャンフニャンとわがままな主張ありげな鳴き声を響かせている。ハナコー、と呼ぶとすぐにやって来るが、来てくれたことのうれしさよりも、自分の声のしわがれっぷりに驚いてしまう。おそらく夕べのボージョレが原因だ。もうワインなぞ自分の金でボトルで買ったりなどするまい、と心に誓う。そもそもぼくはワインをうまいと思えないニンゲンなのだ。しかし、なぜかワインをいただくことが多いようだ。外見から、皆さんぼくがワイン好きだと判断されるようなのだが、残念ながらオレはそんなに高貴な酒飲みじゃねえ。下品なビール飲みの、意地きたねえ焼酎のみの、ヨレヨレのウィスキー飲みだ。頼むからもうワインは贈らないでくれ、といえるものならぜひいいたい。
十時起床。掃除、洗濯後、書斎で本を読んでいると、リビングからカミサンのあああという変な声が聞こえる。うるせえと思いながら様子を窺うと、どうも麦次郎をでっかいビニール袋に入れて遊んでやろうと思ったところ、麦め本気で怖がってビニールから飛びだし、そこで花子と鉢合わせ、目が合ったところでシャーと威嚇され、麦まで錯乱していたのか、シャーと応戦しかえしたという。また不仲状態にもどるのかと危惧したが、まあなんとかなっているようだ。猫の奥深い部分の精神状態なぞ、ニンゲンにわかるはずがない。わかっていると信じ込むことこそ、ニンゲンの一方的な押しつけがましい愛情であり、猫たちは必ずしもそれを望んでいないことを胆に命じなければならない。と頭ではわかっているが、ついつい愛情の押しつけをしてしまうのは、やはりニンゲンは本質的にワガママでバカだからだろう。とこんな持論を書き連ねるぼくもまた、麦や花子に愛情を押しつけ、拒否され、嫌われつづけているのである。
午後から事務所へ。伝票記帳などの事務処理。十八時、吉祥寺へ。「House Styling」で、ニンゲンのかたちをしたドアストッパーを購入。これでわが家のニンゲン用のトイレのドアを止め、猫がいつでも出入りできるようにする。つづいて「ユザワヤ」へ。鳥籠を載せる台を作るための材料を購入。まず木材。あらかじめパソコンで作っておいた図面を持参し、それ通りに切っていただく。ほか、木ねじ、蝶番、鍵など。十九時すぎ、帰宅。
不在中の猫の様子が心配だったが、なんということはない、花子も麦も威嚇しあったことなどすっかり忘れ、ベッドのうえで仲良く寝ていたようである。
夕食はニンニクの芽と牛肉の炒め、吉祥寺で買った鉄鍋餃子、ニラ饅頭。腹いっぱい。
テレビ『アド街ック天国』『エンタの神様』などをダラダラと観る。
漱石『猫』。ほんのすこしだけ。
保坂和志『カンバセイション・ピース』。人間の見るという行為と、神の見るという行為。うーん、このストーリー展開で本気で神に触れますか。超常現象的な話題、チャーちゃんの死、自分の記憶のなかにある「自分を見ている視点」などで、たしかに神、つまり不可視的な存在について語る下地をつくろうとしていたのはわかるけど、やっぱりこれは唐突だと思うぼくは、性格が悪いのだろうか。それとも読みが浅いのだろうか。
-----
十一月二十三日(日)
「動物奉仕の日」
勤労感謝の日である。非労働者から感謝されるべき日であるというのになぜかぼくはかならずこの日を働いて過ごすというおかしなジンクスのようなものが、断ちきることができない鎖のように何年もつづいていたのだが、今年はしっかり休むことができる。ひょっとすると、社会人になってはじめてのことかもしれない。いや大学生のときもこの日はアルバイトをしていたのだから、十数年ぶりの勤労感謝の日ということになるか。しかしぼくの勤労を祝ってくれる人など身のまわりにはまったくいないわけで、したがってこの日は自分の勤労を自分で褒めるという自画自賛的な迎え方になるわけだが、それも少々虚しくはないか、ということで、結局ぼくはこの日を自分のなかでは「動物奉仕の日」と決めた。今日は、鳥籠用の台を自作する。日曜大工、勤労感謝の動物奉仕大工だ。
今、わが家の鳥籠はふたつある。体調不良でつねに籠のなかを二十八度以上に保たなければいけないきゅーと、生後数ヶ月のぷちを同居させることができないからだ。きゅーの籠はアクリル板で三方を囲み、さらにそのうえからビニールのテーブルクロスをカットしたものをかぶせてある。なかには保温用のヒヨコ電球が二つ、取り付けてある。保温が不要だった夏は、鳥籠をワゴンのうえに載せていたのだが、さほど大きいものではないので鳥籠ふたつは載せられない。ここ数週間は段ボールを切って四方に高さ二十センチほどの壁をつくったものを床に直に置き、そこに鳥籠を並べて置いていたが、段ボールでは少々貧乏くさい。
十時に起床し、食事、掃除を済ませてから早速作業に取り掛かる。昨日ユザワヤで購入しておいた木材――ナラ合板とかいう、木くずを圧縮して作った木目のない合板――に鉛筆で木ねじの位置を書き込み、錐で穴を開けてからドライバーで止める。これだけの作業なのだが、一枚目は要領がわからず少々時間がかかってしまった。底板を囲うように、三つの側面の板を取り付ける。残すは前面だけなのだが、ここは鳥籠を置いたときに掃除しやすいように開閉式にしたかったので、蝶番をつけることにした。最後に底にキャスターを四つ付けて、完成。途中木ねじが足らなくなり西友まで調達に行くというアクシデントもあったが、無事完成した。最後に、先日購入したラグマットの段ボールについていた「Y's
for Living」のロゴを切り抜いて、蝶番で開閉できるようにした前面の蓋に貼り付けて作業終了。これで見栄えもよくなったし、鳥籠を移動しやすくなった。
疲れた。すぐに寝てしまう。本はほとんど読まなかった。
-----
十一月二十四日(月)
「二代目うりゃうりゃの実家、初代うりゃうりゃの墓」
九時起床。ちらかりっぱなしのリビングを片づける。窓のほうに目をやると、一面にびっしりと結露ができている。外はかなり冷え込んでいるらしい。先日のリフォームの効果で結露の量はかなり減ったが、それでもやはり気密性の高いわが家では、結露を防ぎきれない。まあ、うるおいのある家だということにしておこう。
午前中は読書。午後より散歩に出かける。マンションの裏を流れる善福寺川の遊歩道沿いに、阿佐谷方面、つまり川の流れとおなじ方向に向って歩いていく。灰色の雲が空一面にフラットに広がり、冬の寒い一日を思わせる。晩秋というより、初冬といったほうが適当かな、なんて思いながらジャンパーのファスナーを首のところまでグッと引き上げ、ちょっとだけ身を縮ませながら、のんびり歩く。
いつも川でくつろいだりご飯を食べたりしているカルガモたちに混じって、くちばしが濃く、しっぽがピンと立ったカモが混じっている。オナガガモだ。毎年木々の葉が赤や黄に身を染め、落葉するころになると、彼らはこの川にやってくる。よく見ると、マガモも混じっているようだ。鮮やかな緑色の体ですぐに判別できる。マガモがこの川に来るのは珍しいことで、ここにかれこれ八年近く住んでいるが、数度しか見たことがない。
オナガガモたち渡り鳥がやって来る時期は、柿の木が艶やかな橙色をした実をつけるころでもあるし、桜の木が赤くなった葉をパラパラと落とすころでもある。ヒヨドリたちの鳴き声がはげしくなる時期でもある。カミサンは、柿の実がなっているのがうれしくて大騒ぎしているのだといっているが、ぼくも同感だ。遊歩道の左右に生えるさまざまな種類の木――やはり桜が多い――から、ヒヨドリたちはスピードに乗ると羽根を畳んで、弾丸みたいに飛んでいく。ヒヨドリは羽ばたいて加速するときやかじ取りをするときは羽根を広げるが、まっすぐ進むときは羽根をたたむ習性がある。羽根の使い方は違うけれど、可変翼を備えたノースロプ・グラマンF-14Aトムキャットみたいだ、などとくだらないことを考えながら、どんどん進む。
川べりに居を構える一戸建ての庭先が、遊歩道から見えることがある。垣根越しにちらりと見える場合もあるし、丸見えの場合もある。どういうわけか、ヒメリンゴを植えている家がいくつも見られた。ちょうど今の時期に実を結ぶらしく、愛らしい赤い玉が、あちこちにぶら下がっている。ブドウの木を植えている家もあった。蔓のように伸びる習性があるのだろうか、ブドウの木は庭先から家の壁をつたってひょろひょろと伸び、二階の庇のところで実をつけていた。実には丁寧に白い袋がかぶせてある。どうやらここの家は、毎年このブドウを収穫し、その味を楽しんでいるようだ。
善福寺川公園についたところで、しばらく公園内を歩いてから阿佐ケ谷駅方面へ方向を変える。パールセンターをぷらぷらと歩くが、別に買い物をするわけでもなんでもない。できればどこかの喫茶店でお茶がしたかったのだが、ぼくもカミサンもドトールやスタバなどのナショナルチェーンの珈琲が嫌いだから、結局どこにも入らないことになる。パールセンターには、うりゃうりゃが売られていたペットショップがあるはずだと、その店を尋ねてみたのだが、今は百円ショップとディスカウントショップが合体したみたいな、おかしな店になっていた。うりゃが生きた痕跡がどんどん消えていくことが、ちょっと悲しくなってしまう。
独身時代、ぼくもカミサンも阿佐谷に住んでいた。ぼくが住んでいた北側へいってみることに。駅からアパートへ向う途中に、築二十五年くらいだろうか、古びた一戸建てがあって、そこで雑種犬が飼われていた。その子はまだ生後数ヶ月、どう見ても一年未満の若い犬だったのだが、顔の毛がテリアのようにボウボウで老人のように見えたので、ぼくらはその犬を「ジジオ」と勝手に命名していた。ジジオはどれくらい大きくなったか確認したかったが、残念ながらジジオがいた家を見つけることができなかった。このあたりじゃないか、という場所に、小奇麗なアパートが建っている。どうやらそういうことらしい。
ついでにぼくが住んでいたアパートにも行ってみる。ぼくは新築の状態で入居したのだが、すでに八年以上経過しているためか、アパートはかなり古びて汚れていた。壁にできた染みのようなものを見ながら、その後何人がここに住み、出ていったのかとチラリ考える。
アパートで確認したかったものがある。じつは、今年の三月に死んだうりゃうりゃの前に、もう一羽「うりゃうりゃ」と名付けたインコがいたのである。一人暮らしのときに、「おかえり」をいう相手がほしいという理由で買ったのだが、二週間くらいで死んでしまった。おそらく先天的になにか病気をもっていたようで、急にご飯を食べなくなったと思ったら、そのまますぐに初代うりゃうりゃは逝ってしまった。当時は動物の病気や治療法などについてもうとかったので、何も手をほどこすことができなかった。このアパートの入り口のところに咲いていた白粉花の根元に埋めたが、白粉花はなくなっていて、初代うりゃうりゃを埋めた場所は、工事か何かをしかけたらしく、無残に掘り起こされていた。
早稲田通りのほうまで歩き、バスに乗って荻窪まで移動。このとき、すでに十七時。
荻窪の「西友」で鶏肉、エビ、イカ、チンゲンサイなどを購入し、帰宅。十八時。鍋をつくって食べる。
夜、ひどい下痢に。原因不明。カミサン曰く「魚介類の鍋、体質に合わないんじゃ? まえにもこういうことあったよ」。そのとおりかもしれない。二時間近く猫といっしょになってホットカーペットのうえで横になったら恢復した。
保坂和志『カンバセイション・ピース』読了。一昨日の日記に書いた「神」のことも、結局はこの作品の一部分でしかない。だらだらと夏から秋にかけての古い一軒家の季節の移り変わりとそこに暮らす人々の日常だけをだらだらと書き連ねたこの作品で、作者がいちばんいいたかったのは、視点の多元性ということではないのだろうか。世界は変わりつづける。だがその変化をはっきりと認知することはむずかしい。世界は変わる。だが世界はなんら変わらないのだ。引用。
□ □ □
庭を見ると置くで白樫が大きな影になっていた。さっき想像したほどではないがだいぶ満月にちかい月が高く上がっていて、星は一つも見えなかった。月が出ていなかったとしてもまだ虫が鳴くような気候では大気中の水蒸気に妨げられて星はまばらにしか見えないだろう。
私(傍点)というのは暫定的に世界を切り取るフレームみたいなもので、だから見るだけでなく見られることも取り込むし、二人でいっしょに物や風景を見ればもう一人の視線も取り込む。言葉のやりとりでその視線を取り込むのではなく、視線を取り込むことが言葉の基盤となる。
白樫の葉が月明かりに小さな光を反射させているのは空からでなければ見ることができないけれど、そういう視線を私は持っていて、それも私がこの場所に固定されているのではなくて暫定的なフレームみたいなものだからだ。
色づきはじめた柿の実が重なる葉の間で月明かりに柔らかく光っている視界や、いま手前でゆっくり静かに揺れている棕櫚の南国の団扇のような葉が幹の頂点から放射状に広がりつつ何重にも重なりあって、硬く細い羽状葉が弱くツーッと光っている視界があるのも私(傍点)がフレームみたいなものだからで、その中で金木犀の香りが消えて柿が落葉してしばらく枝の先に濃く色づいた実だけが残り、落葉しない葉が冬の間にくすむのを知っているのも私(傍点)がフレームみたいなものだからで、私自身もまたそれらを橋渡しする媒体項になっていく。
いまを秋だと知る私は、金木犀が香り柿の実が色づきはじめたから秋だと知るのではなく、春先に沈丁花が香り、そのあとに、タンポポやニガナやスミレが咲いて、夏に木槿や夾竹桃が咲くから今が秋だと知るのかもしれない。
□ □ □
-----
十一月二十五日(火)
「用心しましょう」
八時起床。今日も雨だ。季節の変わり目には必ず雨が降るものだが、今日の雨はこの季節ならではの時雨というよりも、ただの冷たい晩秋の雨といったほうが正確か。窓の結露は相変わらずで、雨がガラスに染み込んで部屋の中まで入ってくるのではと勘ぐってしまう。
九時、病院へ。夕べの下痢が少々気になったため。朝は吐き気がした。医者の診断は、ひょっとしたら食あたりかというあいまいなもので、アンタはどうも胃腸が弱いようだから、普通の人が平気で食べれるものでも用心したほうがいいと忠告されてしまう。胃薬を処方してもらう。
九時三十分、事務所へ。外気がまったくわからない自宅とい違い、事務所は日当たりがさほどよくないせいか、寒い。外に出たほうが暖いと感じるときも多々ある。あわてて暖房を入れると、同時に電気ポットでお湯を沸かしていたせいか、ブレーカーが落ちてしまう。東京電力にアンペア数のアップを依頼する。
明日の取材準備、事務処理など。夕方、お中元の手配のために新宿の小田急へ。ついでにビックカメラに寄り、乾電池を購入。ICレコーダー用の単4型。
胃腸は薬が効いているせいか、かなり具合がよい。夜は思い切って普通の食事にする。餃子を大根おろしとポン酢であっさりと食べる。
漱石『猫』。名無し君の運動について。『猫』には人間世界への皮肉だけでなく、こうした猫本来の無邪気さを克明に――ただしおかしな視点からではあるが。名無し君は教養が高いゆえに視点がずいぶんずれているのだ――描写するという側面もあったのを忘れていた。この無邪気さがなかったら、『猫』は駄作になっていたかもしれない。
笙野頼子『パラダイス・フラッツ』を読みはじめる。『レストレス・ドリーム』である種の到達点に達した笙野の次作。
-----
十一月二十六日(水)
「みっちゃんのひみつ」
六時起床。広島出張である。懸念していた天気は曇りで、まあフライトにはまったく差し支えあるまい。日帰りの強行取材だから心して掛からねば、と気合いを入れて出発。
八時四十五分、羽田着。空港で榊原郁恵を見かける。フツーのちっちゃいオバチャンだった。
九時、J社のLさん、Nさんと待ちあわせ、出発。中央の列だったので窓が見えず、残念な思いをする。
十一時、広島市街へ。軽く昼食を採ってからN社のFさんと合流。タクシーで取材先のN自動車へ。
取材はおよそ二時間。充実したインタビューができたと思う。飛行機を待つ空き時間を利用して広島風お好み焼きなるものをLさん、Nさんとともに食べるが、あまり美味くない。名店だと聞いていた「みっちゃん」は、経営者の兄弟同士でおなじ屋号を名乗っているらしく、それゆえか、美味い「みっちゃん」と美味くない「みっちゃん」があるらしい。がっかり。
十九時過ぎの飛行機で東京へ戻る。
漱石『猫』。銭湯――漱石は「洗湯」と表記していた――を覗く名無し君。ひょっとすると、全編をつうじてもっとも描写が克明な部分かも。
-----
十一月二十七日(木)
「田舎の夜景」
目を閉じると浮かんでくるのは、飛行機の客席のなかではなくて広島駅から空港へ向うリムジンバスから見える田舎の夜景だった。蒲団のなかでウトウトとしはじめると、体がまえへまえへと滑ってゆくように感じられ、やがて何も見えていないはずの視界に、トンネルのなかを照らすオレンジ色の光の連なりや、暗闇のなかで時折見える信号機、路面にポツリポツリと現れる商店や家屋の明かりが浮かんでは、体の滑る速度にあわせて、まえからうしろへと流れ、消えていく。そこでハッと我に帰り、目を開ける。そんなことを数度くり返すうちに、眠りについた。夢を見た。夢は広島も飛行機もリムジンもまったく関係がなかった。
八時起床。疲れはあるようで、いつもより若干顔を洗ったり着替えたりするときの体の動きにキレがないように感じられたが、生活に差し支えるほどのものではない。いつものように仕度をし、いつものように事務所へ向う。
午前中は出張旅費の精算など。午後より外出。十二時、ゲートシティ大崎の「カフェ・ハイチ」で、サツマイモのポタージュとドライカレー、そしてハイチコーヒー。ここのハイチコーヒーはたいへん気に入っている。ほろ苦いしっかりした風味だが、軽やかで、濁った感じがしない。よけいな味の成分がしない、といったほうが正確か。
ゲートシティ内の書店にて、大江健三郎『二百年の子供』。大江氏が子供向けに読売新聞で連載していたファンタジー・ノベル。
十三時三十分、大崎のE社にてPOPのプレゼン。他社とは違った切り口が受けた。
帰社後は昨日の取材内容をまとめはじめる。原稿を書くにあたっての要素の洗い出しと、誌面構成の決定。インタビューのときに取ったメモだけでは執筆は不十分と判断したので、テープ起こしをすることに。
夕方、インターネットで注文しておいた本が届く。阿部和重『ニッポニアニッポン』『シンセミア』(上)(下)、真木準『一語一絵』。
十九時、インナーイヤー型のヘッドホンが耳にあたっていたくて作業ができなくなり、帰宅。明日は大きいヘッドホンを持参しよう。
漱石『猫』。学生にからかわれる苦沙弥先生。
笙野頼子『パラダイス・フラッツ』。胴体だけしかない幽霊(?)、妖怪のような管理人のおばちゃん。嫌悪の具現化、嫌悪の陰喩化というのは、笙野の十八番。
-----
十一月二十八日(金)
「倒錯的な美文」
八時起床。『ズームインスーパー』でペット産業の特集をやっている。話題の猫語翻訳機「ミャウリンガル」のデモをしていた。ヒット商品「バウリンガル」の猫版というわけだが、あくまでおもちゃと考えたほうがいいだろう。自分の買うペットの気持ちくらいわからんでどうする。という自分は、なにを隠そう猫の気持ちがよくわからずに、しつこく遊びすぎてすぐに嫌われる。
九時、事務所へ。午前中は銀行へ行き、支払などを済ませる。広島取材のテープ起こしをすこし。
十二時、カイロプラクティック。十三時、吉祥寺駅北口のソニー系電器店「VIC」の向かいにあるインド・ネパール料理店「ナマステカトマンズ」で昼食。野菜カレー、ナン、サラダ、タンドリーチキン、シシカバブ。辛くないがスパイシー。店の雰囲気も悪くない。食後にチャイが出たのはお茶好きとしてはうれしい限りだ。
帰社後もテープ起こしだ。自宅から持ってきた大型ヘッドホンは役立たずだ。ICレコーダーに接続すると、なぜか片チャンネルしか聞こえない。ソニーのMDプレイヤーのヘッドホンも、やはり片チャンネルだけ。どうやらICレコーダー付属のヘッドホンでないとまともに聞こえない仕様らしい。インナーイヤータイプ固有の耳の痛みと集中力の途切れに堪えながら作業する。音に集中しながらキーを叩くのは疲れる。
十八時、なんとかテープ起こし終了。事務処理などを済ませてから帰宅。十九時三十分。
夕食はお刺し身と豚汁。サーモンはあまりおいしくなかったので、花子様へ積極的に献上した。
笙野頼子『パラダイス・フラッツ』。外猫との関係、猫と自分の関係など。猫との接し方に、主人公の切なさが反映されるが、それが文体によってねじ曲げられ、独特な毒のある描写となる。醜悪というのではない。倒錯的な美があると思う。
漱石『猫』。近所の学生との「戦争」。
-----
十一月二十九日(土)
「飼い主をしつけ」
カミサンと弟が仲よく風呂に入っている夢を見て目が覚めたが、その夢の意味がよくわからず蒲団のなかで小一時間考えこむ。麦次郎はぼくの枕の横でぼくの頬にピタリと体をくっつけ、鍋にはいったエビのように丸まってじっと寝ている。花子は呼ぶとすぐにやって来て、胸のうえでぼくが起きるのを待つ。九時三十分、起床。
外は雨だ。目を凝らせば煙り具合で雨の強さがわかるだろうと窓を覗くが、あいにく結露のせいでなにもわからない。マンションは人間の五感を鈍らせる。窓を開けて確認してみようかとも思うが、リビングの窓は大きい。寒いのはイヤなので止めた。
午前中は読書。十四時ごろより外出。荻窪のアメックスの近所にある古書店にて、後藤秋生『挟み撃ち』、古井由吉『招魂としての表現』、柄谷行人『日本近代文学の起源』、大江健三郎『万延元年のフットボール』、蓮實重彦『小説から遠く離れて』、松谷みよ子『現代の民話』。松谷はカミサンの本。今日は評論が多いかな。大江の『万延元年』は、買い直し。文庫をもっていたが分解寸前で読みかえせないなのだ。
つづいて「カルディ コーヒーファーム」でクリームシチューのルーを購入。有機野菜を扱う八百屋「グルッペ」で、ニンジン、ブロッコリーの芽、卵、豆乳など。
仲通りにある日本茶喫茶「茶のイ」で休憩。ぼくは深入り煎茶とじょうよまんじゅう。カミサンは新茶煎茶となんか小豆でできたまるっこいヤツ。名前忘れた。煎茶は旨味が強い。
今は義父のいる岡山に桃子と泊まりに行っている義母の自宅へ行き、郵便物の整理などして帰宅。帰りに善福寺川沿いの遊歩道で犬のウンコを踏んづけてしまった。犬よ、飼い主をちゃんとしつけておけとぼくはいいたい。
夕食はシチュー。ニンジンはすばらしく味が濃く、かついやな風味がない。完璧。
笙野頼子『パラダイス・フラッツ』。生活のなかにある、ごくごく小さな悪。そこから広がる狂気。狂気に翻弄される主人公もまた、狂気そのものなのではないか。現実と虚構の境界線は、狂気によってたちまち曖昧になる。
漱石『猫』。苦沙弥先生と学生たちの大戦争。
-----
十一月三十日(日)
「古書を漁る」
全身がドロドロとした感覚のなかで瞼にほんのわずかな光を感じて目を覚ます。寝室のカーテンの向こう側が気になったが、陽の光など感じない。夜が朝に変わったというだけだ。晴れてはいない。だが昨日からの雨はやんでいる。時計に目をやる。十時。寝すぎたと思う。起きあがろうとすると、ほんのすこし喉が痛む。原因が思い当たらない。花子を呼ぶ。なぜだか今日はすぐに寝室へやって来ない。
午後より散歩へ。西荻に向って、南側の住宅街をカミサンとプラプラ歩く。夕べの雨で落葉樹はかなりの量の葉を落としたか。道の両側に、濡れた黄褐色の葉が乱雑に重なりあっている。塀越しにアタマをのぞかせるように、サザンカの桃色の花が咲いている。一戸建ての家にはサザンカを植えているところが多い。常緑樹は木が裸になることで家がまるみえになることがないからだろうか。多くの日本人に愛される桜の木は、申し訳程度にオレンジ色に染まった葉を、ぷらりぷらりとぶら下げている。あれがすっかり落ちたころは、呑気に散歩するのが少々きびしくなるのだろう。
古書店「スコブル社」へ。ここはあまりに本が多すぎてかつ本棚と本棚のあいだがせまくいため、顔と本の背表紙との間隔が近すぎて、目を凝らして本を探すとだんだん目が回ってアタマがクラクラしてきてしまうのが難点なのだが、置いてある本のバリエーション、方向性がぼくのツボにはまりやすくて、よく利用している。笙野頼子のハードカバーはここでかなり買いそろえた。今日は奥泉光『鳥類学者のファンタジア』購入。
事務所に寄り、カミサンの仕事の道具を引き上げてから、駅前の喫茶店「カフェロッジ ダンテ」へ。「ダンテ」とは『神曲』のダンテのことだろうか。古びたダークオークのインテリアとアンバーのシェードの照明でほのかに照らされた店内はあまり『神曲』という感じはしない。店内にはクラシックが流れている。これが神の曲というわけだろうか。「カフェロッジ」と枕詞がつくだけあって、たしかにどことなく山小屋風な感じもある。奥には装飾品であろうが、暖炉が据え付けられている。ぼくはオリジナルブレンドとチョコムースコーヒーを、カミサンはおなじくブレンドとレアチーズケーキを注文。珈琲はほろ苦く深い味わいだが、いやな渋味は感じない。「どんぐり舎」にちょっと似ているかもしれない。
北側を通って家に戻る。古書店「比良木屋」でまた引っかかってしまう。カミサンは猫作家の作品集のような本を購入。ぼくは、村上龍『限りなく透明に近いブルー』(今さらって感じだが…)、多和田葉子『三人関係』『犬婿入り』を購入。スーパーに寄ってから帰宅する。十七時。
夕方、喉の痛みがひどくなったような気がするので、すこしだけ休む。
夕食はキムチ鍋。
笙野頼子『パラダイス・フラッツ』。小さな狂気と小さな嫌悪の積み重なり。最後にどんなかたちとなるのだろうか。ストーカーということばが定着するまえに、ストーカーをテーマにしたという点はどうでもいいのだが、結末は気になる。
|