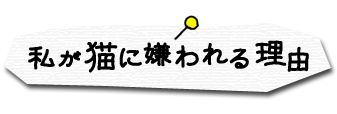|
二〇〇三年七月
-----
七月一日(火)
「梅雨の空、下痢の腹」
八時起床。下痢がまだ治らない。水のような便が出るという感じではない。ウンコたちがぼくの躯から出たくて出たくてたまらなくなり、駄々をこねた結果、ちょっと水分と空気が多くなり、それが短い間隔でスポン、スポンと肛門から逃げ出していく。そんなふうに感じられるのだ。ひどい下痢に特有な腹部の激痛というものはない。あるのはウンコの陣痛ともいうべき、「あ、腹痛いかも。出るかな出るかな」という感覚だけである。「出るかな」感覚は、今日の空模様みたいに気まぐれだ。降りだしたかなと思うと弱まり、いつのまにか止んでいる。油断していると、また降りはじめる。梅雨の空は下痢の腹とよく似ている、ということか。
九時、事務所に行くまえに病院へ。医師に症状を話すと「食あたりかな」とボソリといわれたのだが、さっぱり心当たりがない。昨日も一昨日も生ものはいっさい口にしていないのだ。胃薬と整腸剤の服用を指示された。
出社後はE社セールスシート、事務処理など。社会保険事務所への賞与支払届や給与算定基礎届などを用意する。二十二時、帰宅。
保坂和志『季節の記憶』を読みはじめる。肩の力の抜けた文体は好感が持てる。
-----
七月二日(水)
「申し訳ない」
花子が妙にプリプリと怒ったような鳴き声で騒ぎ、ベッドの下や横をうろついている。ご飯をあげなきゃ、と思い躯を起こし目覚まし時計を見ると、もう八時に近い時間である。ふだんご飯を食べるのが五時くらいなのだから、花子は三時間も空腹を我慢していたことになる。申し訳ない気分になった。
目が覚めなかったのは、自分が思っている以上に体力の消耗が激しかったからか。原因は昨日の胃腸不良であろう。下痢は激しく体力を奪い、胃痛は激しく気力を奪う。
九時、事務所へ。日中、時間が空いたので髪を切りに行く。夕方、半蔵門にあるJ社のUさんに会いに行く。あるケータイコンテンツのライティングの引合い。Uさんと会うのは二年ぶりくらいだろうか。この二年間に、おたがい色々ありすぎて、話したいことがたくさんある。ほんとうは食事でもしながら激動の二年をおたがいに報告しあいたかったのだが、残念ながらぼくはこのあとE社の仕事をしなければいけなかったので、丁重にお断りした。まあ、機会は何度だってあるだろう。今日でなくてもいい。
十九時、広尾のO社へ。E社セールスシートの打ちあわせ。帰社後、赤字の対応をする。二十三時三十分、帰宅。
保坂和志『季節の記憶』。主人公の息子、隣の年の離れた兄妹、その妹の旧友(バツイチになって出戻ってきた)、宗教を起こしたがっている友人、主人公の元同僚の同性愛者……。この作品は、さまざまな愛のかたちを綴ろうとしているのだろうか。
-----
七月三日(木)
「おなじ過ちは二度と繰り返すまい」
おなじ過ちは二度と繰り返すまい、などと書きだすとなにやらベタベタした人生訓とかいう代物を押しつけるような内容がダラダラと書かれたことばと思想の押し売りとでもいうべき内容の、どこぞのカリスマ経営者とか呼ばれて喜んでいるタイプの人間が書いたなんちゃってビジネス書みたいでイヤなのだが、そんな私情はさておき、わが愛猫のためにぼくは「おなじ過ちは二度と繰り返すまい」という誓いを立てから、夕べは寝た。過ちとは、猫の朝食を与えるのを忘れて眠りこけることである。もちろん、今朝は誰に起こされるともなく自然と日の出前に目が覚めた。だが頭がイヤに朦朧としている。足元を軸に、躯が時計回りだか反時計回りだかはわからんがグルグルと回っている。ぼくは回りながら缶詰めを開け、猫用の皿を洗い、ご飯を盛りつけた。そのあと便所にも行ったが、ひょっとすると小便も時計回りだか反時計回りだかにくるくると、スパイラル状に放射されていたかもしれぬ。だが、便器を汚すほどではなかった。パジャマのズボンも、濡れていない。
八時起床。躯がヘドロになったような気分。いや、長雨にさらされてぬかるんだ畑の土といったほうが正確か。自分は雨に打たれ続けてやわになった畑のようだと考え出すと、作物を育てるという使命を果たすことができない、ただの地面に成り下がったような気がしてくる。卑屈になっていてもしかたないので、ニンゲンとして起床し、軽く躯を動かしてみる。ひどく喉が痛むのは、夕べ窓を開け放して寝たからか。鼻汁がすぐに溜まる。
九時、事務所へ。雨は降っていない。うっすらとした雲が陽の光を拡散してくれるおかげで、暑さはほとんど感じない。五月のはじめごろに、今日あたりから半袖を着てもいいのではないか、などとすこしだけ悩んで、外気の気持ち良さに打ちのめされ、その年はじめてTシャツとジーンズだけでうろついてみた――そんな日のことを思い出す。服とは季節を映す鏡である。だが、季節のほうは、あまり服とは仲良くしたくないらしい。今日はカットソーの上にジャケットを羽織ったが、気まぐれな季節のご機嫌次第で、明日はジャケットを脱ぎ捨てなければならなくなるかもしれない。しかし、その気まぐれに振り回されながら毎日服を選ぶのも一興。こういうのを文化的な生活と呼ぶのかもしれない。
E社セールスシート。日中は時間が空いたので、読書などして過ごす。鈴木康之『新・名作コピー読本』。パラパラとは読んでいたが、通読しようと思い立ったのははじめてである。ほか、『日経ビジネス』『宣伝会議』『販促会議』『ブレーン』といった雑誌も読む。夜、E社セールスシートのデザインチェック。二十二時、終了。
夕食はワイズカフェにて。ぼくはドラゴンカレーと名付けられた激辛ドライカレー。とにかく辛い。しかし、口の中にはうま味がしっかりと感じられる。これが辛味の魔術なのだ。辛さに隠れたうま味に魅かれて、人(の一部)は激辛カレーを愛しつづける。カミサンは、ここのマスターが沖縄のナントカ島のおじいちゃんから教わったというソーミンチャンプルー――メニューには「ソーメンチャンプルー」とあった――を注文する。ふつうのソーミンチャンプルーはもやしとニラ、そして豚肉を使うと思うが、ここの場合はゴーヤを使う。美味。
帰宅後、プラムを食べる。今年ははじめて。ぼくはこの果物が大好きである。これを食べなければ、夏を迎えることができない。梅雨時のプラムは、盛夏をまえに新調した半袖のシャツとおなじくらい大切な存在なのだ。
保坂和志『季節の記憶』。失恋した三十代のゲイの友人との、真夜中の恋愛談義。人間の存在と愛情について。ちょっとおもしろい記述があったので引用。
□ □ □
それにしても一言で「大きな」ということばで片づけては申し訳ないくらいの大きなエネルギーによって生まれた宇宙の中で、恋愛したり失恋したりそうでなくても広く愛に取り憑かれて、そのことで身も心も大きな時間とエネルギーを使ってそれで死んでいくという人間がいて、砂漠には一日中費やしてわずか一日分の水滴を背中に溜めるという、ほとんどそれだけを毎日毎日繰り返して一生が終わっていく虫がいて、愛に取り憑かれた人間と水に取り憑かれた虫とたいして変らないようにも思えるのだが、すべて生き物がそういうことばっかりして生きている宇宙というところはとてもおかしなところだという気持ちがぼくにはますます強くなっている。
□ □ □
そして主人公たちの関心は「時間」へと移っていく。タイトルの『季節』とは、時間を意味しているのかもしれない。
-----
七月四日(金)
「社会保険の地獄道」
八時起床。雨は降っていない。
午前中はカイロプラクティックへ。ここ数日右側の尻の筋肉に痛みを感じつづけているのだが、朝だけ痛むのはどういうわけか。長時間歩くと左足がしびれてくるのは相変わらずで、やはり骨盤がずれてしまっているのだろうと素人なりに判断し、カイロプラクティックの先生に症状を話す。約一時間の施術でかなり快方に向かったような気がする。会計の際、先生は「イソハタさんは机に座るとき、こうやってませんか」と、椅子のうえで足を組んで片方のひじ掛けだけにもたれて偉そうにふんぞりかえってみせるのだが、そんなポーズをとった覚えなどまるでない。しかしよく考えてみると、職場の机はL字型になっていて、正面のMacと右側のWindowsを同時に使うことが多いため、偉そうにふんぞりかえっているわけでなくとも、結果的には先生がやってみせたポーズを一日に何度も何度もとりつづけているということになる。先生は「まさに、それが原因」といっていた。さて、この腰痛、下半身の不調を治すためには、職場環境の改善から取りかからねばならない。さて、どうするか。
吉祥寺の「まめ蔵」で昼食。またカレーを食べてしまう。どうして何度も何度もカレーを食べてしまうのだろうか。どうして何度も何度もカレーを食べつづけても飽きないのだろうか。
午後、事務所へ。源泉税の納付、算定基礎届の記入と資料の取りまとめなど、事務処理をいくつか。十四時過ぎ、外出。まず高円寺の社会保険事務所へ行き、算定基礎届を提出する。給与をいくら払っているかをまとめた書類を出し、控えにハンコを押してもらう、ただそれだけのことなのだが、ぼくはこの届け出がイヤでイヤでたまらない。その理由は、事務所の場所にある。環七沿いに建てられているのだが、最寄りの高円寺駅から歩いて十二、三分はかかる。それだけならまだいい。バスなどは一切通っていない。それも割りきれば許せる。いちばん許せないのは、環七に出てから社会保険事務所に辿り着くまでの、およそ五、六分は歩かねばならない歩道に、日陰というものがまったくないという点だ。高円寺駅を出てからは、しばらく中央線の高架線に沿って環七のほうへと歩いていくことになる。高架線のしたは店舗が並んでいる。高円寺らしいエスニック料理店や小奇麗なカフェ、ビリヤード道具の専門店、貸し倉庫、鮨屋、焼肉屋、阪神タイガースファンが集まる飲み屋などが軒を連ねる。直射日光を避けたかったら高架線の北側を、これらのお店を眺めながら歩けばいい。西荻窪とはちょっと違った街並みや街ゆく人々が――とくにファッション――新鮮で気晴らしにもなる。問題は環七にぶつかってからだ。ここを右に折れると、店舗などほとんどなくなり、通行人もまばらになる。歩いても歩いても、いかにも幹線道路でございといった風情の粗雑な感の否めない街並みとそれを途切れ途切れに遮っていく自動車の列ばかりが目に飛びこむが、代わり映えがないので飽きてくる。おもしろくもなんともない道を歩きつづけるだけでも苦痛だというのに、ここの歩道にはまったく日陰がないものだから、夏場は地獄道を歩いているような気分になってしまう。書類を出すだけのために、つまらない風景とやかましいエンジンの音ばかりがつづくなか、絶え間なく吐きだされる排気ガスを吸いこみながら、不快に流れつづける汗をぬぐいつつ、この道を延々と歩きつづけなければならない。時間にすれば十分もかからないのだが、さまざまな苦痛がこの道に凝縮されたように感じるせいか、十分は十五分となり、二十分となり、一時間となり、永遠のようにすら感じられる。三年ほどまえ、右足首に骨腫瘍ができて歩行が困難になり、二週間後(だったかな?)に手術することが決まっていたときも、事業主としてはどうしてもこの書類を提出せねばならぬため――社会保険制度についての基礎知識がないカミサンにはまかせられない――、杖をつきつつここに向かったことがある。往路はタクシーを使ったが、帰りはタクシーなどまったく通りかからない。鞄を肩から掛け、杖をつき、あいたほうの手でハンカチを握り、びっこを引く珍妙なリズムの足取りで、ぼくは三十分かかって駅まで辿り着いた。倒れるかと思ったが、倒れなかった。足のほうはかなり悪化していた。
つづいて広尾のO社へ。新規物件の打ちあわせを済ませてから、原宿のビルケンシュトックに行き、靴を一足新調する。十九時、帰社。雑務などを済ませ、二十時、帰宅。
夜、コミコから電話あり。画廊に転職したらしい。
保坂和志『季節の記憶』。季節ごとに色を変える木々。鎌倉の自然を眺めながらの、主人公のモノローグがとても共感できたので引用。
□ □ □
僕は前に人間なんかに見られなくても山は山で自足しているし海は海で自足しているといったが、それは孤立していたり他と無縁であったりということでもなくて、木の実がきれいなのには意味がある。「きれい」とは鮮やかで目を引くという意味だが、木の実は鮮やかな色をつけて目立って、そうして鳥たちに食べられていま生えているところと別の場所に糞と一緒に落とされる必要がある。そういう風に鳥の目を引くための色がやっぱり人間にもきれいと感じられるのは、人間の感受性が木の実を食べる動物たちと完全に断絶しているわけではないことを示しているのかもしれないが、他の生き物だったら種全体が同じ色や形を好んだり警戒したりするのと違って、人間の場合には種としての全員が木の実や秋の紅葉の山をきれいと感じるわけではない。だから「きれい」と「鮮やか」では意味というか機能が違っているし、僕自身としても「きれい」ではなくて「鮮やか」と感じているのかもしれないが、とにかくそうして僕と息子と美紗ちゃんはあれからもずっと午前中は稲村のまわりの海岸や山を歩きつづけていて、そうしているあいだに僕の家にも松井さんの家にも炬燵がたった。
□ □ □
-----
七月五日(土)
「」
目が覚めるまで寝る、というのがウチのカミサンの休日の過ごしかたの基本である。ぼくは無駄に寝すぎるとその日一日にできることが減ってしまうのであまり好きではないのだが、それでもひどく疲れているときや体調があまりよくないときは、目覚ましをセットしないで寝ることがある。昨夜がそうだった。案の定、目が覚めたのは十時三十分ごろ。暑いので開け放っておいた窓から聞こえる、外出のための仕度をしている隣のJさん一家の話し声で目が覚めた。小便を済ませてから鳥籠にかぶせた風呂敷をとってあげたが、しばらくは頭も躯もぼーっとしたままで、ちょこちょこと動きながら機嫌よく鳴きつづけるインコたちのまえから移動することができない。
午後より外出。『ソラリス』を見に行く。原作はポーランドのSF作家スタニスワフ・レムの『ソラリスの陽のもとに』。七二年にアンドレイ・タルコフスキーも映画化している。レムは大学時代に愛読した作家のひとりだ。最近でこそSFはまるで読まないが、昔は三度の飯とおなじくらい――「三度の飯より」といえないところがツライのだが――好きで、とくにレムとフィリップ・K・ディックは好んで読んだ。
『ソラリス』。基本的なストーリーは原作とおなじなのだが、ラストシーンとコンセプト、テーマとなる部分は原作とは大きく異なっている。科学至上主義に警鐘を鳴らしながら、人間の内面を大切にしようとした原作のコンセプトのなかから、科学至上主義批判の面が大きく切り離され、人間の内面、というよりも、愛のありかたにスポットをあてた内容になっていた。タルコフスキー版よりかなり明快である。
夕食は『めちゃめちゃイケてる!』を観ながらスパゲティ。「スモウライダー」のコーナーを観て、おもしろいが批判も多そうだなあなどと、余計なことを考えながら大笑いした。
食後は宮藤官九郎脚本の『ぼくの魔法使い』の最終回を観る。エンターテイメントとして、隙がないと思った。
保坂和志『季節の記憶』。ことばと抽象、ことばと人間、ことばと自然、自然と人間、そういった二律背反的なものを掘り下げようとするのが本作のテーマなのだろうか。かなり重たいテーマを、肩の力の抜けた軽い文体で綴っている。スゴイと思う。不自然さがない。
-----
七月六日(日)
「四季とは違う/チケットゆずってください/ギャルソンの犬」
九時起床。かけっぱなしにしていた鳥たちの籠の風呂敷を取りにリビングへ行くと、ひんやりとした空気が部屋を静かに満たしている。空は形も濃淡もわからないほど均一に広がっている灰色の雲が延々とつづいているのが向かいのマンションの屋根越しにわかる。こうなると、たちまち体内カレンダーは異常を来たし、はて今は何月だったろうと自問してみることになる。梅雨とはとらえにくい季節だとつくづく思う。上着を羽織らないと震えるほどに冷たい雨が降りつづけると思えば、むしむしした霧雨が一日中街を濡らすこともある。春夏秋冬の四種で季節をわけるとすれば、梅雨はやはり夏に属することになるのだろうか。晩春だとか初冬だとかいった微妙な季節を言い表すことばはたくさんあるが、初夏と梅雨がイコールで結ばれるとはちょっと考えにくくい。だからといってニアリーイコールというのも変だ。梅雨とは、四季とはちょっと違った感覚で季節を捉えるためのことばなのかもしれない。
十時、事務所へ。休日出勤である。O社ダイレクトメールのリーフレットの構成を考える。金曜の夜にやってもよかったのだが、あの日は高円寺の社会保険事務所に行ったため歩きすぎで気力も体力も残っていなかったので断念したのだ。企画の作業自体は二時間くらいで終了。つづいて、先日カイロプラクティックの先生に指導されたとおり、机の、というよりはパソコンの配置を変更する。L字型に並べた机はそのままだが、正面にMac、右側にWindowsという並べかたから、正面は何もナシにして右側の机にMacとWindowsの両方を並べて置くことにした。手書きで作業をするときは正面で、パソコンを使うときは右を向いて、ということになる。もっとも、Macは液晶モニターを使っているから机のうえはまだ比較的余裕があるため、右を向いて手書きの作業をすることも可能だ。これを上手に使って、仕事中に躯をひねるようなことがないようにしたいと思う。
それいゆで昼食後、原宿へ。ラルクアンシエルが代々木体育館でコンサートをやるらしく、「チケットゆずってください」と書いたボードを頭のうえに掲げた若いおねーちゃんたちがあちこちに立っている。みんな、大好きなアーティストの音楽を生で愉しみたいのだから必死だ。もしも会場にはいれなかったらどうしようという不安のせいだろうか、彼女たちの顔色はかなりどんよりとしている。あのなかに、ひとつくらい「マンション建設反対」とか「ただ今の記録 68m50」とか、全然違うことが書かれたボードがあったらおもしろいだろうに、などとふざけたことを考えながら通りすぎる。カミサンは、ひどい人ごみに早くも気圧されつつある。
ラフォーレ原宿に入り便所にだけ立ち寄ってから、ビルケンシュトック原宿店へ。おととい買った靴がちょっと小さいような気がするので、取り替えてもらう。カミサン、すこし恢復する。
つづいて、革新的な店舗建築として話題になっているプラダの青山店へ。大きな大きなひし形のガラスで囲まれたビル。あれはガラスタイルみたいなものなのだろうか。店内からは、青山の街がチラリと見えた。建物自体がブランドイメージの向上だけを狙ったものなのだろうなあ、などと考えながら、あまり興味のない商品の陳列をざざっと見てみた。値札は見なかった。見る必要もなかったから、それでいいんだと思う。
コム・デ・ギャルソンへ。どうしてギャルソンの服はこんな方向に行ってしまったのだろうかと、ここに来るたびに不思議に思う。笑い声にたとえると、十年くらいまえまでのギャルソンは「うふふ」とか「クスクス」が似合っていたが、今のギャルソンは「ヘヘヘ」とか「クックック」のほうがよく似合う。昔のギャルソンは全身ギャルソンで固めないとちぐはぐな感じがしたが、今のギャルソンはほかのブランドと組み合わせて着てもあまりおかしくないような気がする。メンズに限っていえば、ストリートブランドや老舗メーカーのジーンズとの相性もいいような気がする。ジュンヤワタナベなんかは単一でないとダメだろうが。
ヨウジヤマモトにも行ってみる。ギャルソンを見てからヨウジの服を見ると、さっきの笑い声のたとえが妙に説得力があるような気がしてくる。スタティックな雰囲気が漂うヨウジには勢いのようなものはあまり感じられないのだが、ひとつの方向に鋭く向かっていく「服の力」が強く感じられる。ギャルソンの「服の力」は、どちらかというと拡散する光のようなイメージだ。
スパイラルへ。雑貨をすこし覗いてから帰る。
夕食はまた餃子鍋。週末の定番となりつつある。
保坂和志『季節の記憶』。今日はあまり読んでいない。
-----
七月七日(月)
「紫陽花の終わり、季節の終わり」
八時起床。今朝も肌寒いのはなぜだろうか。夏の気配はすっかりなりをひそめている。この空気の冷たさは季節に分類するのは少々難しそうだが、気温の乱高下があるのも梅雨時の特徴ということなのだろうか。気象学には詳しくないのでよくわからない。暇があれば調べてみたいが、きっと明日にはわすれているだろう。
ちょっと寒いせいか、きゅーはあまり元気がない。
九時、事務所へ。道すがら、あちこちで紫陽花の花が目につくのだが、鮮やかさを保ちつづけているものはほとんど見られなくなってしまった。花びらが茶色くくすみ、皴より、うなだれている。すでに花びらが落ち、萼の部分だけが点々としているものもある。梅雨時の花といえば紫陽花だが、この花は梅雨の訪れとともに咲きはじめ、梅雨の終わりとともに朽ちるのだろうか。だとすれば、湿った季節の終焉は間近だ。次に咲く花は何だったろうか。
O社ジョイントキャンペーンDMのリーフレット構成、コピー、企画書など。おなじことばかりしているので、すぐに飽きる。そのたびにベランダに出て空を眺めてみるのだが、一日中降ったり止んだりが繰りかえされていたようだ。階下に目をやると、開いた傘の数が増えたり減ったりしているのがちょっとおもしろい。ほんのわずかな、霧吹きで軽く吹いた程度の雨のときはなかなかの見物だ。女性は差す率が高いが、若い男はほとんどが傘を差さない。小学生も差さない。傘を差さない人のなかにはフリーターっぽいファッションをした若い女性も多い。ヒップハングパンツに着丈の短いカットソーといういでたちでは、おヘソが湿って冷えてしまうのではないかと心配にならなくもないが、まあ他人のことなのでどうでもいい。
二十三時三十分、帰宅。雨は止んでいたが、またいつ降りだすかわからない。空気は冷たく湿っている。
帰宅後、風呂に入ろうとすると麦次郎が風呂蓋のうえで湯が風呂釜に溜まるのをじっと見つづけている。ぼくがシャワーを使いはじめると慌てて風呂場から出ていき、シャワーのしぶきで躯が濡れてしまった、ユウさんに濡らされた! と、カミサンにニャーニャーと鳴き叫びながらそれを訴える。週に一、二度はこんなことがある。ぼくはいじわるな気持ちになってわざとびしゃびしゃと湯をかけてみたり、湯がかからないようにシャワーを浴びながら麦次郎が自分の力で風呂場のドアを開けて出ていくのを待ってみたりする。いずれにしても、麦はかならずカミサンのところに行って、濡らされたことを報告するのが常だ。イヤなら入らなければいいのにと思うのだが、それでも風呂に来てしまうのは、学習能力がないからか。それとも濡らされるのが楽しいからか。ぼくは後者だろうなと思っているが、ほんとうのところはどうなのだろうか。
保坂和志『季節の記憶』。あと四十ページくらいかな。
-----
七月八日(火)
「頭脳明晰? いや、明晰なのはコンディションだけ」
七時、不自然なくらいに頭のなかが明瞭になるような感覚とともに目が覚める。そういった内容の夢を見ていたのか、それとも体調がいい証拠なのか。なにはともあれ、猫にご飯を与えなければならない。いつもなら暗い雲のなかを手探りで歩くような気持ちでキッチンへ向かうのだが、今朝はすでに明るくなっている時間だったことと頭が冴えていたことが重なってか、一歩一歩がおかしなくらい着実な感じがする。缶詰めを開けたあとでもう一度蒲団に入ったが、頭がはっきりしすぎていて二度根ができず。ちょっと残念な気分がしなくもない。
九時、事務所へ。今日も涼しい。天気予報では日中から晴れ間が射すようだったが、あいにく一日中霧雨がつづく。わずかに流れる風に冷やされた霧のように細かな雨の粒が、ゆっくりと街のなかを流れていくのが肌でわかる。
E社セールスシートなど。日中は時間が空いたので読書して過ごす。夕方からまたすこしバタバタしはじめる。二十時、業務終了。
カミサンとぼん・しいくで夕食。チキンのマサラ焼き定食。今日は小鉢がユニークだった。小鉢は一人にふたつついてくる。お店の人が気をきかせて別々のものにしてくれたから、夫婦ふたりで四つの味が愉しめる。おから、煮物はスタンダードだが味がしっかりしていて乙な感じだ。ツルムラサキとエリンギの和え物は、癖のあるもの同士を組み合わせるという発想に脱帽。ニンジンとパイナップルの酢の物は、ちょっと病みつきになりそうな味だ。
帰宅後、教育テレビでシニア向けのパソコン講座の番組を見る。義母はこれを見てスキルアップに励んでいるらしい。
保坂和志『季節の記憶』読了。鎌倉に住むちょっと理屈っぽい男と五歳の息子の日常。物語はない。なのに、登場人物たちの動向や科白から目が離せなくなるのはなぜだろう。感動は物語のなかだけに隠れているわけではない。おなじことを繰りかえすだけの毎日の生活のなかにも、そうだ、たとえば移りゆく季節のなかにも、近所の人とのなにげない会話にも、友人から送られてきたプライベートビデオのなかにも、息子と友だちのままごとのなかにだって、感動――ここでいう「感動」とは、テレビドラマやハリウッド映画を観て感じる感動とはまったく違う次元のものだ――はある。しかし、だからといってその感動を大袈裟に表現する必要もない。感動は行間から自然とにじみ出る。その出汁のようなものを読者が感じとれば、それでいい。そんな小説だと思った。保坂氏のほかの作品も積極的に読んでみたいと強く思う。
阿部和重『インディヴィジュアル・プロジェクション』を読みはじめる。チーマーが荒れ狂っていたころの渋谷が舞台の小説。『季節の記憶』の対極にあるといってもいいかな。
-----
七月九日(水)
「実はまだ眠い/ペアルック、あるいはアメリカ的なるもの/くだらなくておもしろい」
ここ数日つづく朝の涼しさにいちばん早く慣れたのは、どうやら二羽のインコのようである。目を覚ました七時三十分に鳥籠にかけた風呂敷をはずすと、いつもなら、起床後三十分はぼーっとしたまま、じっとして動かないはずのきゅーが、今朝は風呂敷をはずすと同時に、籠のなかなど狭すぎるといわんばかりの活発さで、ぴょんぴょんと跳びはね回っている。ぷちぷちも同様で、きゅーの元気さを応援しているかのように、ゲーゲーとかギョギョギョとかいったひどい声で鳴き叫びつづけている。それを見ているぼくはどうかというと、実はまだ眠い。
八時三十分、事務所へ。E社セールスシートの入稿準備を進める。準備万端にしたところで、十時に外出。銀座にあるT社へ。新規案件の打ちあわせ。O社のモバイルキャンペーンだ。
打ちあわせ後、伊東屋へ。欲しいわけではないのだが、万年筆売り場を覗いてみる。長居すると物欲が比例して高まってくるので、五分で店を出る。店のまえで、外人が松屋のほうに向かって歩いて行くのを見かける。四十代くらいの、着ているものから察するにおそらくはアメリカ人のその男は、なぜか左手にリアルに作られた本物そっくりの赤ん坊の人形を抱えていた。それだけなら、まあなにかの事情でむき出しにした人形を運んでいる最中なのだろうとかなんとか想像して納得することもできるのだが、人形をよく見てみると、彼がなんの目的でそれを抱えているのかがさっぱりわからなくなる。その赤ん坊の人形は、黒いポロシャツと赤っぽいチェックのズボンをはいていた。そしてアメリカ人も、黒いポロシャツと赤っぽいチェックのズボンをはいていたのだ。パンツの柄は、ほとんど同一である。ペアルックだ。こういうのもアメリカ的なるものの一種なのだろうか。わからん。
旭屋書店へ。仕事の資料を二冊、小説を二冊。保坂和志『猫に時間の流れる』『残響』。
帰社後はO社モバイルキャンペーンに終始。情報整理、資料の読み込み、そしてキャンペーンタイトルのコンセプト出し。二十時帰宅。
くだらなくておもしろいと話題のバラエティ番組『トリビアの泉』を観る。荒俣宏が出ていた。ほんとうにくだらなくておもしろい。入浴後、『ココリコミラクルタイプ』を観る。くだらなくておもしろい。『マシューズベストヒットTV』を観る。基本的にはくだらなくておもしろいのだが、優香はこの番組には馴染まないと思った。またまたなっちか保田圭に出てほしい。
阿部和重『インディヴィジュアル・プロジェクション』。バイオレンスアクション純文学とでもいおうか、そんな感じの内容。
-----
七月十日(木)
「少年犯罪の刑罰と社会的影響、そしてその予防」
八時起床。新聞もテレビも、例の中学男子生徒による幼児殺害事件一色に染まっている。切り口はどの記事も番組も「少年犯罪の刑罰と社会的影響」である。ぼくもこの事件には大きなショックを受けたが、その社会的意味などを真剣に考えてみたわけではないのでここでは意見を避けたい。しかしひとつだけ、思ったことを記しておこう。絶えず揺れつづけるローティーンの不安定な心を外側から支えることで、このような事件を防ぐことができるなどと書いたり発言したりするマスコミ――このことばを使うのには抵抗があるが――の、なんと多いことか。おせっかいじみた教育はときに激しい拒絶につながるということを、誰もが忘れているように思えてならない。まあ、ぼくの考えはきっとまだまだ浅いのだろう。発言する資格などありはしない。
九時、事務所へ。一日中霧雨が降っている。いや、霧雨が舞っている。普段なら吹いているかどうかなど、よほど感覚を研ぎ澄まさないとわからないくらいの微風が細かな雨をしずかに運ぶ。風が地面や建物の外壁にぶつかり、乱れた流れがそこに生じると、小さな雨滴はさらに拡散し、四方八方へと当てもなく漂う。こんな天気の日は、傘をさしてもすぐに眼鏡に水滴がつく。
O社モバイルキャンペーンのタイトル、コピーなど。十九時三十分帰宅。
帰宅後、キリンビールの『まろやか酵母』とかいう名前の瓶ビールを飲む。義母がうまいから飲めとカミサンに勧めたらしいのだ。麦とホップだけを材料に使った本格的なビールだ、だとしたらエビスビールのような重厚な味わいと強烈なインパクトがあるのかな、などとついつい期待してしまったのだが、口当たりは極めて軽い。材料が変ってもやはりキリンっぽい味になるのはどういうわけなのだろう。軽い味のビールを高い金を払って――ラガーや一番搾りよりも当然高価なのだ――飲むつもりはない。美味かったが、もう二度と買わないと思う。
阿部和重『インディヴィジュアル・プロジェクション』。スパイ、ヤクザ、右翼、映画、フリオ・イグレシアス。うーん、よくわからん。
-----
七月十一日(金)
「眠れない夜のオノマトペ」
蒸し暑い夜の寝汗とけたたましくなる目覚まし時計、より確実に目が覚めるのはどちらだろうか。ムシムシする。妙なほどに寝苦しくて、気づくと顔が汗だらけだ。便所で小用を足し、ついでに洗面所で顔を冷たい水でザバザバと使ってべたついた汗を洗い流すのだが、蒲団に戻るとまたベタベタと汗が出て、ベタベタはやがてイライラに変り、クソ眠れん、などと考えているとそのうちイライラはウトウトに変り、最終的にはグーグーになるのだが、グーグーはまたもやムシムシに妨げられ、ぼくは再び目を覚ます。これを夕べは二回ほど繰り返した。二度目は冷凍庫からアイスノンを引っ張り出し、頭に当てて寝た。ヒヤヒヤする。イライラが消える。ヒヤヒヤはすぐにグーグーに変る。グーグーはもうベタベタに妨げられることはない。
八時起床。夜のあいだだけ閉めていたカーテンの裾のあたりから、明るい陽射しがこぼれてくるが、部屋の中は夕べほどではないが少々蒸していてぼくは少々不機嫌になるが、わが家の鳥たちはそんなことはまるで気にしていないようである。猫たちも同様である。
九時、事務所へ。十時すぎ、掃除などを済ませてから吉祥寺へ。ワイズフォーメンのバーゲンに行く。フリーランスだから、時間は自由に使うことができる。サラリーマン時代にこんなことをしたら罪悪感を感じるだろうが、今ならそんなことはなく、むしろこういった上手な時間の使い方ができることを少々うれしく思う。ただし土日に働くことも多いのだが。よくビートたけしが着ているような長袖の開襟シャツ(ただし色はグレー。たけしは白が多い)、半袖のレーヨンと麻の混合素材のシャツ(実は先日購入した開襟シャツと同じ素材のデザイン違い)、半袖のVネックのカットソー、長袖のカットソー、ベルトを購入する。今年はどういうわけか寿命が来た服が多く、とくにシャツの類が極端に少なくなっていたのだ。十一時すこしまえに、カミサンと合流。カミサンはレディスのワイズでシャツだかカットソーだかサマーニットだかよくわからんが、何か二着くらい買っていた。十一時三十分、義母と合流。東急裏の武蔵野文庫という名の喫茶店で早めの昼食をとる。店内には井伏鱒二の直筆の書が飾られていた。主人はかなりの文芸好きらしく、書棚には昭和の文豪の作品が所狭しといわんばかりに収められていた。しかしそのなかに一冊だけ、吉永小百合のエッセイがあったのをぼくは見逃さなかった。ふふふふふ。また焼き物も好きなようで、店でも使っている九州のなんちゃら焼き――名前を控え忘れた――を販売している。三人ともカレーセットを頼んだ。欧風カレーなのだが、でっかいジャガイモがドン、でっかい鶏肉がドンという、なんともわかりやすく、魅力的な盛りつけ。お味のほうもなかなかしっかりしていた。
午後、事務所に戻る。請求書の発行などの事務処理、そしてO社のモバイルキャンペーンのコピー。クイズの問題などを考えた。一案だけ、ちょっとばかばかしいクイズをいれてみた。採用になればいいのだが。
夕方より雨が降りだしたが、外に出なかったのでどの程度の雨なのかがよくわからない。
十八時。ベランダから外を見るとどうやら雨は止んだようなので、ちょっとだけ駅前をぶらつくことに。雨上がりの夕方は立ち話をする主婦が激増するようだ。あちこちで、幼稚園児くらいの子どもを連れた三十代くらいのTシャツからちょっと太めの二の腕をのぞかせた奥様たちがほっぺに手をあてたり腕を組んだりしながら井戸端会議に夢中になっている。子どもはこんなときに何を考えているのだろう。大好きなマンガのことだろうか。ご飯やおやつのことだろうか。無心だったらすごいと思う。
猫の手書店で週刊モーニングを百円で購入。信愛書店で舞城王太郎『阿修羅ガール』購入。
十八時三十分、事務所に戻る。O社モバキャンの残りの資料を受け取ったりクイズの問題を推敲したりしてから帰宅する。二十時。
二十一時、夕食を食べながら『金スマ』の神技リフォーム特集を観る。最近は陰陽師の心霊ものをあまりやらなくなってしまったのでさみしい。
阿部和重『インディヴィジュアル・プロジェクション』。なんだか平井和正の『ウルフガイシリーズ』を読んでいるような気分だ。
-----
七月十二日(土)
「水溜まりの夢想/アイスノンとコロッケ四個」
今日も寝苦しい、と思い目を覚ますと、外から雨音が聞こえてきた。ぼくが住むマンションの裏側は今空き地になっていて、梅雨に入ってからというもの、ここはつねに地面がぬかるんであちこちにいろんなかたちの水溜まりを作っている。大きなくぼみに雨水がなみなみと溜まることもあるし、ブルドーザーのキャタピラがつくったわだちのあとに沿って、用水路みたいに整然と水が流れていることもある。雨音を耳にして、ぼくはすぐに裏の空き地は今どうなっているのかと半分眠ったままのアタマで考える。寝ぼけているから想像力もたいして働かない。ぼくは空き地全体が沼のようになったところを夢想する。考えていたのではなくて夢をみていたのかもしれないから、文字通り「夢想」だ。にわかにできた都会の沼は、暗闇のなかでしずかに雨を受け止めつづけているのだろうか。たくさんの雨の波紋が同時に広がり、打ち消しあって消えていき、またそのうえにたくさんの波紋ができるさまが脳裏に浮かび上がる。外に出て確認してみようかとも思ったが、再び襲った睡魔には残念ながら勝てなかった。
九時起床。鏡を見ていると顔の下半分が急にマンガにしたような色形になり、鼻のしたがグングンと伸びだし、おちょぼ口になってしまう夢をみた。誰かに夢判断でもしてもらいたいものだ。
外は晴れていた。裏手の空き地に目をやる。ぬかるみはひどかったが、水溜まりなどほとんどできていなかった。だが雨は確実に降ったようだ。ベランダの手すりがほんのり濡れていた。
十時、事務所へ。O社キャンペーンのコピー。十七時、帰宅。義母が来ていた。カミサンとコロッケをつくっている。アタマを使いすぎたのか、夜中に水溜まりのことを考えすぎたのか、ひどく眠い。疲れている。すこし眠ることにする。アイスノンを使った。
十九時、目が覚める。すぐに夕食。コロッケを四個食べる。仮眠をとったせいか、食が進む。アイスノンの効果だろうか。
二十時からはテレビばかりを観て過ごす。リラックスモードである。
阿部和重『インディヴィジュアル・プロジェクション』。人殺しにつきあうはめになってしまった主人公。
-----
七月十三日(日)
「遠回りする散歩」
三時ごろだろうか。小便。六時ごろだろうか。小便。九時ごろだ、これだけははっきり覚えているが、小便。そして十時、小便ではなく、きちんと起床。身支度をし掃除を済ませ、十一時に遅めの朝食。このときになって、はじめてぼくは花子と麦次郎に朝食を与えていなかったことに気づく。小便の多さにわが膀胱はどうなってしまったのかと不安を感じていたのだが、その不安が猫の食事というぼくの使命を忘れさせてしまったわけだ。猫には軽く謝っておいた。花子は少々怒っていたが、これを書いている時点では、もう気にしていないらしい。
最近土日に出かけることが多かったので、今日は自宅で静養。読書など。夕方、カミサンと傘をさして散歩に出かける。善福寺川沿いの遊歩道を荻窪方面に向かって延々と歩く。川沿いの道は夕方になると犬の散歩でかなりにぎわうのだが、今日は雨のためにほとんど犬を見かけない。野良猫のパトロールに出くわすことも多いが、この天気ではパトロールどころではないのだろう。どこで雨宿りしているのかが気になる。環八を越して荻窪駅の南側あたりに来たところで、遊歩道からそれて駅前の商店街のほうへ進路を変える。いつのまにかオープンテラスのカフェや洒落た焼き物屋などが増えている。自然食を使ったフレンチの店も見つけた。時間があって天気のよいときに、ゆっくり回ってみようと思う。こだわりが尋常ではない感じのパン屋で夕食、朝食用のパンを買ってから帰る。適当な道を勘を頼りに歩いていたら、かなり遠回りをしてしまった。
夕食はスパゲティ、サラダと先ほど買ったパン。クルミとなんだかよくわからんがフルーツが入っていた。パン自体の味がしっかりしているので、菓子パンのような感じがしない。
阿部和重『インディヴィジュアル・プロジェクション』読了。阿部和重はJ文学の走りとかいわれているらしいが、とんでもない、本作はそんな狭苦しいカテゴリーに入れられたらかわいそうだというくらいの完成度。表面的には暴力的な雰囲気が全体に漂うスパイ小説のように思えるが、作者が描きたかったのは暴力を媒介とした個人の分裂、狂気、現実と虚構の境界なのだと思う。かなりの深読みが必要な作品。奥泉光の『バナールな現象』との相似点を指摘する人も多いようだが、奥泉氏がインテリ的確信犯としてサスペンスの手法を取り入れているのに対し、阿部氏は本質的に暴力的なものを渇望するからサスペンスやアクションの手法を取り入れている点で、二作は大きく異なっている。
読み終わったあとに、渡部直巳氏と阿部氏の対談を読む。ついでに渡部氏と保坂和志氏の対談も読む。
阿部和重『アメリカの夜』を読みはじめる。
-----
七月十四日(月)
「ヘルシーな一生」
七時三十分起床。夕べから雨は降ったりやんだりを繰り返しているようだ。裏の空き地が沼になる夢を思いだし、外を見る。今朝の水溜まりはかなり沼に近くなっているようだ。金魚でも放したら風流かもしれない、などとくだらぬことを考える。
八時三十分、事務所へ。スケジュールの確認とメールチェックを済ませて、すぐに外出。十時より、新宿のD社でPR誌の打ちあわせ。本号はかなり難航しそうである。帰社後はひたすら打ちあわせでいただいた資料の読み込みと不足している情報の収集。ひどく疲れる。十九時、カミサンといっしょに帰宅。
あちこちで紫陽花が枯れはじめている。終わりかけた紫陽花の花は、遠目に見るとサニーレタスのようである。花咲くまえはカリフラワーみたいで、散り際はサニーレタス。ヘルシーな一生だなあと思った。
帰宅後は読書とプライベートな雑文書き。
阿部和重『アメリカの夜』。読者を煙に巻くような文体。へんなの。
毎晩寝るまえに半ページとか一ぺージとか、そんなペースで読みすすめていた笙野頼子『愛別外猫雑記』をちょっと多めに読む。『レストレス・ドリーム』と文体は近いのだが内容はまるで違う。ホントに同一人物の作品なのだろうかと訝しんでしまう。金井美恵子、多和田洋子、それからこの作家を、保坂和志は渡部直巳との対談で「エクリチュール派」といっていたのを思いだした。そこですかさず渡部氏が「いっしょにしたら金井さんが怒るよ」と切り返したのも思いだし、ひとりで笑ってしまった。
毎朝、便所でウンコしながら読んでいる武田百合子『富士日記』。今日は夜にもウンコしたので、いつもより多めに読んだことになる。夜のウンコのときに読んだ箇所があまりにおもしろかったので、長いけど引用。昭和四十一年六月の話だ。富士へ行く御殿場まわりの道にあるトンネルは古くて凹凸も激しい。百合子は夫・泰淳を乗せて注意深く運転しているが、タイヤが穴に落ちた拍子にクルマのホイルカバーが外れてしまう。トンネルのなかなので後戻りするわけにもいかない。百合子はクルマをトンネルを出てすぐのところに停める。そこで事件は起きる。
☆ ☆ ☆
ふと気がつくと主人がいない。ひとことも言わずに、トンネルの中へ、すたすたと戻って行くのだ。しかもトンネルのはしっこでなく、まんまんなかを歩いて入って行くところだ。「あんなものいらない。なくても走れるよ。歩いて入っちゃ危ない」。私が呼び返しても、大トラックが轟音をたてて連続して出入りしているので聞こえない。ふり向かないで、真暗いトンネルの中に、吸いこまれるように、夢遊病者のように、大トラックに挟まれて入って行ってしまう。何であんなに無防備なふわふわした歩き方で、平気で入って行ってしまうのだろう。死んでしまう。昨夜遅くまで客があり、私が疲れていて今朝眠がったからだ。ぐったりしている私の、頭を撫でたり体をさすったりして、しきりになだめすかして起こしてくれたのに、私が不機嫌を直さなかったからだ。車の中で話しかけてきても私は意地の悪い返事ばかり返した。私は足がふるえてきて、のどや食道のあたりが熱くふくらんでくる。予想したことが起る。トンネルの中で、キィーッと急ブレーキでトラックが停る音がし、入って行く上りの車の列は停って、中でつかえている様子。バカヤローといっているらしい運転手の罵声が二度ほどワーンと聞えてくる。私はしゃがんでしまう。そのうちに、主人は、またトンネルのまんまんなかを、のこのこと戻ってきた。両手と両足、ズボンの裾は、泥水で真黒になって私の前までくると「みつからないな」と言った。黄色いシャツを着ていたから、轢かれなかった。ズボンと靴を拭いているうちに、私はズボンにつかまって泣いた。泣いたら、朝ごはんを吐いてしまったので、また、そのげろも拭いた。
☆ ☆ ☆
うーん。脱帽。こんな文章をサラリと書けるようになりたいものだ。
-----
七月十五日(火)
「今日の事件簿」
●沼化進行事件
●鰯はよく噛んで食え事件
●『アメリカの夜』は分裂小説事件
●ハッシュドビーフとハヤシライスの違いがいまいちわからない事件
●向かいのビルの屋根の上に満月事件
●小さなキーボード事件
●おばちゃんにもADSL事件
●終わらない事件
-----
七月十六日(水)
「すべからず」
夕べは三時に寝た。一時半まで仕事をしていたからである。超特急進行の物件が舞い込んできたためだ。二十二時ごろまでには家に帰って数時間をのんびりと自分と家族と猫とトリのために使うのが理想なのだが、そうもいっていられない。働かざるもの、喰うべからず、遊ぶべからず、家族をもつべからず、ドウブツとともに暮らすべからず、読書すべからず。
八時十五分起床。九時過ぎ、事務所へ。昨夜終わらせることができなかったPのキャンペーン告知チラシの構成とコピーに取り組む。時間がないのだが、なるべく工夫してみようと心がける。
十五時三十分、外出。L社のN氏と打ちあわせ。K社の自動販売機ならびにコンビニ用のPOPの企画。
L社のある小石川は植物園があるだけでなく、街並みにも濃い緑が生い茂っている。地下鉄の駅からL社までのあいだにある、坂に沿って作られた遊歩道には無数の桜の木が植えられていて、五月ごろは陽の光を照り返す新緑に心奪われてしまうこともあった。梅雨も終わろうとしているこの時期の桜の緑は、あの頃とは比較にならぬほどに濃く、力強くなっている。葉の色が深いせいだろうか、たいして晴れていないというのに木漏れ陽がみょうにまぶしく感じられた。西荻にもこんな道があれば、と思う。意外に緑が少ないのは中央線沿線(三鷹まで)の弱点である。
十八時過ぎ、帰社。
夜もPのキャンペーン告知チラシ。一段落したところで、D社PR誌の取材用ヒアリングシートの作成。二十三時、終了。
阿部和重『アメリカの夜』。分裂、気違い、恋、マゾヒズム。ブルース・リー、フィリップ・K・ディック、アロンソ・キハーノ=ドン・キホーテ・デ・ラマンチャ。なんだかよくわかんなくなってきた。でもおもしろい。
-----
七月十七日(木)
「突然話しかけてみた」
四時、花子に足の甲を思いきりひっぱたかれて目を覚ます。ご飯の催促だ。熟睡していたのと花子のツメがとがっていたのとの相乗効果で、きわめて唐突かつ比喩しがたいほどの痛み。やめてほしいと本気で思った。
八時起床。九時、事務所へ。P社キャンペーンチラシ、K社自動販売機のPOP企画。日中、一時間くらい西荻の街をさすらいながら自動販売機を視察する。ときおり利用者に「広告やってるものなんですが」とか「自販機の調査しているものですが」とか適当なことをいって話しかけ、使用感やPOPについての感想などを聞きだした。変なやつだと思われたに違いない。疲れた。
二十三時、終了。
今日は頭が飽和状態だったので、本はほとんどよまなかった。阿部和重『アメリカの夜』を二ページだけ。
-----
七月十八日(金)
「ポン酒と蕎麦/桃子のラリアット」
夕べも雨が降ったのだろうか。窓をしっかり閉めて寝たからだろうか、雨音はまるで聞えてこなかった。マンション住まいがつづくと、天候の変化に鈍感になってしまうようだ。雨に気づいたのは、八時に目が覚め、リビングのカーテンを開けているときだった。ベランダの手すりに水滴が溜まって不規則な水玉模様ができていた。空を見上げる。すでに止んでしまっていたようだ。
九時、事務所へ。路面は濡れ、路肩に生える草木もまた濡れている。街の濡れ具合から夕べの雨の強さを想像してみる。かなり降ったように思えるが、実際はどうだったのだろうか。
K社POPの企画書を納品。N不動産チラシの原稿、O社チラシのデザインチェックなど。
一時間に一度くらいの割合で、ベランダに出る。ときどき立ってうろついてみたり伸びをしてみたりすることで、軽い気分転換をするわけだ。午前中はまだ道路がかなり湿っていたが、午後になるとすこしずつ乾きはじめた。十五時ごろには、雨の形跡はすっかり消えていた。ところが、十八時ごろから夕立のような勢いで激しい雨が降りだす。ベランダから雨宿りする女子中学生の姿が見えた。
二十時終了。このころになると、雨は小降りになっていた。
蕎麦を喰おうということになり、カミサンと草庵おおのやへ。日本酒にはビールよりポン酒だ。大平海というぼくの地元茨城の地酒を飲む。辛口だが淡くない。しっかりした旨味が口の中に残り、それが料理をさらに引き立ててくれる。稚鮎の天ぷら。内臓の苦味と身の淡泊な甘さのコントラストがたまらない。小学校のとき、オイヌマアユコちゃんという名の同級生がいたことを思いだした。じゃこと山芋のサラダ。こちらは予想通りの味だが、ドレッシングに一工夫あるらしく、野菜の味が引き立っていた。ひょっとすると、蕎麦つゆをベースにしたドレッシングなのかもしれない。よくわからないが。閉めはせいろそば。薬味はいらないかな、と思うくらい蕎麦の風味がしっかりしている。蕎麦は秋口に収穫されるから夏の蕎麦はまずいというが、このせいろに限っていえばそうでもない。蕎麦粉の保存状態がいいのか、蕎麦打ちの腕がいいのか。蕎麦粉自体がいいものであるのはいうまでもない。今が夏というより梅雨であるのも影響しているのだろうか。わからん。二十二時帰宅。
帰ると、義母の家で飼っている桃子がウチに来ていた。二週間ほど単身赴任中の義父のところへいくので、ウチで預かることになったのだ。帰宅してすぐに桃子に声をかけると、少々興奮気味だった彼女はいきなり「フウーッム!」と変な声をたてながらぼくをギロリと、下から上へ睨みつける。ガンを飛ばすというか、メンチを切るというか、そんな類いの凄みが感じられる。怒ってるのかい、と声をかけると、興奮が最高潮に達した桃子はぼくの右の足首にウェスタン・ラリアットをかまして、そのまま廊下のほうへダダダダダと走り去っていった。
阿部和重『アメリカの夜』。白と黒の衣装。春分の日と秋分の日の二項対立。わかりやすいなあ。
『タモリ倶楽部』がないので、おとなしく寝る。
-----
七月十九日(土)
「目覚ましはなっていない」
九時起床。雨こそ降っていないが空は相変わらずの灰色で少々気が滅入る。
午前中は書斎の片づけ。机の引き出しにかなりの量のゴミが紛れている。ゴミか必要なものかの判断に困るようなものもどんどんでてくる。こういうときは容赦なく捨てることにしているが、あとで後悔することも多い。だが捨てる快感、いいかえれば所有するものが少なくなること、身の回りに何もない空間が増えることの快感にしばし酔いしれたくて、片づけをつづける。いっそのこと、何ももたないで暮らしていけたらと思うのだが、その反面ぼくの物欲はなみなみならぬものがある。着る服にこだわり、本は借りるのでは気が済まず買わないと落ちつかなくなり、最近こそ購入する機会は減ったがCDは収納しきれないほどに抱え込んでいる。音楽などここ何年か真剣になって聞き入ることは稀なのだから聞かないものはどんどん処分すべきだと思うのだが、これがなかなかそうも行かない。
午後から外出。事務所の向かいにある不動産屋に行き、物件を探す。現在の事務所は四、五人で働くことを想定して借りていたから、今のスタジオ・キャットキックの体制では少々広すぎて、おまけに家賃の負担も大きい。引越しにもある程度の費用が必要だからこれまで我慢しつづけていたのだが、資金繰りがうまくいきそうなので、思いきって秋に今の事務所を引き払おうと思っている。「アルゴシティ」という名の不動産屋で、以前義父母が東京の家を探したときに世話になった。ヒョロリとした外見だが気さくで笑顔を絶やさない五十代の男性と、その妻らしいいかにもやり手といった感じの凄みの効いたゴージャスな風体の巨乳の熟年女性、そして同じく巨乳の二十代後半らしい女性の三人がぼくとカミサンを迎えてくれた。三人とも人当たりはよい。店のテーマカラーはピンクらしい。デスクや棚は白が貴重なのだが、ブラインド、椅子、台所用品、デスク小物と、細部のアクセントはすべてピンクで徹底されている。おそらく巨乳熟女のラッキーカラーなのだろう。
吉祥寺へ。三越の地下にある「故宮水餃」で中華ソバと水餃子。上にある和雑貨屋でまたたびの入った猫のおもちゃを二個購入。つづいて東小金井の義母の家に行く。今朝、カミサンのケータイに「目覚ましをとめ忘れたような気がするから見てきて」というメールが入っていたからだ。目覚ましはしっかりとめられていた。こういうのを不安神経症というのだろうか。知らないけど。
再び吉祥寺へ戻り、「House Styling」で雑貨を、「ロンロン」の食品売り場でベーグルを購入。西荻のスーパーに寄ってから帰宅する。
夜はまた餃子鍋。キムチを入れてみた。
阿部和重『アメリカの夜』。出た、暴力。暴力というのも、愛や死とおなじくらい、文学でよく取りあげられるテーマだなあ、と思いながら読む。
-----
七月二十日(日)
「西荻散策/珈琲が染みる剥げ、ジャズが染みる傷」
海の日である。だがこんな天気じゃ海も人も浮かばれないなあ、などと思いながら起床。九時三十分。
藤田嗣治の猫を題材にした作品ばかりを集めた展覧会が銀座で開かれると聞き、今日はそこに行ってみようと考えていたのだが、展覧会は来週からであったため予定がひどく狂う。午前中は読書と駄文書きをして過ごすことにする。
午後から外出。西荻の町をブラリと散歩することに。線路の南側の住宅街を適当に歩いてみると、西荻にはかなり古い建物が多いことに気づく。木造モルタルのアパートや中途半端にモダンで欧風の一戸建てがあちこちに残っている。アパートはともかく一戸建てはかなり個性が強く、たとえば理由はわからないが玄関の横の外壁に大きな壁掛け時計を付けた家があったりする。家の主人がこまめに時間をチェックするのが癖だったりするのだろうか、それとも夜中の訪問客があまりに多いので「今何時だと思ってるんだバカヤロー」ということをこの時計で伝えようとしているのか、はたまた家とは形あるもの、形あるものはいつかは朽ち果てるという真理を時計を設置することで表現し、その家を訪れるさまざまな生き方や考え方の異なる人間たちに伝えようとしているのか。空想が果てしなくつづいてしまう。野良猫にも出会った。南側では二匹見かけたが、一匹は身重だったようだ。野良猫の保護――彼らはそれを「地域猫」化と呼ぶ――を目的に設立されたNPOや地域のボランティア集団が、野良猫の去勢/避妊手術を進めることでその数を減らそうとしているが、それでも野良猫は増えつづけている。本能だから仕方ないのではあるが、今の世の中は野良猫にはかなり住みにくいのであるから、生まれてくる子猫たちの行く末はかなり暗いものになってしまう。どうにかならないものだろうか。ぼくら夫婦はときおりNPOに救援物資を送ったり捨て猫防止の看板の制作を手伝ったりしているが、もっと多くの人たちの協力が必要なのかもしれない。
駅のあたりで道を変え、「丹波通り」と呼ばれている道を吉祥寺方面に向かってのんびり歩く。こちら側になると急に緑が深くなる。武蔵野の森が近くなるからだろうか。丹波哲郎の家はちょうど武蔵野と杉並の境目あたりに建てられており、周囲は緑ですっぽりと囲まれているように見える。実際はさほどでもないのだろうが、そのように感じられるのはおそらく丹波の霊力の仕業に違いない。
丹波邸の裏側で折り返し、伏見通りを通って駅へ戻る。途中『どんぐり亭』という喫茶店へ。三代つづく歴史ある喫茶店だそうだ。RefineのKaoriさんのオススメである。店内には年季が入った調度品がズラリと並ぶ。壁も床もテーブルもこげ茶色のニスが塗られた木でできていて、それらは多くの客が繰り返し手で触れたりコーヒーカップを置いたりしたために剥げたり傷が入ったりしているのだが、その剥げや傷のひとつひとつにまで、店内に漂う煎れたての珈琲の香りが染み込んでいるように見えた。珈琲の香りはジャズの調べとともに流れる。壁にはマイルスのレコードジャケットが飾られていた。もちろんジャケットも珈琲の香りをたっぷりと吸いこんで、茶色く煤けている。ぼくは苦味ブレンドと名付けられた珈琲と自家製ジャムの塗られたマフィンのセットを、カミサンはおなじ珈琲と焼き菓子のセットを注文する。珈琲は豆を厳選しているだけでなく自家焙煎したものをその場で煎れているだけあって、味が深い。ゲートシティ大崎にあるハイチ・コーヒーの専門店で飲んだものの次くらいに美味いと思った。『それいゆ』の水だし珈琲よりも上である。ジャムはペクチンを使っていないため口当たりが自然である。砂糖ではなくはちみつを使って甘味を出しているのだそうだ。これも病みつきになりそうである。カミサンの食べた焼き菓子、つまりクッキーなのだが、こちらも自家製らしい。ぼくはクッキーの類いはあまり好きではないので味はよくわからないが、カミサンは「わたし好みでいい感じ」と絶賛していた。
そのまま駅へ戻り、二十パーセントオフのセールをしている西友で靴下、パジャマ、食材などを購入。そのままスーパー、百円ショップなどを数軒はしごしてから帰宅。
夕食はキーマカレーを作って食べた。いつもはトマト缶を使うのだが、今日は減農薬のプチトマトが手に入ったのでそれを使ってみたら大正解だった。缶の場合はトマトの酸味と水分に随分と悩まされ、味付けが難しくなってしまう。ところがプチトマトは甘味は強いが酸味は弱く水分も少ないため、カレーにコクと爽やかさを与えてくれるがそれ以上のでしゃばりはしないから、とても扱いやすい。米はサフランライスにしてみた。要するにサフラン、シナモン、ベイリーフ、カルダモン、バターなどを入れた炊込みご飯であるが、これもはじめての試み。カレーとの相性は抜群である。
二十一時よりNHKの『新日曜美術館』。前衛生花師の中川幸夫のドキュメンタリー。昨年行われた、二百万枚におよぶチューリップの花びらを空中からばらまくという「舞う生花」を実現したときの模様などが紹介された。花びらが散るなかで、大野一雄が舞踏を披露する。鬼気迫る美しさがあったが、できればこれをギャラリーのいない状態で、そして青空のもとで見たいと思った。
番組内で紹介された中川のことばをいくつか。
「感動とは、また驚き」
「しかられながら生きてきたって感じだよねえ」
「生花とは個人の行為であり、自分をいつわった行為はいつかは破れる」
阿部数重『アメリカの夜』読了。すべてのクリエイターの卵の励ましになるような小説、とでもいえばいいのだろうか。かなり屈折していておまけに難解ではあるが。
舞城王太郎『阿修羅ガール』を読みはじめる。
----
七月二十一日(月)
「今日は句点の限界に挑んでみました。さすがに金井美恵子さんみたいにはいかないです」
八時半に目覚ましをセットしておいたというのに睡魔の誘惑に負けて十五分ほど余計に寝てしまい、自分を甘やかしてしまったことを悔いたが、よくよく考えるにきっちり時間を守って行動しなければいけないほど忙しいわけではないので、気にしないことにして余裕をもって身支度をしていたら、今日は昨日の「海の日」が日曜だったので振替休日になっているのではなく、数年前に施行されたハッピーマンデー法というふざけた名前の――おそらくは俗称なのだろうけれど――法律で七月の第三月曜日が「海の日」ということになってしまっていて、したがって昨日ではなく今日が「海の日」なのだということにようやく気づき、昨日の日記に「今日は海の日」みたいなことを書いちゃったな、しまったなあなどと考えていたが、たいした問題ではないので気にしないことにしたが、ということは今朝おれは十五分余計に寝たことと、海の日を間違えたこと、ふたつのことを「気にしない」と決めたわけで、朝から「気にしない」なんてことばかり考えてるなんて相当能天気だなおれは、とも思ったが、実はさほど能天気なわけではなく、アタマのなかは朝からすでにN不動産のチラシのコピーをどのように仕上げるかと、昨日一昨日と書きかけていた駄文をどのようにまとめるかということばかりを考えていたのだから、どっちかというと神経質というべきで、おまけに「能天気」ということばは、灰色の雲がいっぱいで突然ポツリポツリと雨粒が肌に触ってこりゃ降るかな、なんて思わせるような空模様の日には全然似合わないから口にすべきではない。
夕方からケイゾーが世話になっている八王子だかどこだかにある陶芸のアトリエの仲間が開く七人展のオープニングパーティーにカミサンといっしょに出かけることにしたが、会場のあるお茶の水に行くのは一年ぶりくらいで、落ちついた街並みはやはり文学とか芸術が根づいた地域性みたいなものが作り出しているのだろうなあなどと考えながら駅を出てみると、たしかに街並みは静かなのだがニコライ堂のすぐそばに巨大なインテリジェンス・ビルディングがそびえていたりして、こいつはひどい興ざめだよなんて感じていたら、いつの間にかぼくら二人は会場に着いていて、なかを覗き込むとオープニングパーティーはもうはじまっていて、ケイゾーは元気そうに七人展の仲間の一人らしい人物と話しあっていたのだが、その表情がとても明るかったので安心して入場し、早速拝見、すると以前よりも飛躍的に上手くなったケイゾーの焼き物はなかなか魅力的で、全体は白いのだがくぼみやふちの部分に溜まった釉薬がほんのり緑がかって見える一連の作品は、朝の食卓に並べたらさぞかし目覚めもいいことだろう、今朝ぼくが囚われてしまった一連の思考の混沌など能天気さと清々しさで吹き飛ばせるに違いないなどと一人で勝手に頭のなかで印象批評を繰り広げ、ほかの人の作品もみて結構変な作品もあったりしたので同じ先生に習っているはずなのにみんな個性的だなあ、文学の場合はエクリチュールの問題に直面してみんな没個性になりがちなのにねえなどと比較芸術論めいたことを考えていたら、荻窪で陶芸家活動しているnananaさんが会場にやって来て、nananaさんは同業者ということでケイゾーのお師匠にあたる先生と話し込んでしまって、そのあいだケイゾーと話したり七人の作品をいろんな角度から眺めなおしたり何を載せたら美味しそうに見えるかなんてことを考えたりしていたら、nananaさんがようやくこちらに戻ってきて、いっしょに作品を見ていたら、結局仲のいいものどうしが集まったというので、オープニングパーティーは陶芸を見ながらの飲み会に変ってしまい、たらふく飲んで喰って、二十時に帰った。
舞城王太郎『阿修羅ガール』。「性と愛」というのはこの人のテーマなのかな。
-----
七月二十二日(火)
「ドタドタドタ、ムシャムシャムシャ、ポトリ」
朦朧とした意識と長引く梅雨の湿気が重なり合って相乗効果を生み、早朝のわが家は異質な空間と化している。そのなかを、三匹の猫が疾駆する。一番活動的なのは花子だ。湿って蒸し暑い部屋のなかでぼくが目覚めるのをじっと待ちつづけていたらしいが、やがて待つことに飽きたに違いない彼女は、ドタドタドタと廊下を走る。活発さなら桃子も負けない。花子はベッドのそばまで来たが、桃子は廊下でぼくの目覚めを待ちつづけ、寝室のドアからぼくの躯が出てくるや否や、ドタドタドタと廊下を走る。麦次郎はひどくのろまで、ぼくが起きるまではベッドのうえで一緒に眠っていたのだが、花子と桃子のドタドタドタでたちまち目が覚め、遅れを取り戻そうとでもいうのか、彼女らに負けないくらいの元気さで、ドタドタドタと廊下を走る。そしてぼくが缶詰を開けると、三匹そろって、ムシャムシャムシャとご飯を食べる。
八時起床。九時、事務所へ。空き地の沼はとうとう水溜まりに戻ってしまった。今年は梅雨が長引いており日照時間の短さの農作物への影響が懸念されている。そんなニュースを聞くと降水量も多いのだろうと思うのだが、実は雨量は例年にくらべて少ないのだという。だから空き地の沼は干上がったのだ。ぱら、ぱら、ぱらとすこし降っては、すぐに止む。ふり返ってみれば、今年はたしかにそんな降り方が多かったかもしれぬ。十年近くまえのことだったと思うが、天候不順により米が凶作となり――「不作」ということばを使っていたと思うが、今ひとつ緊張感がないのでここでは「凶作」とあえて書いてみる――、米不足が社会問題となったが、あの年の夏はどんな天気だったろうかと記憶をたどるが、まったく思いだせない。この長引く梅雨が日本の食料事情になんらかの影響を及ぼすのはたしかだろう。それを試練と受けとりスムーズな打開策を講じることができるか、否か。
午前中は事務処理のために動く。法務局、銀行、そして新宿の国民金融公庫。十二時過ぎ、西荻に戻り『ビストロさて』でハンバーグランチ。帰りがけに『猫の手書店』で金井美恵子『軽いめまい』を購入。午後からは伝票の整理とN不動産チラシのコピーのフィニッシュ、J社パンフレットのコピーの仕切り直し。二十時、帰宅。
二十二時、夕食。実家から送られてきた野菜を使って麻婆なす、棒棒鶏など。食べはじめようとしたら、桃子がリビングにウンコを落としていった。義母によれば、この子はウンコしたあとドタドタドタと走り出す癖がある。そのときに、尻あたりに生えた毛に引っかかったウンコといっしょにダッシュすることも多いそうだ。足が止まると、ウンコは床にポトリと落ちる。ぼくらがこれからムシャムシャムシャとご飯を食べようというときに、ウンコを転がり落とすとは。「猫のウンコはかりんとう」という自作の唄をネットで公開している人がいるが、断言しよう、猫のウンコは猫のウンコだ。それ以外の何物でもない。いつ見たって、どこでみたって甘い黒糖のおかしではなく、猫缶とカリカリの成れの果て、腸に溜まった食い物のカスだ。くっさいクソだ。クソッタレだ。今度桃子がご飯を食べているときに横でウンコしてやろうかと本気で思った。もちろん実行することはないだろうが。
舞城王太郎『阿修羅ガール』。この作品は純文学として読まないほうがいい。もともとボーダーレスな作品なのだが。日本では、ボーダーレス=じつは純文学、という図式が常識となってしまっている。村上春樹のせいだろうか。
暴力。このことばも、舞城の作品に共通するキーワードなのかもしれない――まだこの作品以外には一作しか読んでいないからわからないのだけれど。
-----
七月二十三日(水)
「あたりまえの無心/生活のリズム、リズムのスタイル」
ぼくは日本一たたき起こされることが多い三十代かもしれない。文字通り解釈すると自分で目を覚ますこともできないだらしない中年男のように思えるが、そうではないのだ。毎日規則正しく目覚めるべき時間に目覚める。それくらいのことは簡単である。ではなぜたたき起こされる必要のないぼくがたたき起こされなければならないのか。答えはひとつしかない。猫にご飯を与えなければならないからだ。無論たたき起こしてくれるのは猫である。桃子を預かったおかげで、早朝のたたき起こしのインパクトは二倍に膨れ上がる。ぼくが薄暗い部屋のなかですこしだけかゆくなった眠い目をこすりながら目を開けほんのすこし腰痛のする躯を起こし小便を我慢しながらずりあがったパジャマズボンの裾もそのままにキッチンまで歩いて缶詰めを開けて皿に盛りつけ「ご飯」といいながらそれを射しだしてあげても、猫たちは「それがあたりまえ」といわんばかりの素知らぬ態度でご飯を食べる。無心に食べる。
ぼくをたたき起こすときも、猫たちは無心なのだろうか。
七時十五分起床。取材の日は生活のリズムが狂う。リズムが狂うと忘れ物をすることが多くなるのはなぜだろうか、と考えてみる。朝の身支度というものは、やることの数はもちろん、ひとつひとつの時間配分、タイミング、そういったものがすべて有機的につながりあいながら構成されているのではないか。だから、ひとつでも要素が狂うと構成はなし崩しになり、リズムがくずれる。早起きや寝坊はそのリズムを狂わせやすいものなのだ。つきつめて考えるに、ライフスタイルとはリズムであり、生活における動作の有機的なつながりが作る形のことなのではないか。よくわからんが。
八時過ぎ、事務所へ。雨は今にも降りだしそうである。メールチェック、スケジュール確認を済ませて事務所を出る。千葉県L市のS大学へ。構内LANの取材である。学会の大御所ともいうべきI教授、そして実務を担当したというN助教授から話を聞く。当初インタビュー相手は四名の予定だったが、学会のようなものの準備でかなり多忙な状態となっているらしく、一分一秒を惜しむありさまだからインタビューは勘弁してほしいといわれたので断念した。キャンパスは広い。中庭には芝生が敷かれ、そこでは暇そうな学生たちがベンチに座っておしゃべりしたり、サッカーボールをパスしあって遊んだりしている。ときおり聞える鳥のさえずりはコゲラのようで、「ギイ」という音が耳に入るたびにぼくはあたりを見回してしまう。自然に囲まれ広々としたキャンパスは学生たちの向学心にどんな影響を与えているのだろうか。
十六時、東京へ戻る。事務所で一息ついてから、事務処理、それからN不動産のチラシ。二十時、帰宅。
タモリの『トレビアの泉』を見る。古い丸ノ内線の車両はブエノスアイレスで再利用されていること、ゴルゴ13の初登場シーンはパンツ一丁だったこと――これは一巻を所有していたのだから覚えていてもいいはずなのだが、失念していた――、ホタテはすいすい泳ぐこと、などを学ぶ。
舞城王太郎『阿修羅ガール』。作中に《天の声》なる、明らかに『2ちゃんねる』をモデルにした巨大掲示板が出現する。『2ちゃんねる』との大きな違いは、そこで渦巻く暴力的な欲求、破壊的な衝動が、実社会で具現化されているということ。作者は『2ちゃんねる』の危険性を予言しようとしているのか、はたまた暴力を具現化したほうがおもしろそうだからそうしているのか。
おそらく後者だろう。そうでなければ、この小説は成立しない。聖人君子に小説は書けない。ちょっと精神が病んでいるくらいで、ちょうどよさそうだ。
-----
七月二十四日(木)
「じゅるじゅるな一日」
鼻水が止まらない。夕べ冷えて風邪をひいたのか、アレルギーが出ているからか、はたまた柏でなにやらおかしな花粉をもらってきたか。原因はわからないが、八時に起床してから出かけるまでの一時間で十回は洟をかんだ。点鼻薬でごまかしてから家を出る。
九時、事務所へ。銀行まわり、N不動産チラシ、J社PR氏など。空からは依然として梅雨の気配は消えず、いつ降るか、いつ止むかばかりに気をとられ、降らないと傘を持ち歩いたことを後悔し、降ると傘を置いて家を出たことを後悔する。そんな日々が続いているが、今日の午後はほんの刹那、雲が切れて陽が射した。太陽の光を感じると、雨空なんぞに振り回される自分が卑小に思えてくる。もっとも太陽系の中心部から八分かけて地球へと降り注ぐ光と自分を比べても、やはり感じるのは卑小感なのだが。
十五時、カイロプラクティック。終了後、吉祥寺の「パルコブックセンター」にて、笙野頼子『極楽/大祭/皇帝』『タイムスリップ・コンビナート』、多和田葉子『ヒナギクのお茶の場合』『球形時間』。
十七時、帰社。業務再開。J社PR誌の誌面構成が見えたところで帰宅。二十一時。
夜、ネプチューンが出演しているビンボーバラエティ番組を見る。新宿にある蔦に侵食されたボロボロの木造一戸建てに住む自称映画監督にショックを受ける。働かずして生きていけるのは、友人の支援があるかららしい。彼にどんな魅力があるのだろう。同情されるのもひとつの才能であり、魅力である。彼の生き様よりも、支援している友人のほうが気になった。どんなヤツなのだろうか。この手のコトは、想像すると止まらなくなる。
舞城王太郎『阿修羅ガール』。「夜もヒッパレ」のメンバー、石原慎太郎、よくわからん外人の俳優。なんだこりゃ。グッチ裕三とモト冬樹はなにかの陰喩なのだろうか。不思議だ。
-----
七月二十五日(金)
「誕生日」
今日で三十四歳になる。と書くと年齢のなんと重苦しいこと。胸が苦しくなってくる。どこぞの俳優だかなんだかが素敵に歳をとってとかなんとかいっているのを聞いたことがあるが、三十代、四十代に限っていえば、そのようなことは起らない。三十になるまでは自分の年齢の軽々しさが恥ずかしく思えたが、それを過ぎると、やって来るのは歳相応の自己保身と退屈な日々に対する麻痺症状だ。
六時、猫の三角編隊に襲撃され、やむなく白旗をあげるように起床し、ご飯を与える。缶詰めを開けるまではまぶたが重くて視界がときおりひっくり返ったりする有り様だったのだが、蒲団に戻ると不思議なことに、妙に頭が冴えてくる。以後、七時過ぎまで眠れず。八時の目覚まし時計で、自分が半分寝ていて半分起きているような状態、まどろみとか夢うつつとかいうとそれなりに貴重な時間をすごしたように聞えなくもないが、実は惰眠ともいえずストレス解消とも疲労回復ともいえない無駄な時間を中途半端な精神状態とやはり中途半端な肉体の状態でただダラダラと過ごしただけだ。眠い。
九時、事務所へ。青空が恋しいわけではないが、灰色の空にはそろそろお引き取り願いたいところだ。夏に咲く花が、ぼやけて見える。
J社PR誌の取材内容のまとめと原稿執筆。
昼、西荻窪駅南口の松屋のそばにあるイタリアン「麦香亭」にいってみる。小エビとベーコンのペペロンチーニを注文するが、材料と味に満足できず。激しく後悔。
夜、L印刷のL氏より電話。コンペだったPのチラシ、採用になったとのこと。朗報に一瞬心躍るが、すぐに赤字の対応をして月曜に修正デザインを出さなければいけないと聞き、少々心が重くなる。二十二時、店じまい。
夕食はぼくの誕生祝いを兼ねて焼肉屋へ。誕生日だといったら、湯飲み茶碗をプレゼントされた。
舞城王太郎『阿修羅ガール』。斬新な三途の川の描写、そして主人公アイコのなかに隠れたもう一人の人格であるシャスティンの物語。
-----
七月二十六日(土)
「ティーポット物色記(簡易版)」
九時起床。十時、事務所へ。秋の長雨のような空がだらだらと広がっている。ぼくの目のまえを通りすぎていく人々が着る服は、半分は夏のものだが、あと半分は春や秋に着るべきもののように見えなくもない。
Pのキャンペーンチラシの原稿、J社PR氏の原稿など。
十六時、吉祥寺へ。パルコ、東急などを回り、事務所で使うティーポットを物色する。東急にあるベトナムカフェ兼雑貨店で購入したが、そのあとに同じフロアにあったワゴンのなかに使いやすそうなガラス製のものを見つけ、こちらも買うことにする。先に買ったベトナムのものは家で使い、ガラス製を事務所で使う。
猫缶、食材などを買ってから帰宅。十九時。
夕食はお好み焼きでお手軽に。
舞城王太郎『阿修羅ガール』。帰らぬ兄を探しに、怪物が出ると噂されている森のなかへはいっていくシャスティン。森のなかで、死の歌が響きわたる。バラバラ殺人の予感。時代を反映させる、そのやりかたがうますぎる。
-----
七月二十七日(日)
「アート三昧」
首輪に鈴をつけているのは桃子だけだから、近づいてきただけですぐにわかる。昼間なら鈴の音を聞いただけでぼくは「もーもこー」と声をかけ、足元でコロリと転がった彼女の腹やら首やらほっぺやらをグリグリといじり回してやるところだが、朝五時となると話は違う。鈴の音は廊下を通ってぼくらの寝室にやってきて、しばらくベッドの下でチリンチリンと鳴りつづけていたが、やがてそれはウニャーウニャーという猫の鳴き声と混じって聞えるようになり、最後には、チリンとウニャー、二つの音がぼくの耳元で聞えるようになる。こうなったらもう起きるしかない。冬ならまだ真暗な時間だが、七月の終わりころの早朝五時は薄明るい柔らかな光がすこしずつ家のなかに射し込みはじめる時間で、熟睡を邪魔されるのと、猫にご飯を与えるのは少々辟易するが、この光を感じることができるので、とりあえずチャラ、ということにして無理やり自分を納得させる。ご飯を与えてから便所へ行く。明け方の小便は、出しきるまでに時間がかかる。
十時起床。だが九時ごろから桃子が大騒ぎしていたから眠れていない。リビングに行くとゲロがある。どうやら桃子は「ゲロがでちゃった。そうじしてよ」と訴えつづけていたらしい。実の母親である花子も「うんこがでた。おといれのそうじをしてください」と訴えることがときどきある。似た者親子、といったところか。
十二時。フジテレビの『ウチくる』という番組に談志師匠が出演していた。弟子は出てこない。志加吾やキウイはどうしているのだろうか。
十三時、外出。銀座へ。オープンのときは話題になったエルメスのビルへ行く。ガラスのタイルで覆われたデザイン。建築物のデザインを主張し強烈な存在感を周囲にアピールするのは過去の手法らしく、現代ではいかに街並みや環境のなかに溶け込ませるか、というのが重要になるらしい。品川あたりに続々と建てられているインテリジェンス・ビルや先日訪れた青山のプラダのビルを見ると、そういった思想がよくわかる。このビルも例外ではないようなのだが、ガラスのタイルという素材はエルメスのブランドイメージに合致しているのだろうか。高級ブランドが建築を通じてブランドアイデンティティを確立・強化させるという手法もまた最近の流行らしいが、このエルメスのビルはそれに成功しているかというと、ぼくにはよくわからない。否定するのは容易なのだが、実際にこのビルのなかへ入ったときに見かける、楽しそうにショッピングする人たちを見ると、建築がミスマッチであるとは断言しにくくなってしまうのだ。単にぼくがエルメスというブランドを理解していないだけの話かもしれない。
八階で開催されている生花師、小川幸夫展を見に行く。フロアいっぱいに、大量のラベンダーが蒔かれていた。一種のインスタレーションだろう。会場は柔らかな香りに包まれている。色と形と香りの生花だ。作品は二エリアから成立している。片方は濃い青色のラベンダーと薄い灰色がかった紫色のラベンダー、二種類をつかったもの。こちらは部分部分で高く山のように積まれていたり、平地のように平らにちりばめられたりしていて、視線を低くして眺めると、ラベンダーが日本の山野や平原、川や海などの縮図のように思えてくるから不思議だ。もう一方では、床に不規則に置かれた丸形の赤、青、白のシートの上に薄い色のラベンダー薄く散らした作品。ラベンダーは、ぼくには砂漠のように見えた。丸いシートはオアシスのようにも、街のようにも、戦場のようにも、そして空爆後の廃虚のようにも見えてくる。それらを一様に、ラベンダーの甘い香りが包んでいる。
つづいて猫専門の画廊『ボザール・ミュー』へ。藤田嗣治の猫画集の出版を記念した作品展。画集に収録された作品も展示されている。女主人と三十分近く藤田のことを話しこんだ。「猫の絵をやろうとすると、藤田は避けては通れないのよ」と七十歳は過ぎているであろう、画廊の主人は笑いながら話してくれた。
伊東屋、プランタンを軽く物色してから、有楽町西武の『ヨウジヤマモト』へ。秋冬の新作を見る。今年のテーマは「ヒモ」。女に稼がせて、自分はのらりくらりと人生を愉しむ連中が表現されている。作品――商品とは呼びにくい――そのものはなかなかいいのだが、残念ながら今回はほしいと思ったものはナシ。店員の縣さんに、挨拶してから店を出る。彼とはかなり長いのだが、新宿丸井から有楽町西武へ転勤になってからはほとんど顔を出していないし買い物もしていないから心苦しいのだが、ほしくなかったのだから仕方ない。
夕食は土用の丑の日ということで、うな丼を自宅で。
舞城王太郎『阿修羅ガール』読了。少年犯罪、引きこもり、十代の性、女子高生の風俗と文化、などなど、現代日本の様々なゆがみを取り込んだこの作品、「社会への警鐘」なんて評価する人もいるかもしれないが、そうではない。作中でくり返し使われる「殺す」という単語がすべてを理解するためのキーワードのように思える。現代社会を生きるぼくらにとって、自分を殺すとはどういうことか。他人を殺すとはどういうことか。殺すことは罪なのか。罪には違いあるまいが、ひょっとしたらそれは、なにかのための第一歩としてとても重要な行為なのではないか。「殺す」を単純に「殺人」と捉えてはいけない。ぼくら人間は、ことばで人を殺すことができる。表現で人を殺すことができる。裏返せば、それは「ことばで人を救うことができる」「表現で人を救うことができる」ということなのではないか。無論、舞城はそんなことは一言も作中では書いていないし、そんなメッセージを作品に込めようとも思っていないはずだ。それでもぼくは「殺す」ということばにこだわってしまう。
最後のエピソードで、永観寺というお寺に納められた阿修羅像が登場する。それを彫った仏師である小山嘉崇は、かつては有名な悪ガキだったが仏像を彫ることで改心したという。その仏師がこだわりにこだわりぬいて作ったのが、その阿修羅像である。小山嘉崇は、何度も何度も阿修羅像を作っては壊し、納得が行くまでそれをくり返した。彼は阿修羅像にかつての自分を重ねていたらしい。阿修羅像を見た主人公アイコのモノローグを引用。
□ □ □
多分小山嘉崇は、そのときは、作った阿修羅像を壊すことに、自分の楽しみを見出してたんだと思う。
もちろん阿修羅像は自分だから、小山嘉崇はくり返しくり返しくり返し、自分を斧で割って殺していたんだろう。
自分を壊す、自分を殺すってのは、脊髄通して脳まで伝わるタイプの実際の痛みってものさえなかったら、結構皆のやりたがることなのだ。この世にいるのは自分のことが大好きな人間ばかりじゃない。そういう人が好きじゃない自分を壊して殺して新しい自分を求める。今の自分に物足りない、まだまだ自分は未熟だ、このままの自分じゃ駄目だと思う人間もたくさんいるから、そういう人たちも自分を壊して殺して、自分を壊した殺したという経験を経た新しい自分に期待をかける。あと、何となく今の自分の状況とか状態とかレベルとかいろんなものに関して、何とかしたいけどどうしていいかよく判んないし、このままなのがなんかむかついてイライラするし、でもやっぱりこのままの自分では解決策見つかんないし、つーか今の自分、解決策を探しているようにも思えない、グダグダしすぎ、でもいろいろ面倒臭い、あーいろいろうざい、なんて奴らも、痛い思いさえなければ、あとまあ、面倒臭くなければ、自分を壊して殺して新しい自分って奴にとりあえず任せてみたいと思ってる。人生リセット。そんなの都合良すぎ。でもそういうの求めてるダラダラした奴はこの世に多いし、まあ誰もが皆、そういう部分持ってる。
□ □ □
-----
七月二十八日(月)
「夢の知らせ」
学校なのか、会社なのか。よくわからん。小さな机がずらっと並んでいて、椅子もちゃんとひとつずつある。机だけ見ると学校みたいだが、そこにいる人たちはほとんどが大人のような気がする。部屋のなかはちょっとうす暗くて、ぼーっとしていると、その暗さについつい飲みこまれそうになる。ぼくはそんな場所にいた。隣に人がいる。女の子だ。もっと正確にいうと、モーニング娘。の安倍なつみだ。なっちはぼくの横でグダグダしている。何かいいたそうな顔をしているけれど、いいだせない。いいだせないから、彼女はとっても怒っている。ほっぺをふくらませる感じの、いつもの怒りかたとは全然ちがう。ウダウダしている。ウダウダしながら、イジイジしている。ウダウダしながら、イライラしている。そんななっちを見るのはぼくははじめてで、見てたらこっちまでイライラ、イライラ。なんだよ、いいたいことでもあるのかい、とぼくは投げやりな口調で、目線をそらしたまま話しかける。いいおわってから彼女の顔をちらりと見ると、アタマが縦にうごいていた。なにがいいたいんだいって、もう一度聞いてみる。今度はちゃんと、目を見て話した。なっちはなにも話してくれない。うーん、うーんと声にならない声を出しつづけている。なんだよ、こいつ。ここじゃ話しにくいの? ちょっと口調をやわらげて見ると、彼女はまたアタマを縦にうごかした。じゃあ、ここ出ようよ。彼女はだまってぼくについてくる。ぼくのうしろを、ついてくる。
スクラップ工場みたいなところに、なっちとぼくはやってくる。そこには大きな壊れたジャンボジェット機が一機、どすんと置いてある。翼の下側についていたはずのエンジンが、取り外されて、テーブルだかマガジンボードだか、よくわからないけど昔は家具だったような感じの木材のうえにこしかけたぼくら二人の目のまえに、無造作に、というか、適当な感じで、置いてある。エンジンの外側は細かいヒビでいっぱいだ。これ、ちゃんと動いていたのかな。ぼくはすこし心配になる。ぼくの横にはなっちが坐っている。なっちのことも、心配だ。いや、なっちのことのほうが、心配だ。飛行機なんか、どうでもいいや。なっちはまだ、なにも話してくれない。ここじゃ、話しにくいかな。
次にぼくら二人が行ったのは、ボロボロな店がまえのお好み焼き屋さん。鉄板が古くて、店のなかも古くて、油が壁に染みこんでいそうで、ちょっとベタベタした感じ。ぼくは熱くなった鉄板に、ゲロみたいなお好み焼きの具をドロドロドロって広げて、そのうえを、鉄のヘラでペッタンペタンと叩きつづける。叩きながら、横を見る。まだなっちは何も話してくれない。お好み焼き、楽しくないのかな。そうこうしているうちに、会う約束をしていたぼくのカミサンと、カミサンの友だちと、そのダンナさんが、お好み焼き屋さんにやって来る。ぼくらはバスに乗って移動する。どこに行こうとしているのかな。ぼくにはまるでわからない。気になるのは、なっちのこと。みんなといっしょじゃ、話しにくいかな。
というところで目が覚めた。あえていつもの日記と文体を変えているのだが、本当にこんな文体がよく似合うような、暢気でゆっくりした感じの夢だった。昨日は日曜、テレビ東京で『ハローモーニング』が放映される日なのだが、小川幸夫展と藤田嗣治の猫の絵展を見るために、番組はまったく見なかった。というよりも、ぼくはこの日、番組の存在をすっかり忘れていたのである。ああなっちの夢を見るとは、やはりオレはモーヲタなのだろうか。こっそり写真集でも買ってみよかな、などとくだらないことを考えながら身支度をし、朝食をとる。驚いたのは、そのときだ。フジテレビの『とくダネ!』で、なっちがモー娘。を来年春に卒業することを発表した、と報じているではないか。なんだよ、なっち。夢のなかに出てきたのは、そういうわけなのかい。
複雑な気分である。写真集どころか、初のソロシングルを買わなきゃダメかな、なんて考える。
九時、事務所へ。P社チラシ、J社PR誌、J社ソリューション商品のパンフレットなど。
駅の南側にある「欧風料理 華」で昼食。メダイのフライ。前菜のサラダはボリューム満点、おまけにスズキのカルパッチョが乗っている。フライは魚の味がしっかりしていて、揚げ具合もバッチリだ。手作りの特製タルタルソースがうまくて泣かせる。店の雰囲気も静かである。とても気に入った。また来ようと思う。
二十一時、帰宅。
小野正嗣『にぎやかな湾に背負われた船』を読みはじめる。この作者、どこぞの大学院でカリブ海の文学を研究しているらしい。クレオール文学ってヤツか。読んだことない。『にぎやかな湾に背負われた船』は三島賞受賞作で、筒井康隆が「ガルシア=マルケス+中上健次」と評したらしい。うーん、そうなのだろうか。まだ読みはじめだからよくわからない。文体は軽めである。語り手が女子中学生だからだろうか。
-----
七月二十九日(火)
「にぎやかな歯医者」
八時十五分起床。九時三十分、家を出る。歩いて四面道のそばにある並川歯科医院へ。先日歯にデンタルフロスをかけていたら右上の奥歯に糸が引っかかる感じがしたので念のため予約したのだが、案の定小さな穴が開いているとのことだった。レントゲンを撮って穴の大きさを確認してから、ドリルみたいな器具でギュインギュインと穴を広げ、そこになんだかよくわからないものをキュッキュと詰め込み、ギュインギュインと仕上げの研磨をして治療完了。と書くとトントン拍子に進んだようだが、実はそうでもない。穴は一番奥の歯とその隣の歯の隙間のあたりにできていたため、視認できず、なんだかよくわからないものを詰めるときもかなり難儀そうだった。並川先生は相変わらず治療しながらペラペラとおしゃべりをつづけている。それはぼくに向けてのときもあるし、自分の治療に対する独り言でもあるし、助手のおばちゃんへの文句でもある。素人落語をしているような人だから、口は達者だ。もちろん腕も確かである。並川先生ほど患者の歯の健康をしっかり考えている歯科医は、そう多くはいないと思う。
「ビストロさて」で昼食をとってから会社へ。J社PR誌の原稿、Pキャンペーンチラシのデザイン修正など。二十二時三十分、帰宅。
無風状態。西荻の町を包む湿った空気がその場でじっと静かにたたずんでいる。空を見上げてみるが、相変わらず星は見えない。東京の夜空に星を求めるほうが間違いなのはわかっているが、それでも見たいと強く思う。梅雨はいつまでつづくのだろうか。この日記を書いている今(翌日の零時十分くらいだ)、また雨が降りはじめている。雨音と、マンションの裏手を流れる川の音とが混じりあい、それが中途半端にメランコリックなメロディに聞えてしまって、少々イヤな気分になる。
小野正嗣『にぎやかな湾に背負われた船』。うーん。無理に純文学であろうとする態度が見え見えだなあ、なんて感じてしまった。
-----
七月三十日(水)
「さえずりのフライング/結膜炎と緑内障」
八時起床。鳥たちは二羽揃って元気よくさえずっている。とはいえセキセイインコのさえずりだから、高原の朝の小鳥たちよりはせわしなくて、騒々しくて品がない。ずいぶんとご機嫌なものだと思いながらリビングのカーテンを開けるが、空は晴れているわけではない。明るい朝の陽の光がうれしかったのではないとすれば、鳥たちはどんな気持ちで鳴いていたのだろう。テレビの天気予報は、明日で梅雨は明け、八月一日からはスイッチを切り替えたみたいな猛暑がつづくと報じている。鳥たちはそれを早々に見越していて、本能で梅雨明けを喜ぶさえずりをフライングしながら表現しているのかもしれない。
夕べはひどく目が痒くて、これはきっとカミサンが義母からもらったらっきょうの皮をリビングで延々数時間にわたって剥きつづけていたから、らっきょうの刺激臭というかエキスというかそんな感じのものに、あるいはらっきょうに付いていた泥が土ぼこりになって部屋に広まったせいではないか、などと勝手な推理をしていたのだが、朝になっても痒みはおさまらない。少々心配になったので近所の眼科――皇室の人間もお忍びで受診に来るという名医らしい――へ行ってみる。緑色の光を目玉に照射されたり空気を瞬間的に吹きかけられたり瞼をぐるりと裏返されたり蛍光色のよくわからん液体を目の中にチョイチョイと入れられたりスポイトで水のような液体をビョビョッと目玉にかけられたりリトマス試験紙みたいな紙を目玉と瞼の間に挟まれてそのまま五分くらい放置されたりした結果、ぼくの目玉は問題をたくさん抱えていることがわかった。まずひとつめは、アレルギー性結膜炎。これはだいたいわかっていた。結膜炎を患っている人間がコンタクトをするのはあまり好ましくないらしい。ソフトレンズの場合、アレルギー性物質がレンズのなかに入りこんでしまうらしいのだ。ハードレンズにするかワンデイのディスポーザブルにしたほうがよい、といわれた。といっても、今使っているのがワンデイタイプだからどうしたらいいのだと聞いてみたら、使ったらバンバン捨てろといわれた。どうしても、というとき以外はコンタクトをするな、ともいわれた。ふたつめの問題はドライアイ。普通の人間の三分の一くらいしか涙がでないらしい。ドライアイもコンタクトには不都合だ。こりゃ、今後コンタクトはいっさいしないようにしたほうがいいかな。そして最後の問題。眼圧が高いといわれた。最初はピンと来なかったのだが、どうやら眼圧が高くなると緑内障になるらしい。ぼくの目は緑内障にはなっていないが、将来そうなる可能性が高いのだそうだ。アレルギー性結膜炎の治療にはステロイド系の目薬が有効らしいのだが、これは眼圧を高める副作用があるらしく、ぼくに使うことはできない。市販の目薬の使用もやめたほうがいいといわれた。また、カフェインの過剰摂取も禁物らしい。今後、珈琲は一日一杯程度にしなければいかん、ということか。診察料は二千五百円くらい。それで緑内障のシグナルがわかったのだから、コイツは儲け物だ――などとも思ったが、ちゃかしたことばかり考えていたわけではない。緑内障というぼんやりとした恐怖に脅かされながら、ちょっと沈んだ気分で事務所へ向かう。
J社PR誌、P社チラシ、N不動産チラシなど。二十一時三十分、帰宅。
自宅に義母が来ていた。桃子をひき取りに来たのだ。毎朝しつこく起こされて困ったといったら、義母はケラケラと笑っていた。義母と桃子、二十三時ごろ帰宅。
小野正嗣『にぎやかな湾に背負われた船』。たしかに、ちょっとマルケスっぽくなってきたかな。
----
七月三十一日(木)
「止まってるなあ」
八時に起きるために、七時五十分に目覚まし時計をセットする。わが家の目覚ましは時間になるとベルの代わりに野鳥の鳴き声が鳴り響く。イカル、ホオジロ、クロツグミ、ウグイス、コルリ、ホトトギス、アカショウビンの七種類が収録されているが、ぼくのお気に入りはどれが鳴くかはお楽しみ、という「ランダム」モードだ。だがほとんど毎日、ぼくは野鳥の声より先に目が覚めてしまう。原因はいうまでもないだろう。花子である。五時前後にご飯を与えるために一度起きる。これで満足すればいいのに、たいていの場合、花子は七時過ぎになると寝室にやって来て、フニャフニャとなにかいいたそうだがはっきりしない、といった感じの鳴き声で延々と鳴きつづけてみたり、あるいはベッドからはみ出だし床に向かってだらりと垂れたぼくの腕を、突然小さな前歯で小さく噛んでみたりする。そうされるたびにぼくは目を覚まし、時計が何時を差しているのか確認する。こうなると、もう眠れない。ぼくに許されたことは、八時前に一度便所を済ませておくか、蒲団のなかでカウントダウンをつづけるか、割りきって早めに起きるかだ。
九時、事務所へ。風がない。空気が動いていないと、街全体が静止しているように思えるから不思議だ。自転車に追い抜かれたり、交差点で自動車が通りすぎるのを待ったりしているのだから、時間は動いているし、街もしっかり生きているのは確かなのだ。それでもぼくは、「止まってるなあ」と考えてしまう。それは梅雨が依然明けないからだろうか。
めずらしく、ぽっかりと穴が空いたような一日。事務処理以外、実作業がまったくないのである。動いている物件はすべて提出してしまった状態である。明日から動く物件もある。仕方ないので、得意先やスタッフに電話してみたり、本を読んだり、新聞を切り抜いたりして一日過ごすことにする。
「カフェ・ルーラル」で昼食。はじめて入る店だ。日替わりパスタを注文する。今日は小エビとナスのトマトソースだ。小エビはしっかりした旨味を感じたし、ナスは甘くて少々濃いめのトマトソースによくあった。食後は珈琲。眼圧が高いのでカフェインの摂取は控えろといわれているが、ついつい食後に頼んでしまう。この店は、珈琲もなかなか。喫茶店の、安心して愉しめる珈琲だ。
食後、「信愛書店」にて、イメージフォーラム編『タルコフスキー、大好き』など購入。
午後からも読書をつづけていたが 夕方になると飽きてしまう。昼時に購入したタルコフスキーの本を読んでいたら無性に映画が見たくなってしまう。というわけで、新宿へ。「HMV」でDVDを購入する。『惑星ソラリス』『ストーカー』の二本。『ノスタルジア』も欲しかったのだが、売ってなかった。「MYCITY」内の文具店や本屋をぶらついてから、紀伊国屋書店へ。一階にある輸入タバコと喫煙具の専門店で、マドラス型のハッカパイプを購入する。去年、ストレート型のものを購入したのだが、ハッカを容れる部分が壊れてしまっていたのだ。ガムを噛むか、ハッカパイプをくわえていないと仕事ができないようになってしまった。ヘヴィスモーカーがタバコをくわえていないと仕事ができないのとおなじだ。ただ、ぼくの場合はまわりにさほど迷惑をかけない。ハッカパイプは、外で吸うこともない。
十九時、店じまい。スーパーに寄ってから帰宅する。
家では延々とテレビを見つづけてリラックス。これから『惑星ソラリス』をすこしだけ観ようと思っている。
小野正嗣『にぎやかな湾に背負われた船』。語り手の少女のエピソードから脱線して、数十年前の「浦」の出来事の描写がつづく。過去の出来事は中上健次っぽい――というより、『千年の愉楽』っぽい?――というか、ラテンアメリカ文学っぽいというか。おもしろくなってきたのは確かである。
|