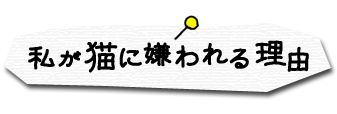|
二〇〇三年六月
-----
六月一日(日)
「今日の事件簿」
●保田圭復活事件
●三時間かかって原稿用紙一枚事件
●けいぞうの荷物が少なくなった事件
●三十路の誕生日会事件
●おせえよウッシー事件
●馬刺しとウナギ事件
●ワインを呑むと悪酔いするのよ事件
●台風一過、秋みたいに空が高く見えたよ事件
-----
六月二日(月)
「あまり仲良くしたくない」
宿酔いである。夜中、吐き気を感じて何度も何度も目が覚め、そのたびにウンウンと唸り、トイレに走り、吐き、口をゆすぐ。戻したあとは、しばらくの間理性が吹き飛んだような気分になる。胸と胃袋が逆流するたびに体力は消耗する。呼吸は荒くなり、アタマのなかは真っ白になる。眠ろうとするが、興奮してしまって眠れない。ところが、気づくと夢のなかにいるからふしぎだ。浅い眠りのなかで見る夢は、ほとんどが悪夢である。もちろん細部は覚えていない。毒素と化したアルコールは躯だけでなく精神までもむしばもうとする。朝、目が覚めると酒は友であるなどと信じていた自分が情けなくなってくる。酒とは仲良くしておきたいが、宿酔いと仲良くするのはまっぴら御免だ。目も合わせたくない。
九時、事務所へ。椅子に座ると重くなった胃袋が折れ曲がり、圧迫され、また吐き戻しそうになる。吐いたあと、鏡を見たら、なにも植えられずに放置された植木鉢のなかの、カラカラに干涸びた土みたいな色をしていた。インターネットで調べると、宿酔いにはシジミのみそ汁がよいとある。西友でカップのみそ汁を買い、それを昼食代わりにした。最低限の仕事だけをこなし、早めに帰って休むことにする。
アルコールの過量摂取で血液中にできたアルデヒドは、消えるまでに発生から二十四時間かかるらしい。陽が暮れたころにはかなり楽になったが、荒れた胃はそう簡単に恢復しない。夕食はおかゆと鶏のささみにした。
-----
六月三日(火)
「クルクルちょこまか」
九時半から銀座で打ち合わせがあるので、七時には起きなければならない。ところがぼくの躯はかなりマジメで几帳面にできているらしく、六時に目が覚めてしまった――五時には一度起きて、猫にご飯を与えているのだが。小便をしに起きるが、アルコール中毒の症状は消え去っているようだ。とはいえ胃袋はまだ重たい。腹のなかに、小学校の体育の時間に使った体操用のマットの生地でできたゴワゴワの袋が、わけのわからない物体をしこたま詰め込んだ状態で鎮座している。ほこりっぽい匂いのゲロが出そうな気がした。
八時すぎ、事務所へ。メールチェックとスケジュールの確認を済ませてから、有楽町へ向かう。ラッシュアワーの電車に乗るのは久しぶりで少々緊張したのだが、乗ってみるとなんということはない、ただちょっとばかし他人同士の躯の密着度が高くて、本を読みにくいというだけのことだ。女子大生らしい、グラビアアイドルみたいな目鼻立ちの美少女が隣に立っている。電車が停車しドアが開いて人の流れが生じるたびに、ぼくはクルクルと躯の向きを変え、女子大生もちょこまかと半径十数センチレベルで躯の位置を変えている。そのたびにかわいらしい横顔が見えて、ちょっとドキドキした。痴漢の気持ちがよくわかる。彼女は四谷で降りた。四谷を過ぎると車内はガラガラになったので、クルクルする必要もちょこまかする必要もなかった。これで安心して本が読める。
九時十五分、有楽町着。訪問するT社は銀座松屋の裏側あたりにある。歩いていくことにした。
九時三十分より打ちあわせ。三十分で終了した。すぐに帰社し、作業に取り掛かる。まずは資料の収集と読みこみだ。夕方、もうすこし資料がほしいと思ったので吉祥寺に出向き、街中をうろつく。少々疲れたと感じるのは宿酔い明けのせいか、それとも夏さながらの暑さのせいか。
二十一時、業務終了。帰宅する。
夕食はゴーヤチャンプル。少々弱った胃袋にゴーヤの苦味は効きそうな気がするが、実際のところはどうなのだろうか。カミサン、あまりつくりたくなさそうだったので、ぼくがゴーヤを刻み、豆腐を切り、鍋を振った。
奥泉光『『吾輩は猫である』殺人事件』。虞美人丸に忍びこむ名無し君とホームズ君。名無し君、阿片をなめすぎてトリップする。捕まえられた彼は、籠ごしに三毛子と再会する。三毛子は生きていた。しかも、今は寒月に飼われているのだという。ますます推理小説になってきた。オモシレエ。
嵐山光三郎の『死ぬための教養』もすこしだけ読む。期待していたほどおもしろくない。
-----
六月四日(水)虫歯の日
「健康噛むかむの教え」
虫歯の日だ。正確には虫歯予防デーだ。毎年、この時期になると行きつけの歯科医である並川先生からカレンダーをいただく。虫歯の日にちなんで六月はじまりになっている、世にも珍しい暦だ。B3サイズくらいだろうか。上部には「健康かむ噛むの教え」とある。これがこのカレンダーのタイトルだ。月ごとの日付の部分の横にならべるようにして、ご教訓が添えられたイラストが十二点描かれている。そのすべてが「健康かむ噛むの教え」なのだ。ある月は「三十回かむと消化にいい」とあり、またある月は「よく噛むときれいになる」とある。ほかの月は「精神が安定する」とあるし、「集中力が高まる」とある月もある。この教訓とイラストは毎年使い回されているようである。歯列矯正をお願いしていたときにこのカレンダーを見て、ぼくが「センセ、これオモロイですね」といったら先生、大喜びで、それ以来、毎年このカレンダーをくれるようになった。教訓はもちろんぼくの生活にはしっかり活かされていて、以来虫歯は一本も増えていない。食事もよく噛むようになった。このカレンダー、一家にひとつかならず飾るべきである。小学校などで配ればいいのにと本気で思う。今年のカレンダーは事務所の洗面所に貼っている。おかげで仕事中も歯の健康に気づかうようになった。
八時起床。曇り。窓を開けると湿っぽい空気がゆっくりと部屋のなかに染みこんできた。こいつは雨が降る前長だろうかと思ったが、天気予報では終日曇天とある。半信半疑ながらも、傘などというかさばる道具を持ち歩くのがイヤなので、天気予報は信じることにした。ところが、午後から雨が降りはじめた。天気予報より自分の勘のほうがアテになる、ということか。二十時三十分、帰宅。この時間になっても、まだ雨は降りつづけている。雨足は強くなったり弱くなったりを何度もくり返している。街行く人たちは傘をさしたり閉じたりで忙しい。ぼく同様、傘を持ち歩かなかった人も多いようで、雨足が強まりつつあるというのに、堂々と濡れながら家路を急いでいる。彼らの後ろ姿は意地を張っているように見えた。「悪いのは傘を忘れたわたしじゃございません、傘などいらぬと報じた天気予報に責任がある」とでもいいたそうな足取りだった。
奥泉光『『吾輩は猫である』殺人事件』。寒月、迷亭、三平、独仙の四人による麻雀。彼らの心理的やりとりが、オリジナルの『吾輩』のエピソードをうまく絡めていく形で物語として描写されている。名無し猫君は麻雀など見るのははじめてらしく、その観察力がとても新鮮。おもしろいなあ。純文学はつきつめると大衆文学に行きつく、とかなんとかいったのは、この作家ではなかったか。実践できているなあとつくづく思う。
-----
六月五日(木)
「猫の三角編隊/ねじれの位置の住人たち」
四時、猫三匹が一斉に「起きろ」とせがみだし、辟易しながら蒲団を抜け出すが、缶詰めを空けるより先に便所へ行くと、猫どもは自分たちの空腹解消が優先されなかったことをこころよく思わなかったようで、放尿し終えて半分寝ぼけていたものの、下半身の一部だけはすっきりした気持ちになっていたぼくに対して一斉に抗議をはじめた。愛読マンガである『エリア88』に、シン、ミッキー、フーバーの三人が、追い込まれた味方の新人パイロットであるマリオを助けるために、イスラエル製の戦闘機クフィールC2で三角編隊を組んで敵に突っ込んでいき、三十ミリ砲三門の一斉射撃で敵機のミグを撃墜するシーンがあるが、このときの猫たちにはまさにこの戦闘機の編隊さながらの勇ましさとチームワークのバランスを感じてしまう。ニャーの一斉射撃を受けたぼくはおとなしく缶詰めを空けた。肩をならべてムゴムゴとご飯を食べているところまで三角編隊みたいに見えた。妙におかしかった。
八時に目覚ましをかけたつもりが忘れていたらしく、目が覚めたのは八時十五分、あわや大寝坊の大惨事となりかねなかったが、最近はどういうわけか眠りが浅いようだから、うっかり寝すごしそうになっても、この程度の失態で済んでしまう。十五分遅れて事務所へ行く。一時間変ると駅までの道の様子はまるで違ってみえるのだが、十五分程度ではさしたる変化はない。いや、変化はあるがあまりに微妙すぎて、浅い眠りをひきずって六分の一くらいは寝ぼけたままでいるぼくの感覚では読み取れないのかもしれない。
午前中は資料の読み込みなど。午後より外出。十三時から十四時まで、吉祥寺の街でPOPの観察。十四時からカイロプラクティック。十五時終了。十五時三十分、新宿駅でL社のNさんと合流。移動しながら打ち合わせする。十六時、大崎にあるアミューズメント企業E社へ。POPツールの打ち合わせ。本件は今日からの参加となる。よくわからないままの出席だったが、ぼそっとその場でつぶやいたコピーがそのまま採用になったのはうれしいことだ。十九時、終了。その足でゲートシティ大崎に寄る。アトリウムやプラザをすこしだけぶらついて店頭観察。書店で奥泉光『ノヴァーリスの引用』、『ダカーポ』を購入してから帰社する。帰社後は残務整理。二十一時、帰宅。
夜、ドラマ『動物のお医者さん』を観る。つづいて『ダウンタウンDX』。的場浩司が目撃している謎の生命体「ゴム男」、石坂浩二も遭遇しているらしい。名前がおなじ「コウジ」だからだろうか、などとばかばかしいことを考える。石坂氏、世の中にはニンゲンには普段わからない時間と空間というものがあって、そこに住む存在がゴム男なんだとかいう持論を熱く語っている。残念ながらぼくはゴム男に遭遇したことはないが、時間と空間の話は実感はないものの妙に納得してしまった。どうやらゴム男に遭遇した人は、このふたりだけではないらしい。全国各地に存在している。ゴム男は、いわば「ねじれの位置」みたいな、ぼくらが存在する三次元とごく近い次元に住む存在なのだろう。それが、なにかの拍子でふと目にとびこんでくるのかもしれない。気になったのでカミサンとネットで検索してみたが、ゴム男に関する情報はほとんどなかった。内閣調査室とか陸幕二部とかJETROとかが情報操作しているのかもしれない。あ。JETROは貿易関連だから関係ないかな。
奥泉光『『吾輩は猫である』殺人事件』。迷亭たちは麻薬密輸団だった?
-----
六月六日(木)ドラえもんの絵描き唄の日
「うるせえ/まぶしいホームレス」
ドラえもんの絵描き唄の日である。「ろくがつむいかに ゆーふぉーが あっちいってこっちいって おっこちて」の日である。しかし残念ながら未確認飛行物体の目撃報告や墜落事件はなかったようだ。
八時起床。ここ数日、八時になると桃子がぼくを起こしてくれる。花子もベッドのそばまで来ているようだが、桃子がいるのが気に入らないのだろうか、こちらをじっと見ているだけで、ぼくを起こそうとはしないのだが、桃子はそんな花子のおとなしいのか、なにかたくらんでいるのかわからないようなそぶりなどまるで気にせず、ニャンニャンと鳴きわめき散らし、蒲団のうえに乗り、ぼくをひっぱたいたり噛みついたりする。花子の起こしかたは時に痛みや不快感を伴うが、桃子の場合は鬱陶しくはあるものの、痛くはないので助かる。そして桃子は、カミサンの枕のうえに、取りたてのフグの白子みたいな太い腹を、なんの恥じらいもなくどーんと載せて横たわっている麦次郎と目が合うと、突然フーッと威嚇の声を漏らし、攻撃態勢にはいり、ムギに一発、きつい猫パンチを御見舞いして逃亡するのだ。このときばかりは、ぼくもさすがに気分を害する。うるせえ。
九時、事務所へ。午前中は急に動き出した諸物件の資料整理。午後から新宿御苑前のデザイン事務所、B社へ。O社PR誌制作のまえのご挨拶だ。御苑前駅から靖国通りのほうへ向かってタラタラと、中途半端に盛り場の匂いをふりまく街並みを見ながら歩いてみる。昼間はふつうの街のように見えなくもないが、ときたますれ違う人たちの服が妙に露出度が高かったり、金色の装飾が多かったりするのを見ると、やはりここは夜の街なのだなあとつくづく思う。
左手に公園があった。学生らしい集団がバレーボールをして遊んでいる。ゲームではなく、ただのトスごっこだ。そのすぐ横では、クタクタのサラリーマンらしい人物がベンチに寝そべってぐーすかと昼寝を決めこんでいる。リストラされたが家族にその事実を伝えることができず、毎日とりあえず通勤するフリをつづける仮面サラリーマンかもしれない。
公園の中央部にある桜の木の根もとには、ダンボールを寝床にしている人たちが数名、午後のひとときを優雅にたのしんでいた。見てくれは優雅ではないかもしれないが、表情が優雅だ。誰かがなにかをいうたびに、一同はがさつに笑っているが、それがなぜかぼくには優雅に思えて仕方がないのである。優雅というより、贅沢といったほうがいいかもしれない。昼間から仕事に追われることもなく、公園でゆっくりすごせるとは。これこそ贅沢だ。
水色のタンクトップにショートパンツを履いた茶髪の女性が見える。彼女もホームレスなのだろうか。それとも、ホームレスと親しい一般人だろうか。ショートパンツから、ときおり真っ赤なパンツが見え隠れしていた。やはり水商売の人なのだろうか。太股は太い。健康的できれいな足だ。
隣の土地と公園を仕切るアルミニウムの柵に、ビニール傘がおよそ三十本、ふつうの洋傘が十本くらい、ずらりと雨の日の銀行の傘立てみたいに並べてあるのを見つけた。そのすぐ横にダンボールハウスが建てられている。これだけ傘があるということは、このハウスの所有者は水に濡れることを極端に嫌っているのだろうか。ダンボールは青いビニールシートでしっかり防水対策がなされているようだ。ビニールはときおり雲の切れ目ができるたびに、中途半端に注がれる午後の陽の光を、中途半端に照らしかえしている。ビニールのほか、陽の光を反射するようなものはこのダンボールハウスにしかなく、光も弱々しかったというのに、公園はなぜかまぶしく見えた。
打ちあわせ後、靖国通りを歩いて新宿駅方面へ。紀伊国屋書店に寄り、仕事の資料を一冊購入する。ついでにトイレに入って大便。ウォシュレットがあれば、と思う。
夕方、小石川のL社へ。アミューズメント企業E社のPOPとパンフレットのコピーに関する打ちあわせ。かなりのボリュームだ。
十九時三十分、帰社。先日構成案とスローガンだけ考えたB社のPR誌、制作が決定したという連絡が入る。原稿、月曜までに書けといわれる。きついなあ。夜中まで時間をいただくことにした。二十一時、終了。
夕食は焼き肉屋で。六千円くらい飲み食いしたが、スタンプカードがいっぱいになったので二千円の支払で済んだ。領収証は六千円分もらった。
奥泉光『『吾輩は猫である』殺人事件』。虎君と猫君による、麻薬シンジケートの偵察。どうやら越智東風と泥棒君は知りあいだったようだ。
-----
六月七日(土)
「固くなってきた」
九時起床。今日も桃子に起こされた。
十時三十分、事務所へ。E社POPのコピー、B社PR誌の原稿などに取りかかる。
十三時、それいゆにて昼食。帰りに書店に寄り、『群像』七月号を購入。
夕方、近所のマッサージ『プラスドルポ』へ。院長に、躯が固くなってるよといわれた。やはり運動不足か。ジョギングでもしようかと本気で考える。
二十一時、帰宅。
奥泉光『吾輩は猫である』殺人事件』。猫救出作戦はまだまだつづく。
-----
六月八日(日)
「ココロの強い生き物」
六時、桃子に起こされる。七時、桃子に起こされる。八時、桃子に起こされる。九時、桃子に起こされる。腹が立ってくる。十時、花子に起こされる。起床。
桃子を一週間以上預かっていたが、今日でおしまいである。あいにく仕事ゆえに桃子を見送ることはできない。出かけるまえに玄関先でバイバイと何度も話しかけてみたが、わかっているのか、いないのか。
十一時、事務所へ。E社パンフレット、B社PR誌など。資料がほしいと思い午後から吉祥寺へ行ってみるが、あいにく目ぼしいものがまるで見つからず、未収穫で帰社する。十八時、業務終了。自宅で使っていた椅子が猫にツメ研ぎされてボロボロなので、事務所で使っていないままになっていた事務用チェアをひとつもって帰ることにする。椅子なんてたいした重さではないだろうと高をくくっていたが、ところがどっこい、これが意外に重く、担いで歩くのは少々難儀だった。背もたれの部分を肩にのせ、キャスターを前方向に向けてもつと、かなり楽なことに気づく。何度かのせる肩を代えながら、ゆっくり歩いて帰宅する。今日は真夏日の地域もあったらしく、力仕事には少々不向きな天気と気温だ。背中全体に、じっとりと汗がにじみ、たまり、すこしずつ下へと流れおちるような感覚が不快でイライラしてくる。
家に帰ると、桃子はもう帰ったあとだった。義父母が昼間にお迎えにきたらしい。桃子は自宅へ帰ると、家中をクンクンと嗅ぎ回り、どうして麦次郎や花子がここにいないのかと不審がり、しばらくの間にゃんにゃんと、ウチの猫たちを呼んでいるかのような声音で鳴きつづけたらしい。ところがわが家は平穏そのもので、花子など、これでようやく落ちついて眠れるといわんばかりの表情で、リビングのカーペットのうえで気持ちよさそうにうたた寝している。麦次郎は、一瞬桃子のことを思い出したのか、大きな声で鳴きちらしていたようだが、それもすぐに止めてしまい、和室でグースカと眠っている。二匹とも、桃子の登場によって壊れてしまった自分たちの生活のリズムを、睡眠によって取りもどそうとしているのかもしれない。あまりさみしくはないようだ。さみしいと感じているのは、ニンゲンだけのようである。猫とはココロの強い生き物だ。
奥泉光『『吾輩は猫である』殺人事件』。時間跳躍実験。SFのエッセンスまで導入しはじめた。名無し君はタイム・リープの能力があるらしい。さて、この先どうなっちゃうんだろ。あと五十ページくらいかなあ。
-----
六月九日(月)
「『『吾輩は猫である』殺人事件』読了事件/紫陽花の毒/中央線らしい飲み屋さん」
夕べは日記を書き終えたあとにもう一度『『吾輩は猫である』殺人事件』を読みはじめてしまい、結局読了してしまった。
特筆すべきは漱石の模倣文体であるが、模倣しただけではこの作品を純文学のカテゴリーと見なすことはできないと思う。小説とは虚構がもつ力を、ことばによって最大限に引き出す芸術だとぼくは思うのだが、この作品はまさにこの考えを具現化してくれている。推理小説のスタイルとSFの技法を巧みに取り入れることで、猫のエンドレスロマンスというふしぎだが魅力的な物語が生み出された。これは、ただひたすらに自然をつづり、世界をつづり、生老病死をつづり、愛をつづることで人間の核心に迫ろうとする従来の純文学の方向性とは大きく異なるものではあるが、やはり純文学作品であることに間違いはない。なぜなら、推理小説、SFといった技法をバックグラウンドとしつつも、奥泉氏はあきらかに名無し君の視点から、人間の本質に、世界の構造に、認識と存在の秘密に触れ、深遠なるその謎に挑戦しようとしているのが、随所で読みとれるからだ。奥泉氏をはじめ、村上春樹、高橋源一郎、笙野頼子などの登場により、純文学と大衆文学の境界線は、二十世紀末から急にあやふやなものになりはじめている。だが、やはりまだ境界線は存在する。今後はこの境界線を利用することで独自性を獲得する手法が、続々と登場するはずだ。
八時起床。目覚めの放尿、と思いトイレへ急ぐと、花子も後ろからついてきて、ドアを開ける直前にサササッとぼくを追い越し、先にトイレへ躯を滑りこませるように入りこんでくる。猫に先を越されたからといって、彼らの生理現象が終わるまでトイレを我慢するほどぼくは甘くない。ドアを閉め、花子と連れションを決めこんだ。ぼくのほうが、放尿時間は長かった。花子は尿を出す時間よりも、砂をかく時間のほうが長くなる傾向があって、ぼくが用を足し終えてズボンを引き上げ、水を流し、手を洗ってドアを開けて出ていこうとしても、まだカショリカショリと砂をかいて、自分のしっこを隠そうとしている。本能なのか、神経質なのか。
九時、事務所へ。近所のマンションの垣根に植えられたツツジの花が、すっかり枯れてしまっていた。しなびて茶色く変色したあわれな花びらの姿が少々痛々しく見える。マンションのすぐ横にある小さな一戸建ての庭先には紫陽花が植えられていて、こちらは半分くらいがつぼみを開き、碁盤の升目四つ分とでもいおうか、そんな形にならぶ紫色をした、ちょっとティアドロップを思わせるような丸みを帯びた正方形四枚が広がる花々を、通り過ぎる人々に見せびらかしつづけている。まだ花開かないつぼみの部分は、じっと見ていると菜の花かブロッコリーのように思えてきて、茹でて喰ったら美味いだろうかと想像したが、紫陽花の花には毒があると小学生のころ誰かに聞いたことがあったようなないような、曖昧な記憶がふと蘇り、ちょっとだけおそろしくなって唾をごくりと飲みこんだ。濃く茂る葉を何枚か触ってみる。ひどくごわごわした感触で、ああ、これなら毒があってもおかしくないかもしれんとひとりで合点してしまった。ほんとうに毒などあるのだろうか。調べる気はさらさらないのだが、気にはなる。
B社PR誌、E社カタログのコピーに専念する。
十三時、昼食。沖縄そばが食べられる店があると聞いたので、そこへひとりで行ってみた。「居酒ック 馬小(うまぐわ)」というおかしな名前で、大田垣晴子がときどき顔を出している飲み屋だ。店先にあった看板には「沖縄すば」と表記されていた。あちらの方言だろうか。スナックばかりが入居している「飲み屋ビル」の奥ばったところにその店はあった。飲み屋だから、昼間は薄暗い。味に期待しつつもちょっとドキドキした心持ちで店内に入ると、眼鏡に無精髭、ちょんまげヘアのオヤジがテーブルで新聞を読んでいる。ちわ、と挨拶しながら店に入るぼくの姿を見ると、オヤジはあわててカウンターに戻り、いらっしゃいませと挨拶しかえす。店内も暗い。そして汚い。延々と沖縄民謡が流れつづけているが、よく聞くと子どもの話し声や拍手、歓声、大人の世間話などがところどころで聞こえてくるから、これはおそらくどこぞのコンサート会場か宴会場で収録したまんまの、未編集の音源なのだろう。こういうものをBGMにしてしまうとは、すごい感性と神経だ。この音楽は嫌いではない。むしろ、おもしろさを感じるし心地よくもある。あちこちに鉄腕アトムなどの昭和三十年代を思わせるアンティークなおもちゃが所狭しと並べられているのも、いかにも中央線沿線の飲み屋らしくていい雰囲気だ。壁には沖縄に関係した印刷物などが、ベタベタと貼られていた。競馬に関するものもあるようだが、ぼくはウマはやらないのでよくわからん。注文もせずきょろきょろしつづけているのも変なので、ラフテーすばを頼んだ。するとオヤジ、いきなり親しげな口調でぼくに「あんた、この辺なの?」と聞いてくる。そうだと答えると、「生まれも?」とさらにつっこんだ質問をする。生まれは違うと答えると、オヤジは無精髭で埋まった顔にちょっとだけ笑みを浮かべながら、自分は西荻で生まれて西荻で育ったと、自慢するように語ってくれた。オヤジは、この店は早稲田の学生と慶応の学生がいるとしたら、早稲田のヤツしか来ないような店だと誇らしげにいい、つづけて、多摩美と武蔵美だったら、武蔵美のヤツしか来ないとも行った。この店のことは大田垣晴子の本で知ったことを伝えると、オヤジは料理をつくりながら、うれしそうな声音で「セイコのヤツはねぇ」と話しはじめる。アンタ、セイコのこと知ってるのかと聞くので、いや本を読んだだけだと答える。職業を聞かれたので近所に事務所かまえて三文コピーライターをやっとるというと、このあたりは変った職業の変ったヤツがおおいからねえ、と、またまたうれしそうに話している。話し好きな人だ。ラフテーすばは美味だった。そばの味がしっかりしている。ラフテーは柔らかすぎないほどよい歯ごたえと甘すぎないがしっかりした味付けで、素朴だがとても好感がもてる。あっという間に平らげ、勘定を払うと、今度は夜においでよ、おもしろいヤツ紹介してやるよといってくれた。泡盛は大好きなので、ぜひ、と答えた。ただね、カミサンが飲まないから、ひとりで来ると怒られるんだ、というと、オヤジはたのしそうに苦笑した。いい人だ、と思った。酒もうまそうだ。
午後もB社、E社。二十一時、帰宅。
帰宅後、金井美恵子の『柔らかい土をふんで、』を読みはじめる。「柔らかい土をふんで、」ではじまる小説だ。相変わらずひとつのセンテンスが以上に長い。以前読んだ『彼女(たち)について私の知っている二、三の事柄』よりも文体は硬調で、ひとつひとつのことばが研ぎ澄まされている。そのせいだろうか、文章がワンカットで長く、丁寧に対象を追いつづける映画の一シーンのように思えてくる。散文詩みたいだな、とも感じた。男女のしがらみを描いた作品みたいだが、まだ全然よくわからん。
-----
六月十日(火)
「濁音の多い名前と匂い」
八時、花子に起こされる。先週は目覚めても骨のなかまで疲労しているような気だるさがとれなかったが、今朝は意外にすっきりしていて、躯もしっかり、きびきびと動く。天気の影響もあるのだろうかと、軽いアレルギー性結膜炎でほんのすこしだけかゆみを帯びた目をこすりながらカーテンを開けてみるが、一軒はさんだ東側にあるマンションの屋根のうえに広がっているのは、相変わらずのグレイ・スカイ、厚いんだか薄いんだかよくわからない雲ばかりが狭っくるしい東京の空を、曖昧な感じで包んでいる。爽やかな朝からはほど遠い。しかし、ぷちぷちが所狭しと籠のなかをうろつき、威勢よくギョギョギョと鳴きちらしているところから察するに、今朝の空模様は、決して本能的に不快なものではないようだ。
九時、事務所へ。昨日は紫陽花ばかりに気をとられていたような気がするが、ほかにも季節の花はないのだろうかと、一戸建てがあるたびに庭先を覗いてみたり、マンションがあるたびに植え込みを観察してみたりするが、心奪われるような花は見当たらない。ドクダミの白い花が群れになって咲いているのを見つけた。濁音の多い名前の音感と、鼻を近づけたときの強烈な匂いのせいでこの花はずいぶん損をしているようだが、ちょっとおしべとめしべが大きめの白い花は意外に可憐でかわいらしい。はてこの花は初夏に咲くのだったろうかと、乏しい植物知識を掘りかえすようにして思い出してみるが、これがさっぱりわからない。一年中咲いているような気がしなくもないが、実際はどうなのだろう。
今日も引きつづき、B社PR誌とE社カタログ。昼休みに、銀行で源泉税の支払った。昼食は万豚記で「功夫坦々麺」なるものを食べる。中華系のスパイスが効いた、辛味たっぷりの坦々麺だ。食べ終わったあと、やたらに喉がかわいた。
午後から義母が事務所に来る。雑務担当だ。義母は空いた時間でパソコンの勉強をしていた。インターネットに興味津々らしい。
十七時、五反田にあるE社の別室へ。カタログ制作の打ちあわせ。キャッチフレーズの受けは上々なのだが、ボディが弱いと指摘される。精進せねば。二十時帰社。
夜は指摘を受けたボディコピーの修正。午前0時、帰宅。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』を読み進める。映画的、映像的な作品だと思った。物語はゆるやかに、拡散する霧みたいに進展していく。でも、ひとつひとつの表現は研ぎ澄まされていて、うっかりしていると描写の迷路に引き込まれ、自我を失ってしまいそうになる。アタマがクラクラする小説だ。
-----
六月十一日(水)
「色彩美本能」
0時過ぎまで仕事をするのは久しぶりで、躯がぶっとおしで働くことに軽い拒絶反応でも起こしているのだろうか、六時間は確実に寝たというのに、一日中眠気がとれず、重たいまぶたに力を込めながら、あれやこれやと仕事をこなすハメになる。八時に起きることはできなかった。いったん目覚めはしたのだが、脳みそのエンジンがかからず、このまま眠っていたほうがいいのではないかという本能的な判断、というより欲求といったほうが正確だろうが、その判断だか欲求だか、単純にいえば「もう少し寝たい」という思いに、あっさり負けて三十分ほど寝坊した。
九時三十分、事務所へ。事務所のビルのオートロックを解錠し、外廊下へつづく階段をとぼとぼと昇っていく。道に面した踊り場から、向かいにある立派だが少々古ぼけた一戸建て――『サザエさん』の家みたいに、アルミでなく、木でつくられた雨戸がある――の庭をなんとはなしに覗いてみると、奥のほうで、紫陽花がひっそりと咲きほころんでいた。つぼみも多い。ほんのりと緑がかったクリーム色をした、ふしぎな暖かさを感じさせる紫陽花のつぼみは、花開きはじめると、すこしずつ色づいていくようだ。この家の庭に咲く紫陽花は、庭の土質のせいなのだろうか、赤味が強くて、鮮やかというよりあでやかと表現したほうが似合う色をしている。クリーム色から赤紫へ至るグラデーションと、生命力に溢れた葉の濃緑色のコントラストに、ほんのすこしだけ目を奪われてしまった。人間には自然よりも美しい色彩など作り出すことはできない――そんなことを考えた。できないからこそ、人は芸術、絵画という形で、自然の美に挑戦しつづけているのかもしれぬ。これも本能なのだろうか。闘争本能や母性本能があるなら、色彩美本能があってもいいと思う。
十七時、大崎にあるE社へ。カタログ打ちあわせ。終了後、L社のNさんと新宿にあるデザイン事務所、Z社へ。カタログのスタッフミーティング。二十時三十分、帰社。「わしや」で処分価格になっていた日替わり弁当を購入し、腹ごしらえしてから、カタログの原稿にまたまた取り組む。二十三時過ぎ、眠いので帰る。この日記を書いているのは午前一時。眠い。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』まったくおなじ文章からなる描写のくり返しが、随所に現れる。くり返されるイメージは、前衛的な映画の手法にも似ている。
-----
六月十二日(木)
「紫陽花と腰痛の比較論」
八時起床。入梅して三日くらいは過ぎたのだろうか。目覚めたら外は雨だった。鉄筋コンクリートに足元も左右の壁も天井も囲まれ、唯一外が覗ける窓も格子状に組まれた細い針金が入った分厚いガラスで塞がれているマンション住まいでは、雨音はほとんど聞こえず、雨の気配などほとんど伝わってこない。カーテンを開けたときに、ようやく気づくような有り様なのだが、躯のほうは本能的に雨であることを察知していたらしく、腰痛が急に激しくなっていた。腰の痛みは天気に左右される。空が荒れると離陸できない飛行機、海が荒れると出港できない船みたいだとひとりで納得しながら、テレビをつけ、画面の左うえに表示されている天気予報と、窓の外とを交互に見た。空気がひどく湿っているな、と感じた。
九時、事務所へ。右手で鞄をもち、左手で傘をさしてとぼとぼと歩く。雨は静かに降っていた。小雨といおうか、霧雨といおうか。雨音はまるで聞こえない。空気のなかに小さな小さな雨滴が拡散して、傘や鞄や躯にまとわりついてくる。雨の微粒子は紫陽花の花を鮮やかに見せる。ほんのすこしだけ、目を奪われた。紫陽花には腰痛などないのだろうと考える。しかし、紫陽花の花は夏を迎えるころには枯れてしまう。これは腰痛よりつらいことなのかもしれん、などと考えたが、花の命と腰痛を比べること自体、なんだか変だ。すぐに考えるのをやめ、再び歩きはじめる。雨はまだ、静かに降りつづけている。
E社カタログのコピー修正、B社PR誌の微調整など。久しぶりにデスクにぞうきんをかけた。ぞうきんがけをしている間、雨は止んでいるように見えた。掃除の手を休め、ローズマリーやレモングラス、スペアミントなどのプランターを無造作に置いたベランダに出て、外に向かって手を伸ばし、ほんとうにやんだか確認してみる。空を仰ぐ。一瞬、晴れ間が見えた。朝からの小雨に濡れた道路は陽の光を照らしかえしたまぶしく輝いた。二、三秒はつづいただろうか。つぎの刹那には、陽光などどこかに消えてしまい。また空は雲に覆われてしまった。夕方になると、雨はまた降りだしたようだった。またベランダに出て、手を伸ばしてみる。ほんのすこしだけ、手が濡れた。雨は弱々しく降っている。
十九時三十分、早めの店じまい。雨は止んでいたので、ただの荷物となってしまった傘が邪魔に感じてしまう。スーパーでビールを九本買って帰った。雨が降っていたら、買わなかったと思う。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』。いかようにも解釈できる描写ばかりがつづく。シーンとしての具体性はあるし、登場人物もある程度明確になってはいるのだが、すこし読み進めると、自分がもっていたイメージはたちまちことばの波のなかに埋没してしまい、新たなイメージが浮かび上がる。そのイメージは今まで抱いていたものとほとんど変らないのだが、ほんのちょっとだけ、濃くなっている。これまでにない小説のかたちかもしれない。
-----
六月十三日(金)
「ラジカセ分解記」
この妙にぬるまったく躯にまとわりつくような重さと湿り気のある空気は、日本中を覆いつくしているのだろうか。いや、北海道には梅雨はないというから、本州、四国、九州、沖縄をすっぽりと包んでいるのだろうか。朝、目覚めると躯がすこしべたついた感じがするのは、この湿った空気のせいか、それとも熱くて寝汗をかいただけなのか。八時起床。いつもより念入りに顔を洗ってしまう。
九時、事務所へ。重たい空気は紫陽花の花のまわりだけは避けているように見えなくもない。顔を近づけると、どんな感じなのだろう。ほどよく乾き、ほどよく湿った美しい風が、わざとらしいほどに爽やかな色合いの花びらをそっとなでているのだろうか。そんなはずはない。花の香りは愉しめるだろうが、空気はきっとおなじ、重くよどんでいるはずだ。紫陽花に梅雨の空気の清浄作用などあるわけもなく、そんな夢想をすること自体、間違ったことなのだ。しかし、そう考えるとすこしさみしい木がしなくもない。人は、梅雨時の紫陽花には自然と心魅かれてしまうものらしい。
事務所のフローリングまで湿った感じで、愛用するクイックルワイパーの滑りが異様に悪い。窓を開けても室内のよどんだ空気は外に逃げず、仕方ないのでエアコンのスイッチを入れ、ドライモードで運転した。扇風機を回して空気を撹拌すると、ようやくまともに仕事ができそうな環境になってきた。これが一ヶ月もつづくかと思うと、湿った空気とおなじくらいに気持ちが重くなる。
B社PR誌のコラム原稿。朝一番で、代理店から社長のトークを録音したテープが届く。これを聞いて、内容をまとめて、読者が読みたいと思うようなかたちの原稿にまとめなければならない。いつもは自分が取材して、録音したものをちょこちょこと聞きながら原稿を書くので、今回はちょっと勝手が違う。そもそも、テープという点が少々困りものだ。独立してからというもの、テープで取材を録音したことがないのだ。最初のうちはMDを使った。こちらのほうが劣化の心配がなく、しかもコンパクトで持ち運びにも便利だからだ。今年からは、ICレコーダを愛用している。WMP形式でパソコンに保存できるのが最大の強みだ。メディアを保管しておく必要がないのである。したがって、ぼくは取材用のテレコなどもっていなかったので、再生をどうするかが問題になった。しかたがない。普段、モーツァルトや村治香織やマイルス・デイビスやキース・ジャレットや坂本龍一やロバート・フリップやデヴィッド・シルヴィアンのインスト作品などをBGMとして再生するのに使っているソニーのCDラジカセを使うことにする。このラジカセ、購入してから四年経つが、テープを再生するのは実ははじめてだ。だいじょぶかな、とすこしだけ不安を感じながら、テープを挿入してみる。よし、入った。巻き戻しボタンを押す。キュルキュルというテープの回転音が聞こえ、やがて自動停止した。最初まで巻きもどったらしい。ヘッドホンをかぶり、パソコンのキーボードに手を置いた状態で再生ボタンを押す。音が聞こえるのを待つ。しかし、何も聞こえない。あれ、と訝しみ、カセットの動作状況が見える小窓からなかを覗いてみると、カセットは空回りをしているではないか。慌てて停止ボタンを押す。テープが切れたか? 冷や汗を流しながら、イジェクトボタンを押す。出ない。カセットが出てこない。あちこちいじってみるが、やはり出てこない。まいった。故障だ。どうするか。原稿の締切は月曜の朝だ。ということは、今日中か、あるいは土日に原稿を書ききらなければいけない。しかし、テープがこの状態では、書きようがない。メーカーに電話するか? いや、そんなことをしたら、テープとラジカセが戻ってくるのは早くても一週間はかかる。間に合わない。どうする? 思いついた対処法は、ひとつしかなかった。自分で分解してテープを取りだし、別のテレコを調達して、それを使って再生することだ。
十一時三十分、吉祥寺へ。ドライバーとテレコを購入する。テレコはソニー製で、消費税込みで四千円。倍速および二分の一倍速で再生ができる、ライターご用達の商品だ。二十分で昼食を済ませ、午後からラジカセの分解に取りかかる。外側から見えるねじを全部はずし、筐体をばらすとなかからつぶつぶしたよくわからんチップだかコンデンサだかがいっぱいの基盤とスピーカの裏側、そしてカセットテープの収納されたユニットが現れた。なんだこりゃ。基盤は何度か見たことがあるが、これを通じて音が再生されるということが、どうしてもイメージできない。理解できない。この基盤にぷちぷちとくっついたチマチマがひとつでも欠けたら、きっと音はでなくなるのだろう。電気工学だか電子工学だかしらんが、すげえなあと感心するが、今はそんな悠長なことをしている場合ではない。基盤をとめるねじもはずし、基盤を傷つけないように気を配りながら、カセット部を取りはずす。この状態でイジェクトボタンを押してみたが――イジェクトは電動ではなく、ばねをつかって一回押すとロック、もう一度押すとロック解除という方式だった――、テープはやはり出てこない。しばらくあれこれつっついてみたり、ばらせそうな場所を探してみるが、埒があかない。アタマに来たので、裏側からドライバーを差しこみ、てこの原理でグイとねじ開けたら、スポリとテープが飛びだした。確認してみる。大丈夫、テープは切れてもいない。よれてもいない。買ってきたテレコで再生してみると、ちゃんと社長の声が聞こえた。安心だ。このまま分解したラジカセを放っておいて先に原稿をまとめてしまおうかと考えたが、ばらしたラジカセが無残だったので、組み立ててやることにする。ここまで、所要時間二時間。とんでもないタイムロス。本日より、このラジカセのテープ再生は禁止にした。取り出し口部分を、セロテープでふさいでしまった。
大慌てでテープ起こしをする。案の定、話はまとまっていないので、エッセンスを整理し、構成を考え、ぶれるテーマを固めてやり、補足し、読み物のかたちに仕上げてやる。この作業が一時間。なんか釈然としない。
十七時、五反田へ。E社POPカタログの打ちあわせ。十九時終了。ひきつづき、近所のフレッシュネスバーガーで御茶をしながらL社のNさんと打ちあわせ。Lさん、途中でE社に戻る。そのあいだ、ぼくは打ちあわせで決まったことをまとめ、鞄にいれておいたシグマリオンを使ってコピーを書きはじめる。モバイルコピーライターだ。二十時過ぎ、戻ってきたNさんといっしょに新宿のデザイン事務所へ。修正についての打ちあわせ。二十一時、西荻着。桂花飯店で夕食をとってから、事務所へ。E社コピーを仕上げる。つづいてB社のコラムも仕上げる。0時、帰宅。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』。ミッションを遂行するスパイの話。
-----
六月十四日(土)
「ブラジャーの装着感/熟成する綿素材」
九時三十分起床。いつもの土曜日とおなじように、テレビのスイッチを入れ、渡辺篤史の『建もの探訪』を見ながら身支度する。空は今日も曇っているが、気温は意外にも高いようで、汗がパジャマにじっとりと染みこんでおり、脱ぐと胸や首のあたりがペタペタした。チャンネルをそのままにしておくと、番組は『サタデー総合研究所』に変る。経済評論家の財部某とユンソナが出ている番組だ。今日のテーマはブラジャーである。シリコンみたいな素材でできた、胸に貼りつけて使うカップ状のブラジャーに驚愕する。モデルがそれをつけたまま、縄跳びしても、水泳しても、ブラジャーは胸に吸いついたままで剥がれない。しっかりしている。下着もテクノロジーの時代なのだなあとつくづく思う。男にとって、ブラジャーはかなり遠い存在だ。女物のパンツをはいたときの装着感はなんとなく自分でも想像できるが、ブラジャーは全然イメージできない。だから、この貼りつけブラジャーの装着感なんて、もうぼくの想像の域を越えている。
十時三十分、事務所へ。O社PR誌、B社PR誌など。昨日ラジカセさえ壊れなければ、今日出勤することもなかったのにと考えるが、まあしかたない、ツイていなかっただけだと割りきって仕事する。
夕方より吉祥寺へ。夏物のセットアップがここにきて急に数着ダメになったので、予定外ではあるが新調することにした。パルコのワイズフォーメンで、裏地も肩パットもないサマーウールのジャケットと、おなじ素材でできた紐で絞ってはくタイプのパンツを購入。店員さんに、今来ているコットンのセットアップが急に痛んできたので仕事では着れないから困っているといって痛んでいる箇所を見せてやると、ああこれは手洗いして一年くらい寝かしておくといい感じに熟成しますよとアドバイスしてくれた。綿素材は経年による素材の変化、彼のいうところの「熟成」が起きるらしい。ワイズの服ははじめからそれを想定してつくられているようである。手洗いと彼がいったので、自分の家で洗っちゃっていいのかと聞くと、この素材ならタンブラーで回しても問題ないと教えてくれた。ただし、合成洗剤は使わないほうがいいらしい。ついでだから、いろんな服の洗濯方法を教えてもらった。カミサン、真剣に質問している。
二十時過ぎ、帰宅。スーパーで買った刺し身で夕食。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』。風呂のなかですこしだけ読む。
-----
六月十五日(日)
「インチキ中華鍋」
十時過ぎ起床。雨はやんでいるようである。ゆっくりと、躯を目覚めさせるようなペースで片づけと掃除を済ませる。
十一時すぎ、遅い朝食、いやブランチ。テレビ東京の『ハローモーニング』を観る。とくに感想はない。最近ソロデビューが発表されたなっちには、今後もがんばってもらいたいと願いながら番組を観た。
午後からは読書。渡部直巳氏の評論、『群像』など。
十六時、スーパーへ。クリーニング店で、料金について少々もめる。
夕食はインチキ中華鍋。鳥ガラスープに鶏肉団子、もやし、チンゲンサイ、水菜などを加え、中国醤油とラー油で食べる。締めは残った汁を使ったラーメン。美味。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』。日曜画家のエピソード。随所に断片的に現れる。
-----
六月十六日(月)
「随分と意志薄弱」
八時起床。今日も頭痛がするのはやはり宿酔いなのだろうかと夕べの記憶を辿ってみるが、ビールは三三〇ミリリットル缶を一缶しか空けていないのだから、これしきで頭が痛くなるわけがない。もう一度辿りなおすと、ダウンタウンの『ガキの使いやあらへんで』の山崎邦正とモリマンの対決を観ながらザ・グレンリヴェット十二年が瓶の底から二センチくらい残っていたのを、全部ストレートで飲んでしまったことを思いだした。これが原因か、と思いつつも、これでシングルモルトのスコッチは全部なくなってしまったから、新しいのを調達しなければと同時に考えている自分はかなりの阿呆で、かつアルコール依存症に陥っているのだと思う。しかし、これくらいあれこれと考えをめぐらすことができるのだから、宿酔いといっても程度はたかがしれているし、ひょっとしたらアルコールによる頭痛ではないのかもしれん。肩凝りや首の凝りからくる頭痛ということもある。そういえば、先週は連日午前様だった。その疲れだろうか。
九時、事務所へ。天気予報は雨だと断言していたが、空に浮かぶ雲に雨雲に固有な陰鬱さは感じられず、これは当面降らないのではないかと勝手に予測し、天気予報をくつがえしてみる。だが、しっかり傘は携帯している自分は随分と意志薄弱だと思う。
B社PR誌、E社カタログ、O社PR誌など。十七時、代官山のJ社へ。O社プロモーションのコンペの打ちあわせ。二十時終了。帰社後、E社カタログをすこしだけ作業してから帰宅する。二十二時。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』ラスト前の章。ちょっと前衛的すぎるよなあ。
-----
六月十七日(火)
「湿り気と戦うわたくし」
よくわからん夢をたくさん見たせいだろうか、五分ばかり寝坊するが、だからといって一日のリズムが、そして朝の洗顔から出勤までの一連のマニュアル的な「やるべきこと」が、なしくずしになってしまうわけではない。いつもとおなじ朝だ。外は小雨がぱらついていた。五分早く起きることができたとしても、おそらく景色も天気もまるで変わりなかったんだろうなと思いながらカーテンを開け、鳥たちの籠にかぶせた布カバーを取り外す。
九時、事務所へ。家を出てから数分がすぎるまでは、湿り気がありすぎて息が詰まりそうになる空気も気温がさほど高くないためだろうか、決して不快な感じはしなかったのだが、事務所が近づくにつれ、躯の運動量は増え体温は上がり、事務所の鍵を開け朝刊を握りながら靴を脱ぐころには、ジャケットの下は汗でいっぱいになっている。エアコンをドライにセットし扇風機を回すがしばらく汗はひかず、上気したままだから企画モノの仕事なんてとても手につかない。チャイを飲みながら汗が引くのを待ったが、チャイのスパイスには発汗を促進する作用があるのではないかと飲みだしてから気がつき、ああおれって馬鹿だなとつくづく思う。
O社のプロモーション企画に終始する。午後、荻窪へ行き資料集め。ルミネの四階に入っている書店で、内田百
間(ほんとは「門がまえに月」ですね)『ノラや』を衝動的に購入する。
二十時、帰宅。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』読了。エクリチュールにただひたすらこだわることで成立している作品、といったら金井氏は怒りだすだろうか。徹底した描写、頻繁な主格の入れ替わりと曖昧化、くり返されるイメージと暗喩、はじまりもなければ終わりもないような、メビウスの輪的な作品構造と、特徴をあげればきりがない。個人的には、これは小説というよりも「詩」に近いんじゃないかと思う。「映像詩人」と呼ばれたタルコフスキーは、自分の作品でよくおなじシーンを、ゆっくりゆっくり、動いているのか動いていないのかわからないようなロングスパンでカメラを回し、ひたすらにその絵を追い続けたりするのだが、それを、カメラのかわりにエクリチュールでやっている、そんな印象を受けた。それ以上のことは正直いってよくわからん。凄さは感じるが、それがなぜなのかがわからん。確信をもっていえるのは、自分はこの作品が好きになったこと、時間があれば再読してみたいこと。そのふたつだ。
-----
六月十八日(水)
「夢疲れ」
花子にご飯を与えてから二度寝に突入する五時くらいから八時に目覚まし時計がなるまでの三時間に夢が集中しているようである。散漫で、主格がなく、場所も特定できず、時代も時間の経過もわからない、とても説明のできないような夢がつづくかと思えば、ときにはおなじく説明のできないような内容なのだが、それは抽象的すぎるとかいうレベルの話ではなく、ただたんに、ちょっといやらしい内容であるだけだったりもする――もちろん、そんな夢を見るのは数えるほどでしかない――、いわゆる淫夢のようなものをみることもある。抽象的な夢というのが、ぼくの場合は圧倒的に多い。かと思えば明確な物語になっていることもあるのだが、いずれにせよ、ぼくにとって夢とは少々やっかいな代物で、その内容にかかわらず、目を覚ましたあとは異常に疲れていることが多い。ここ数日、毎日夢を大量に見る。だから少々疲れ気味だ。ひょっとしたら梅雨のじめじめした蒸し暑い空気が原因なのかもしれない。紫陽花にみとれたりすれば解消できるかも、などと考えた。
九時、事務所へ。泣きだす寸前の女の人のような空模様だが、まだ涙は流れてこない。十二時ごろだろうか、作業の気晴らしにベランダへ出て外へ手を伸ばし掌を空へと向けてみたら、ぽつりぽつりと涙が垂れてきた。今日の空は、静かに泣くタイプの女か、などとくだらないことを想像する。きっと嫉妬深いのだろう、などと想像は尽きないのだが、こんなことばかり考えているから仕事の能率が悪いのだろう。自重せねばとは思うのだが、やめられない。
日中はO社プロモーション企画に専念。ときどき空模様の様子見。
十八時、九段下のナントカホテルへ。ロビーにあるカフェでE社プロモーション企画の打ちあわせ。オリエンテーションの内容が理解できず、苦しむ。
二十時、帰社。E社プロモーションのキャッチフレーズを考えてから帰宅する。0時。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』を読みはじめる。悪夢のなかで殺戮ゲームに参加しつづけなければいけない女の話。夢をテーマにした小説は数あるが、これはかなりエグイほうの部類に入るだろうな。笙野頼子は寝るまえにベッドのうえで『愛猫外猫雑記』も読みすすめているから――こっちは一日一ページとか二ページの超スローペースだが(眠くて読めなくなるのだ)――、おなじ作家の本を二冊同時に読んでいることになるのか。ふうん。
-----
六月十九日(木)
「ふふん。」
八時起床。九時、事務所へ。今日も一日中企画モノに集中していたので、頭が飽和状態になってしまった。中途半端に壊れたサウナみたいな熱さと湿気のコンビネーションが、飽和状態を加速させる。飽和というより、表面張力といったほうが的確だろうか。緊張感は高まるばかりなのだから。
ヤフーショッピングから、注文していた本が届く。阿部和茂『アメリカの夜』『インディビジュアル・プロテクション』、保坂和志『季節の記憶』、後藤明生『小説は何処から来たか』。
笙野頼子「レストレス・ドリーム」をすこしだけ。こういう方法もあるんだなあ、と納得。たしか、この作品が書かれたのは九一年。バブル真っ盛りのとき、というわけか。ふふん。
-----
六月二十日(金)
「オナガの『ギョエー』で涼を取る」
日中の緊張の度合いが高すぎると、睡眠は深くなるようだ。昨日も今日も、夢は見ていない。いや、見ていたがそのあとの睡眠が深すぎて忘れてしまったといったほうが正しい。花子たちの朝ご飯をあげたのが七時三十分。それまで目をまったく覚まさなかったとは、花子もさぞかし困ったことだろう。このオッサンいつまで寝てるんだろさっさとご飯をちょーだいよマッタクという文句が聞こえそうだ。
九時、事務所へ。天気予報が東京の最高気温は三十一度、真夏日になると報じているのを聞くとたちまち気力は萎え暑さといっしょに緊張感が溶けだしてしまいそうになるがそんなことをいっていたらせっかくいただいた仕事をしっかりこなせるはずなどないので、暑さを理由に仕事の効率を落とす、すなわちチョコチョコさぼりながらダラダラと仕事を進めるというのは禁止にしようと自分を戒めるが、躯は正直なもので、窓を開け扇風機を回したくらいでは十分の徒歩通勤ですっかり上気してしまった躯のあちこちから吹きでる汗はそう簡単には引いてくれず、しかたなしにエアコンをドライモードにセットすると、やっと冷静になって仕事に取りかかることができた。十五時ごろ、ようやく企画書を書き終える。J社のIさんにメールで納品し、電話でこの後の予定を確認しておく。
時間が空いたので、事務処理のために法務局へ行く。清水二丁目のバス停から法務局へ行くまでの道は意外に長いがこのあたりは住宅地なので駅前によくある放置自転車や路上に坐る若い衆のような道を遮る障害物のような存在もなく、もちろん静かなので歩いていて気持ちよく、企画づくめで狂いそうになっていたぼくにはちょうどよい気分転換になると思いながらも、やはり外は暑く汗が午前中よりさらに勢いよく吹き出してくるようでイヤになるが、ふと空を見上げると電線にしっぽの長い鳥が留まっているのを見つけ、目を凝らしてみるとそいつはどうやらオナガらしい。ウチの近所ではあまり見かけないなあ、はて最後にこの鳥を見たのはいつだったろうかなどと考えていると、そのオナガが留まっている電線のすぐそばに建てられた家の庭、これがほとんど雑木林のようにしか見えないのだが、その庭の中から「ギョエー」とか「ゲエエー」という鳴き声が聞こえてくる。もちろんオナガの鳴き声である。密生しているらしい。この一瞬だけは、暑さを忘れた。オナガの『ギョエー』で涼を取ったということになるのか。いや、涼しいなあとは思わなかったのだから、この表現は適切ではない。
そのまま吉祥寺へ移動。パルコブックセンターで、金井美恵子『文章教室』『タマや』、古井由吉『槿(あさがお)』、それから元マイクロソフト社長の成毛眞氏のマーケティングの本を購入(タイトル忘れた)。つづいて二階のセゾンカウンター(なのかな?)で、届いたDMを渡して引き換えプレゼントのローズヒップティをもらった。最後にワイズフォーメンへ。先日購入したセットアップのパンツの裾直しが上がったので、引き上げる。店員さんに「イソハタさん、アロハとか好きっスか」と聞かれ「へ? アロハ?」と確認すると、店員は見せたいものがあるといいながら奥の在庫を収納した倉庫のような場所へ行き、限定品らしいアロハシャツを出してくれた。全体的に色度、彩度のない墨っぽい色調だが、開襟シャツだし、南国を思わせる花が描かれているからやはりこれはアロハなのだろう。目を凝らすと、花にまぎれてしゃれこうべが描かれている。これはいかにもヨウジらしいではないか。数年前のコレクションに「ドクロ」があったが、そのときを彷彿とさせる。店員は買わせたかったようだが、あいにく今シーズンは買いすぎている。フトコロのリミッターが効いた。食指は伸びなかった。
十八時、帰社。バタバタと電話連絡をしてから店じまい。二十時。
カミサンは今日から従姉の結婚式のために関西に行っているので、夕食はひとりだ。お気に入りの「ぼんしいく」で、ビールを晩酌しながら小説を読み、適当なところで定食を食べた。豚バラと鶏のフィリピン風煮込み定食。メインより、トマトとシラスを和えた副菜のサラダのほうが気に入ってしまった。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。風刺小説か、これは?
疲れたので二十三時に寝る。おやすみなさい。
-----
六月二十一日(土)
「糸状菌と頭痛」
八時三十分起床。今日も真夏日らしく、陽射しは朝から鋭く、暑い。
九時三十分、きゅーを連れて都立家政にある中野バードクリニックへ行く。きゅー、体重は増えはじめているがまだ体内の糸状菌はさほど減ってはいないという。薬が今日から変る。
帰宅後、読書など。だるいので、すこし寝る。頭痛がひどい。
夕方、スーパーへ。帰宅後カレーを作ってひとりで夕食。頭痛がおさまらないので早めに寝る。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。
-----
六月二十二日(日)
「なにもしない」
九時起床。昨日ほどは暑くない。一日読書と書き物をして過ごす。ほんとにそれだけ。あとはなにもしていない。テレビもほとんど見なかった。背中が痛む。腰も痛む。頭痛もやまない。夕方ごろになると痛みが最高潮に。早く寝ることにする。二十三時ごろカミサンが帰ってきたが、起きることができない(※このあたりは次の日に書いている)。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。自虐小説か、これは。
-----
六月二十三日(月)
「背中が痛い」
四時、背中の痛みで目が覚める。横で花子がミャーミャーと鳴いているのに気づいたのでご飯をあげなければいけないという使命感から背中と腰をかばいつつそろりそろりと起きあがり、キッチンまでなんとかたどりつき、やっとの思いで猫缶を開ける。厠で小用をたすが、放物線を描く尿のほうに視線を合わせると背中がひどく痛んで苦しい。
七時、痛みでふたたび目が覚める。もう一眠りしたいところだが、残念ながら睡魔は痛みに負けてしまい、ぼくは苦しみながら蒲団のうえでコロコロと寝返りを打つのだが、どんな姿勢を取っても背中の痛みはおさまらず、どうしようかと悩んでいたら目覚ましがなった。起きると左足の腿からふくらはぎにかけてがビンビンにつっぱっているのがわかる。尻の左側のほっぺも痛い。大腿神経痛ってヤツだろうか。ヒーヒーいいながら身支度し半ベソをかきながら家を出る。雨が降っていなかったのがせめてもの救いだ。この状態で傘をさすなんて、拷問にひとしい。
九時、事務所へ。痛みと湿気の不快感のダブルパンチに打ちのめされながらも、こんな状態だというのに掃除は怠らない自分はなんて偉いのかはたまた馬鹿なのか、いったいどちらなのだろうと考え、馬鹿だという結論に至る。馬鹿は死ななきゃ治らないというが、背中の痛みはカイロに行けば治るだろう。ということで、かかり付けの木村カイロプラクティックへ電話し、症状を話すと十一時に来てくれといわれる。行きますとも行きますとも。十時四十五分くらいまで時間が空いたが、とても企画を練ったりキャッチフレーズを考えたり長い文章を書きつづったりするような状態ではない。痛みで集中できないのは過去の経験からわかりきっているので、この時間は割りきって事務処理に充てることにする。
カイロでは、ひどく躯が固くなっていると診察された。はじめてここに来たときとおなじくらいのひどい状態らしい。おそらく原因はストレスだろう。自分でも気づかないうちに、鬱積するものが溜まっていたようなのだ。仕事をいただけるのはありがたいことだが、無理が重なると知らず知らずのうちに躯が錆びはじめ、気づくことなく勢いだけで激務を乗りきろうとすると、休みきれていない躯は悲鳴を上げ、ストライキを起こしはじめる。そういうことみたいだ。
午後からはE社のパンフレットの企画に専念する。こんな状態なので、早めに帰宅することにした。二十時。
自宅で新聞を読んで、昨日が夏至で、多くの大型施設から電気の光が二時間ほど消える省エネイベントが行われる日であったことに今さら気づいた。そういえば先週の日曜の日経新聞に掲載されていた古井由吉のエッセイは「闇」がテーマだったなあと思い出す。自分の闇はどうやら心と躯のあいだのあたりにあって、そこがあまりにも深く暗く沈んでいたので、躯がおかしくなったのではないかと考えてみると、このイベントの日と症状の悪化が重なったのは少々イヤミな偶然だ。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。虚構の構築力もまた作家の才能のひとつ。どこまで嘘をつけるか。コピーライターは本当のことを表現することで本当の価値を消費者に伝えるが、作家は嘘のことを表現して真実や真理を模索しそれを読者に伝える。
-----
六月二十四日(火)
「雨が降りてくる」
四時、猫ご飯で起床。今になって思い返すに、このときぼくはまったく背中の痛みを意識していなかった。
七時、目覚ましが鳴るよりだいぶ早く目が覚めた。背中は痛まない。もう一眠りしようかと思うが、背中が快方に向かっていることに興奮してしまったのか、眠ることができない。足元で寝ていた麦次郎をつま先でうりうりと突っついてみたり、胸のうえに乗ってゴロゴロと喉を鳴らす花子の後頭部をポリポリと掻いてやったりしていたら、目覚ましがなってしまった。八時。少々眠い。
九時、事務所へ。朝からE社のパンフレットの企画に専念する。午前中になんとかカンプ用のコピーを書き上げ、デザイナーにメールで送信。午後は企画書づくりだ。イラストはカミサンにやってもらうことにした。二十二時三十分、夫婦揃って帰宅。
梅雨時は台風でも来ないかぎり強い風は吹かないようだ。雨粒は風に流されることなく、空からスッと降りてくる。雨足もさほど強くはならない。気がつくと、うっすらと曇った空からシトシトと細かな雨が降りてくる。降ってくる、というよりも、降りてくるといったほうが正確のように思えるのは、雨足が夏の夕立よりもゆっくりしているからだろうか。大きな花が重たそうな紫陽花があちこちで咲いているが、風は無風に近く、雨足も弱いせいだろうか、花も葉も茎も、揺れることなく、ただじっと雨が降りてくるのを見届けている。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。この作家は「うんこ」ということばが好きらしい。ぼくも好きだ。
-----
六月二十五日(水)
「餌を待つ子ら」
昨日の日記に「梅雨時は台風でも来ないかぎり強い風は吹かないようだ。雨粒は風に流されることなく、空からスッと降りてくる。雨足もさほど強くはならない」と書いたばかりだというのに、夕べは雨音のけたたましさについ目を覚ましてしまった。マンションの裏手に流れるコンクリートの川の水面を打つ雨の音は夜の静けさに反響して増幅され、外の冷えた空気を取り入れようとすこしだけ窓を開けておいた寝室に、外気といっしょに流れ込んで、眠るぼくらの耳を打つ。
八時起床。背中はほとんど痛まないが、尻のほっぺがまだ痛む。万全になるまでにはまだちょいと時間がかかりそうである。時間がかかるということは、お金がかかるということと同義だ。今まで以上に稼がねばと思うが、今回の腰痛や背中の痛み、坐骨神経痛は明らかに働き過ぎが原因なわけだから、仕事をほどほどにしないかぎり、ぼくはいつまでもこの痛みと付きあい続けなければならないというジレンマがある。現代人には体調不良の無限連鎖を生みだす才能があるようだとつくづく思う。
九時、事務所へ。朝のうちはまだ雨が降り続いている。昨日の雨は「降りてくる」ということばがよく似合ったが、いくぶん風が強く、やや横殴りでぼくらに迫ってくる今日の雨は、やはり「降る」といったほうが正しい。風は強かったが、紫陽花の花はさほど揺れてはいなかった。そばで見れば、風の強弱に合わせて小刻みに震えているのがわかったかもしれない。
E社パンフレットの企画、デザインカンプのチェックなど。昼ごろになると雨が止んだので、月末恒例の銀行巡りをする。自分たちの給与振込、通帳記入、事務所の家賃の支払い、売掛金の振込確認など。すべてを済ませたころには雨雲はすっかり姿を消し、青空がすこしだけ顔をのぞかせていた。風には空の表情を変える力があるようだ。傘をもつことの煩わしさから解放されたのが、青空のおかげで強く実感できる。うれしくなり、銀行巡りのあとは五日市街道のほうまでちょっと散歩してみる。普通のサラリーマンが日中にこんなことをしたらサボりということになるが、ぼくはフリーランスだからそんなことは気にしない。アンティークショップがちらほらと見えるが、ほとんどのお店が西洋骨董だけでは喰っていけないらしく、リサイクルショップを兼ねて営業している。杉並区民はリサイクルということばの響きに弱いから、戦略としては正しいのだろうななどと、青空にまったく似合わないマーケティング的な考えに囚われながら歩き続けると、元スポーツショップだったらしい空き店舗の軒先に、ツバメが巣をつくっているのを見つけた。まず、鳴き声が聞こえた。せわしなく「ピーピー」「キーキー」と鳴き続ける鳥がいることを耳が察知する。目を凝らすが、巣は見えない。音だけをたよりにヒナたちのいる場所を探すと、一羽のツバメが目の前を横切った。ツバメの軌跡を追う。すると巣はすぐに見つかった。見せの入り口の上にかけられたビニールテントみたいな庇(あれ、なんて呼べばいいんだろう?)の裏側に棚が作ってあった。そこにツバメの若鳥が六羽ほど留まっている。若鳥たちは口を開け、鳴きながら親鳥が餌を運んできてくれるのを待っている。巣立ち間近なのだろうか、からだの色はくっきりとしていて、首を彩る赤い部分も鮮やかだ。飛ぶ練習をするところを見てみたい、と思った。
十五時、事務所に戻る。事務処理、そして引き続きE社の企画。二十時三十分、帰宅。
夕食は餃子鍋にした。お手軽。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。多重構造の夢? 多重構造の小説?
-----
六月二十六日
「」
八時起床。九時、事務所へ。いつ降りだすか、いつ降りだすかと空ばかり見てしまう。午前中は銀行や郵便局へ。数軒をはしごしたが、空はぐずつく寸前のところでグッと涙をこらえている。
午後、阿佐谷の商工会議所へ。すっかり様変わりし、吉祥寺の東急裏あたりよりもよっぽどきれいになった中杉通りに違和感を覚える。十五時、いったん帰社し、荷物を入れ替えてからL社へ移動。T氏、N氏とL社のなかでもはしごする。十九時三十分、帰社。雨はまだ降りださない。移動中はひどく傘が邪魔になった。事務所に戻ると、たちまち天気がくずれた。開け放った窓からは夜の冷気ではなく、雨音ばかりが流れ込んでくる。雨足は強く、アスファルトを打ちつける音がけたたましくて妙に気になり、仕事が手につかない。二十二時、帰宅。このころになると、雨はもう止んでいた。梅雨時の雨は、じつは気まぐれである。
夕食は焼き肉屋にて。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。作者が本当に書きたかったのは「ことば」のことなのかな、なんて感じる。
-----
六月二十七日(金)
「」
四時四十五分、自然に目が覚めてしまう。厠が近くなったわけでもなし、花子がうるさかったわけでもなし。理由がわからず、すこしだけ戸惑ったが、ああ猫にご飯をあげなきゃいけないんだよなと、まだ半分寝ているらしい頭で途切れ途切れに考えながら、ついでだと思い厠にいって途切れ途切れに小便をし、よく手を洗ってから猫缶を開けたのだが、これが少々早すぎたようで、花子は不覚にもぐっすり眠ってしまい、ぼくがこうして早朝に食事の準備をしていることに気づかない。皿にマグロのナントカを盛りつけ、猫用ランチョンマットを敷いた床に置き、花子のことは呼ばずにそのまま寝室へ戻ろうとすると、廊下で花子がぼくのことをじっと見ている。どうやらたったいま起きてきたらしくて、「なんでまた寝ようとしてるの? ごはんをちょーだい」といわんばかりのまなざしで、ぼくを見つめるのだ。ぼくは花子を連れて台所へ向かい、「ごはん」ということばを口にすると、花子は「なんで? 先に用意してくれてたの?」といいたそうな顔でチラリとこちらを見てから、無我夢中でマグロのナントカを食べだした。おかげでかなり目が覚めてしまったが、蒲団に入るとすぐに寝つけた。
八時起床。九時、事務所へ。E社のセールスシートの構成とコピーライティングに取りかかる。
夕方、三鷹のドコモショップへ。動画が撮れるテレビ電話、FOMA P2102Vを購入する。ドコモショップでは、調べたかぎりではここがいちばん安かった。これで手軽に写真メモや動画メモが撮れる。
二十三時、帰宅。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。最終章に突入。といっても、全部で四章しかないのだが。
-----
六月二十八日(土)
「ミレーの暗さ/写真も服も」
八時三十分、マンションの裏手にある家屋の解体工事の音で目が覚める。六階建てのマンションが建設されるというので、近隣の一戸建て住宅に住む人たちは反対運動をしているようだ。塀や壁に「軟弱な地盤に六階建て マンション建設反対」などと書かれた横断幕をでかでかと貼りだしている。解体はもう数日続きそうだ。
十時、テレビ朝日の『サタデー総合研究所』を見る。リストラされたサラリーマンの再起のドキュメンタリー。自転車メーカーを解雇された四十代後半の男は、その後無店舗の修理専門自転車屋に転職。路頭に迷った末の決断だったらしいが、以前は多かった家族に対する突然の激昂も今ではなくなり、むしろ人生は充実しているという。そんな生き方をしている人を数人、紹介していた。
十時三十分、渋谷へ。文化村で開催されているミレー三大名画展を観る。案の定、ひどい混雑で絵の全体を見ることができない。構図を捉えようとすると、下の方にはおばちゃんたちの頭が並んでいて、肝心の部分をすべて隠してしまうのだ。ミレーの作品には人だかりができていたが、ミレーと同時代に生きて自然主義の作品を残したほかの画家や、ミレー以降に自然主義の流れを汲みつつ独自の世界を模索した画家たちの、いいかえればミレーほど著名ではない、美術史に埋もれがちな画家たちの作品のまえには人は集まらない。
多くの人たちが、五百円を払ってイヤホンによる作品解説サービスを利用していた。正直いって、これには反対である。まずは自分のなかにある知識や感性の下地だけを頼りに、素直に絵を鑑賞すべきである。美術史上のポイントやら時代背景やら制作上のテクニックやらは、そのあとに調べたって遅くはない。知識の習得と絵の観賞を同時に行ったら、鑑賞のほうがおろそかになるのは明らかだ。知識ばかりに関心が向かうあまりに美しさを感じる心を失ってしまった者には、芸術を観る視覚などない。
客の話はさておき、ミレーである。三大名画、いずれも本物を観るのはもちろんはじめてである。三大名画に限らず、ミレーの作品はほとんどが十九世紀の生活者、それも農民という多数派ではあるが限られた階級のみを素材としている。いずれの作品も、セピア調の色彩と「暗さ」が印象的だ。厚い雲を通って地上に柔らかに降り注ぐ、決して明るくはない陽の光をバックに、農民はうつむき、地面を見つめながら農作業に没頭する。弱々しい光を背にした彼らの姿はよりいっそう暗くなる。この「暗さ」が、十九世紀の労働者階級の実情を物語るものなのだろうか。生活全体をすっぽりと覆っているように見える「暗さ」、薄明かりのなかでの生活というものは、電気という文明の利器に恵まれ、つねに明るく平坦な照明のもとで生活している――いや、生かされているといったほうが正確だろうか――現代人には、直接的には理解できないのかもしれないと強く思った。ミレーは人々をなぜ暗く描いたのか。ぼくの勉強不足のせいなのだろうが、その理由がまるでわからない。ひょっとすると、人間とは光を求めるために生きる存在なのかもしれない。だとしたら、人間の本質とは光ではなくて「暗さ」であり「闇」である。もしこの仮説が正しければ、ミレーは人間の本質を――おそらくは直感的に――知り尽くしていて、それを農民の生活を通じて描こうとしていたのではないだろうか。闇がなければ星も光ることができないといったのは誰だったろうか。ミレーは逆に「光がなければ、人間の本質である暗さを描くことはできない」と考えたのかもしれぬ、などと『落ち穂拾い』などの、光と影の微妙なコントラストのなかで生えるセピアの色彩美に酔いしれつつ考えた。その一方で、邪魔なおばちゃんたちの頭を思いきり左から右へ順番にパシパシひっぱたいてやろうかと別のことも同時に考えてしまう自分には、ひょっとすると芸術を鑑賞する資格などないのかもしれぬとも考えた。芸術というものはつくづつタチの悪いものだと思う。
渋谷から大崎へ移動。カミサンに、ぼくがアドトレイン広告を担当したゲートシティ大崎を見せてやる。カフェ・ハイチでハイチ風ドライカレーとハイチコーヒーで昼食。カミサンはここの静かさと堅実さが気に入ったようだ。しきりに友だちと先日行ってみたが幻滅したといっていた六本木ヒルズと比較している。
つづいた品川にある原美術館へ。ヨウジヤマモトの広告用写真の作品展が開催されている。ワイズやヨウジの服を愛し、高えなあ分不相応かなあと思いつつもオンタイムの服はほとんどこれらしか着ないようになってしまったぼくら夫婦としては、この作品展を見逃したら、死んでも後悔するにちがいない。
原美術館ははじめて訪れるが、基本は現代美術らしい。常設作品が何点かあったが、それらはすべて美術館の建物の一室と化しており、かつこの美術館の方向性を明確に主張できる内容のものばかりで、芸術好きとしてはたいへん興味がもてた。ただし、それらの作品が自分の好みに合うかどうかは別問題。
ヨウジの写真は、いつもはポスターやダイレクトメール(ハガキ)で見慣れていたものを、改めてオリジナルを大判で観ることになる。もちろん観たことのないもの、も多かった。古くは八四年の作品も展示されていた。作意に満ち趣向を凝らしたそれらの写真は芸術作品として充分愉しめたのだが、ファッション好き――というよりもヨウジの服好き、ヨウジヲタだ――でもあるぼくは、服の美しさのほうにも気がとられてしまう。つまり、二重に愉しめる内容だったということだ。帰りにミュージアムショップで写真集とコレクション時のBGMが収録されたCDを一枚購入し、退館する。
夜は義母の家へ。インターネットを使いたいというので、オンラインサインアップを手伝ってあげた。手巻き寿司をごちそうになる。桃子ともすこし遊ぶ。ちゃんと覚えていてくれているようで、うれしい。義母特製の梅酒を一本もらって帰る。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。ミレーとヨウジで頭のなかがちょっと飽和状態に近くなっていたせいだろうか。集中できないので四ページくらいで読むのをやめた。
-----
六月二十九日(日)
「足指にいろんなものを挟んでみよう」
九時起床。身支度をして三十分ほどしたがカミサンはまだぐーすかと寝ているので、フェルトでできた五センチ×二センチほどのティアドロップ型の花子のおもちゃを足の親指と人さし指のあいだに挟んでみる。起きないのでそのままにしておく。五分後にもう一度様子を見にいくと、まだぐーすかと寝ている。今度は先ほどとおなじ足の薬指と小指のあいだに、駅前かどこかでもらったキャバクラのフロアレディ募集の告知がついたポケットティッシュを挟んでみる。まだ起きない。そのままにしておく。さらに五分後、またまた様子を見にいくが状況は変らず、足の異変に気づかぬままカミサンはぐーすかと眠りつづけている。こんどは足の中指に、茎の部分が針金でできた、小さな薔薇の造花――たぶん先週カミサンが従妹の結婚式に出席したときに、花子と麦次郎のおもちゃとしてもらってきたものだ――をくくり付けてみる。これはさすがに変な感じがしたらしく、カミサンはようやく目を覚ました。
外は暑い。真夏日である。いつまでも寝ていると、ひどく寝汗をかいてしまうではないか。こんな日は早く起きてどこか涼しいところに行っちまうに限る。
十時三十分、事務所へ。金曜の夜にやり残してしまったE社セールスシートの原稿などを済ませる。義母から会社のアドレスにメールが来ていた。今朝、さっそく昨夜ぼくが教えたことを実行してみたらしい。義母に限らず、シニア世代は妙に向上心があるよなあと感心した。
夕方、荻窪のルミネでカミサンと合流。猫のご飯、人のご飯などを購入する。十八時、帰宅。
きゅーの具合が悪い。先週あらたに調合してもらった薬に切り替えてからだ。明日からもとの薬に戻しても用と思う。
夕食はお好み焼きでお手軽に。夕べ録画しておいた『二十七時間テレビ』の深夜枠を観る。中居君とさんまの女性に関するトーク。途中、中継でつながった鶴瓶がちんこを出してしまった。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』。最終章、意図的に読者が混乱するような書き方をしているみたいだ。
-----
六月三十日(月)
「匂いの染みた男」
七時三十分起床。妙に物語としての構造がしっかりした夢をみたような記憶があるのだが、肝心の内容はさっぱり覚えていない。だから、みていないのとおなじである。
外は晴れている。ときたまうっすらと広がった雲が陽の光を遮るが、陽射しは明るい。きゅーは元気よく籠のなかを飛び回り、ご飯をもりもりと食べている。陽の光がうれしいのか、薬をもとにもどしたのが功を奏したのか。
八時三十分、家を出る。この時間になると、陽光は雲に押され気味となり、頭上にはお馴染のグレイ・スカイが広がりはじめる。気温は高く少々汗ばむのだが、その汗を爽快なものに転化させてくれるはずの心地よい初夏の風は、残念ながらやって来ない。
E社パンフレットの企画書、おなじくE社のセールスシートなど。月末だから、事務処理も並行して行う。銀行で入金の確認をしようとすると、すでに四十人くらい並んでいる。こういうときは、待つしかない。最後尾にいる男性の後ろに並ぶと、なぜか醤油と古い家具と酒と煮込みを思わせる料理と油が混じったような匂いがしてくる。ひとことでいえば、古めの居酒屋にはいったときに感じる、あの匂いである。匂いのもとを探すと、どうやらそれはぼくの前にいる男性かららしい。彼をよくみると、藍染の甚兵衛みたいなものを着ている。胸元には、近所の居酒屋の店名が刺繍してあった。服に匂いが染み込んでいるのか、彼に匂いが染み込んでいるのか。不快だとか不潔だとか、そういうことではない。ただただ、ふだんいる場所、働いている場所の匂いが染みついているという事実がおもしろいなあと思っただけだ。染みついてしまったのは、きっとその居酒屋の匂いだけではないと思う。
今日は終日下痢だった。六回は便所に行ったと思う。その一回一回が腸と肛門にとっては緊急事態だというのに、いちいち持ち込む本を選び、それを手にとってから便所に駆け込んでいる自分はつくづくアホだと思う。ウンコを漏らしてしまったらどうするのだろう。などと書いてみたが、この言い草はいささか他人事すぎる。漏れたウンコがパンツのなかで途方に暮れる、と読めそうな書き方だなあとあとから思った。漏らして困るのは、ウンコのほうじゃない。ほかならぬぼくのほうなのだ。ウンコに人格はない。栄養もない。
明日も下痢のようなら、病院に行こうと思う。
二十二時過ぎ、帰宅。きゅーは元気である。
笙野頼子『レストレス・ドリーム』読了。異端の夢文学、といってしまえばそれまでの内容。斬新なテレビゲーム文学、といってしまえばそれまでの内容。フェミニズム文学、といってしまえばそれまでの内容。しかし、これらのエッセンスをまさに「悪夢」のごとくごちゃまぜにして、旧来の文学に対し宣戦布告した笙野頼子はスゲエと思う。作中で主人公である桃木跳蛇が戦っていた相手は、物語のあり方であり、旧来の文学形式であり、そしてわれわれが当時直面してた九十年代の「現実」である。戦うための道具、すなわち武器は「ことば」であるが、ことばが武器となりうるということを知らしめようとした作品は、本作以降、どれくらい登場しているのだろうか。『レストレス・ドリーム』文学の潮流を変えるほどのパワーをもった作品であるが、本当に文学の流れが変ったかどうかは疑問だ。
多くの小説家たちの関心は、「ことば」からすこしずつ離れているような気がしてならない八十年代、九十年代の文学は書くための道具自体をテーマにすることで成り立っているように思えるが、二十一世紀にはいってからは「歴史」や「時代」が重視されるようになっている、そんなふうにぼくには思えるのだ。
明日からは、保坂和志『季節の記憶』を読みはじめようと思う。
|